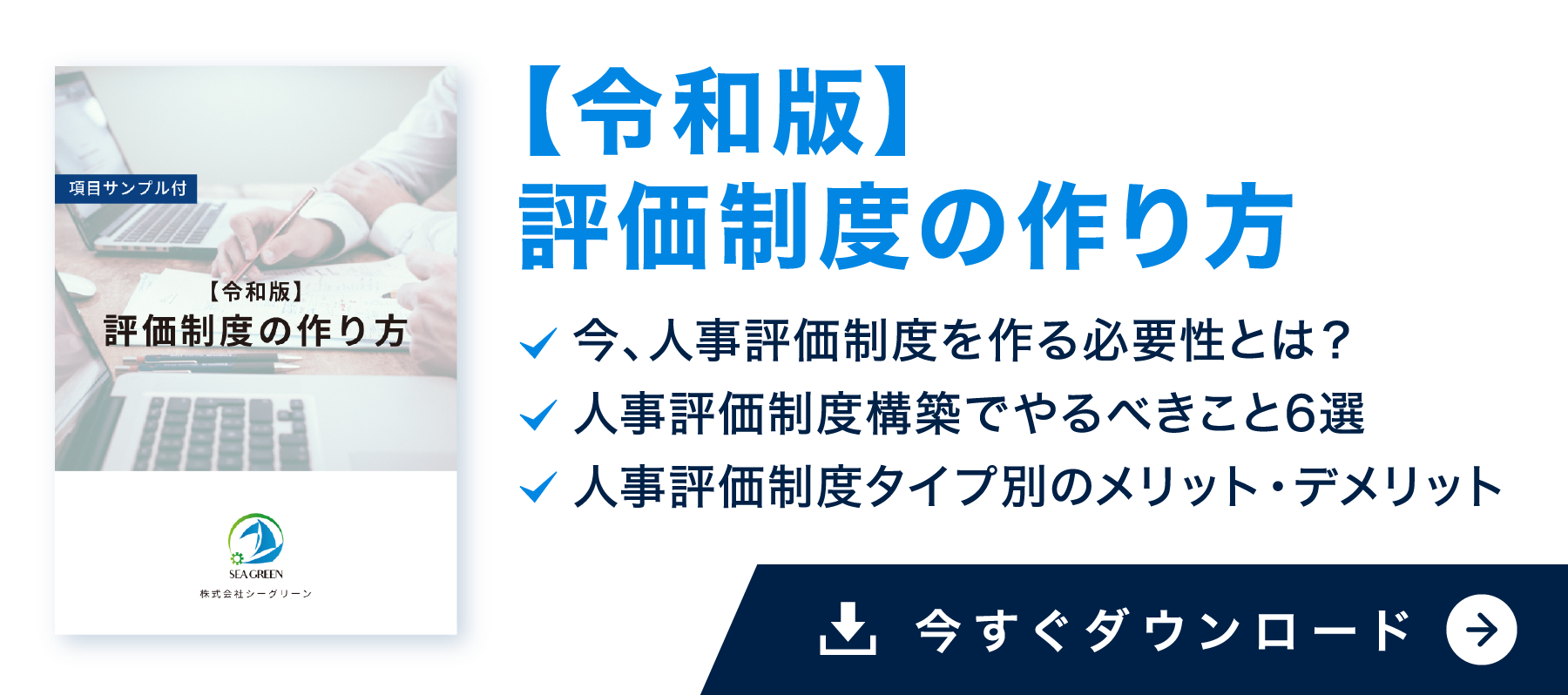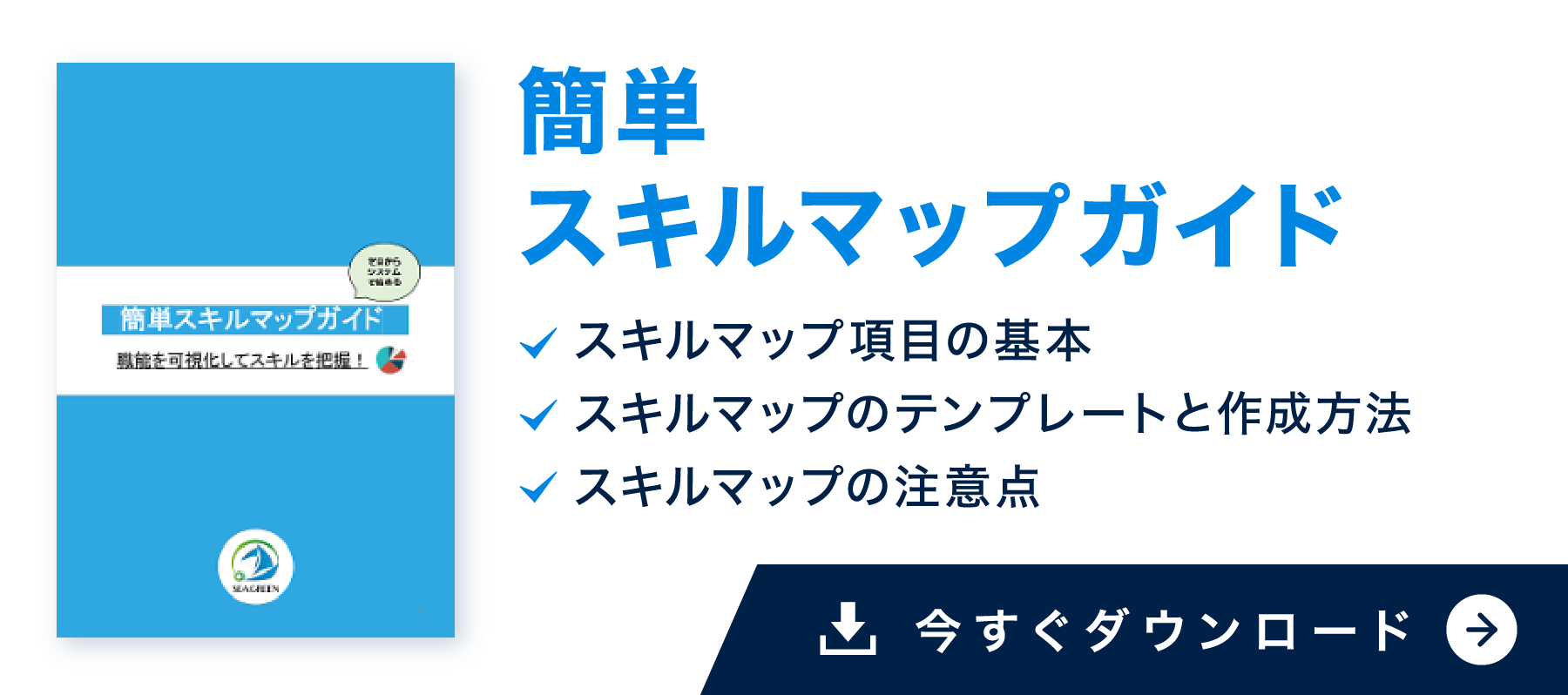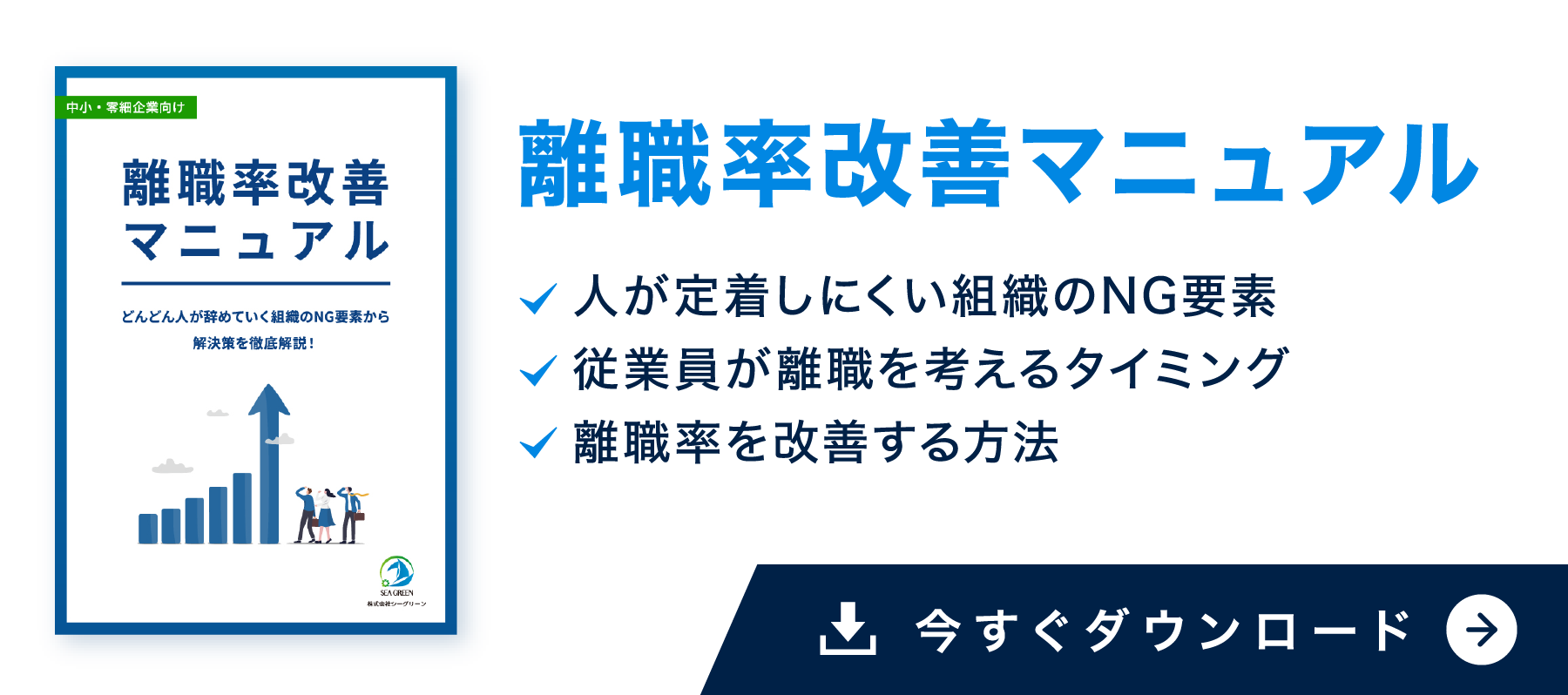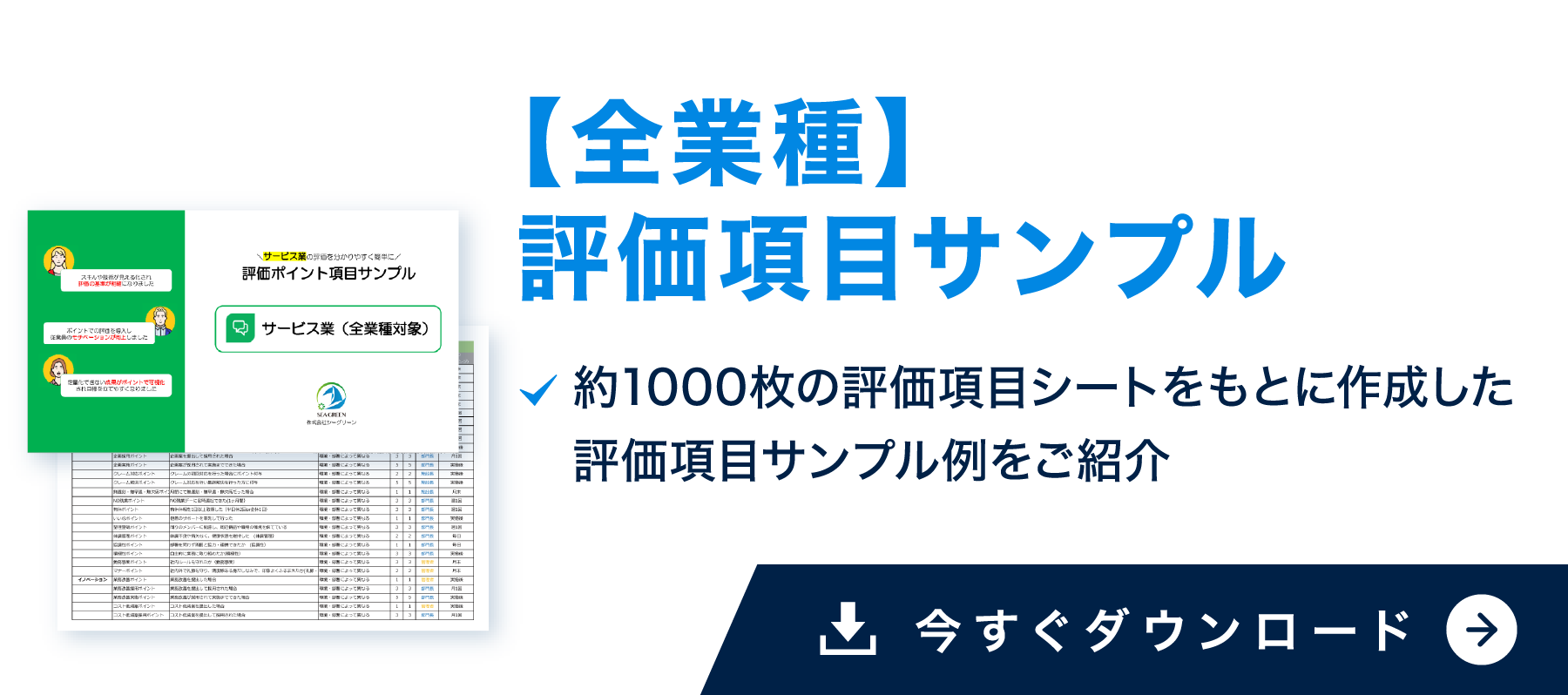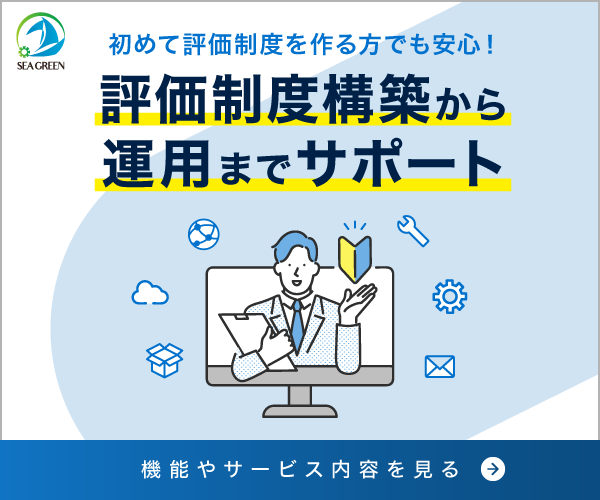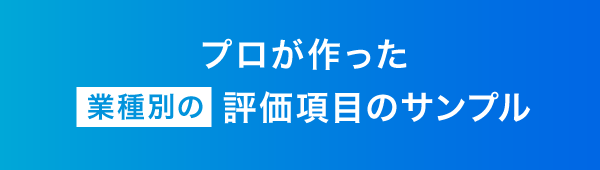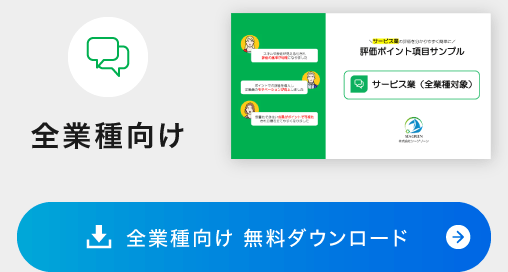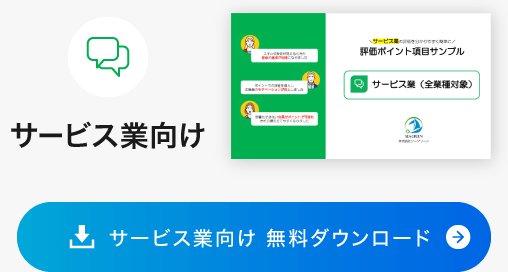人事評価制度を整備しても、運用が複雑だと、制度自体が形骸化してしまうおそれがあります。
こうした課題を解決するためには、使いやすい人事評価システムの導入が効果的です。
本記事では、「使いやすさ」にこだわった人事評価システムの選び方と導入メリットを詳しく解説します。
評価業務の効率化や公平性の担保や従業員の納得感向上など、具体的な課題をどう解決できるのかを整理しながら、自社に最適なシステムを選定しましょう。
目次
使いやすい人事評価システムを導入すべき理由

人事評価制度を見直したくても、現場にかかる負担や複雑な手順に悩む担当者は少なくありません。
そこで注目されているのが、「使いやすい」人事評価システムです。
ここでは、使いやすい人事評価システムを導入する理由を4つご紹介します。
- 複雑な評価業務をスムーズに進められる
- 評価の属人化を防ぎ、公平性を担保できる
- 現場の運用負担を減らし、定着率を高められる
- 評価プロセスの透明性が向上する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
関連記事:【評価システム】おすすめ5選!導入メリットと注意点徹底解説
複雑な評価業務をスムーズに進められる
人事評価業務では、評価シートの配布・回収から進捗管理、集計、フィードバックまで、多くの工程が発生します。
紙やExcelで運用している場合、情報の抜け漏れや作業ミスが起きやすく、担当者が本来注力すべき業務にまで手が回らないことも少なくありません。
優れた人事評価システムを導入すれば、評価項目の自動設定やワークフローの一元管理、リマインド通知による進捗の見える化が実現できます。
煩雑だった業務が効率化され、人的ミスの減少にもつながるでしょう。
その結果、評価の質とスピードの両立が実現し、より戦略的な運用が可能になるのです。
評価の属人化を防ぎ、公平性を担保できる
人事評価においてよくある課題が、評価が上司の主観に左右される「属人化」です。
評価基準があいまいなままだと、評価者ごとの判断にばらつきが生じやすく、従業員の不満や納得感の低下につながります。
このような状況が続くと、組織全体への信頼にも悪影響を及ぼします。
人事評価システムを導入すれば、職種や等級ごとに統一された評価基準を全社で運用することになり、誰が評価しても一貫した判断が可能です。
さらに、360度評価や多面評価といった複数の視点を取り入れやすくなり、より客観性の高い評価が実現します。
こうした仕組みにより、評価に対する納得感と信頼性が向上するのです。
現場の運用負担を減らし、定着率を高められる
評価制度が整っていても、運用が複雑で現場に負担がかかっていては、制度そのものが形骸化するおそれがあります。
評価入力の手順が分かりにくい、対応に時間がかかるなどの課題が大きいほど、従業員のストレスや不満が蓄積してしまうでしょう。
使いやすい人事評価システムを導入すれば、直感的な画面設計とシンプルな操作フローによって、現場の作業負担を大きく軽減できます。
スマホやタブレットに対応していれば、時間や場所を問わずスムーズに入力できるため、評価業務が定着しやすくなるのもポイントです。
使いやすさは、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下といった好循環を生み出す要因となります。
評価プロセスの透明性が向上する
どれほど公平に評価しているつもりでも、従業員に伝わらなければ、評価の透明性は確保できません。
実際、評価に対する不満や不信感の多くは、制度そのものよりもプロセスの不透明さに原因があります。
人事評価システムを活用すれば、評価の進捗や承認フローが見える化され、誰がどの段階で関わっているかが一目で把握できます。
評価コメントやスコアの根拠が記録として残るため、あとから評価の内容を振り返ることも可能です。
こうした仕組みがあることで、従業員は「見えないところで勝手に決められている」という不安から解放され、評価制度への信頼も高まります。
人事評価システムにおける「使いやすい」以外の選定ポイント

ここでは、使いやすさ以外の観点に着目した人事評価システムの選定ポイントを5つご紹介します。
- 自社の評価制度に柔軟に対応できるか
- 組織の規模や業種に合ったシステムかどうか
- 操作性・導入後のサポート体制は十分か
- セキュリティ要件や法令対応の条件を満たしているか
- すでに利用しているシステムとの連携性はあるか
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の評価制度に柔軟に対応できるか
人事評価の仕組みは、企業によって目的や運用ルールが大きく異なります。
用意されたテンプレートでは自社の制度にフィットせず、かえって運用が煩雑になるケースも考えられるでしょう。
評価項目の自由設定や評価者ごとの段階別設定、配点のカスタマイズなどの機能が備わっていれば、現在の評価制度をそのまま反映しやすくなります。
制度の形を崩さずに移行できるため、運用もスムーズに定着するでしょう。
組織の規模や業種に合ったシステムかどうか
どれだけ高機能な人事評価システムでも、自社の規模や業種に合っていなければ、十分に活用できません。
たとえば、店舗数の多い小売業や、部門ごとに評価基準が異なる業種では、それぞれに対応できる柔軟な設計が不可欠です。
また、中小企業と大企業では求める機能や使い方も大きく異なります。
システムの導入実績や対応業種などをあらかじめ確認し、自社に最適なものを選ぶことが重要です。
操作性・導入後のサポート体制は十分か
どれほど多機能なシステムでも、操作が複雑だったり導入後に十分なサポートがなければ、定着せず形だけの制度になってしまいます。
UIの分かりやすさや直感的な操作性はもちろん、導入時の初期設定支援やマニュアルの充実、専任サポートの有無も見過ごせないチェックポイントです。
トライアルで実際の操作感を確かめたり、サポート体制の内容を事前に確認しておくことで、導入後のトラブルを防げます。
関連記事:人事評価システムの導入成功事例15選!「やる気をなくす」人事評価制度を脱却する方法とは?
セキュリティ要件や法令対応の条件を満たしているか
人事評価には個人情報や機密性の高いデータが多く含まれるため、セキュリティ面の対策は必須です。
データの暗号化、アクセス権限の細かな設定、バックアップ体制などは確認したいポイントです。
ISMSやSOC2などの認証を取得しているか、自社のセキュリティ基準やコンプライアンス要件を満たしているかもチェックしておきましょう。
すでに利用しているシステムとの連携性はあるか
人事評価システムは単体で完結するものではなく、既存の人事管理システムや勤怠・給与システムと連携できるかどうかが大切なポイントです。
連携が不十分だと、情報を何度も入力したり、複数のツールを行き来しなければならず、現場の負担が増えてしまいます。
シングルサインオン(SSO)への対応や、API連携・CSV自動取り込み機能の有無など、自社で利用しているほかのシステムとの相性を事前に確認しましょう。
中小企業・自治体にも適した人事評価システムの特徴とは

ここでは、限られた人員でも無理なく運用でき、コストを抑えながら必要な機能が搭載された人事評価システムを選ぶポイントを3つ解説します。
- 導入・運用のしやすさが最優先
- コストを抑えても必要な機能がそろっている
- サポートやマニュアルが充実している
それぞれ確認してみましょう。
導入・運用のしやすさが最優先
中小企業や自治体では、IT担当者や人事専任の人材が少なく、システム導入に多くのリソースを割けないケースが多く見られます。
初期設定が簡単で、マニュアルがなくても直感的に操作できるシステムであれば、導入時の負担が大きくありません。
あらかじめ評価テンプレートが用意されていたり、クラウド型でインストール不要だったりと、誰でもすぐに使いこなせる仕組みが整っているかを確認しましょう。
関連記事:中小企業向け評価クラウド徹底比較!選び方のコツと事例
コストを抑えても必要な機能がそろっている
人事評価システムは高額なイメージがありますが、近年では低コストでも実用的な機能を備えたサービスが増えています。
中小企業や自治体にとっては、評価項目の設定、進捗管理、集計・フィードバックといった基本機能が備わっているかが肝要です。
必要な機能を見極めたうえで、コストとのバランスを重視すれば、無理なく導入できるシステムを見つけやすくなります。
サポートやマニュアルが充実している
操作が難しかったり、トラブル時の対応に時間がかかったりすると、せっかく導入した人事評価システムも現場に定着しにくくなります。
導入時の初期設定支援や操作マニュアルの有無、電話・チャットによるサポート体制が整っているかは確認しておきたい選定ポイントです。
システムに不慣れな担当者でも安心して使える環境があれば、導入効果を最大限に引き出せます。
使いやすさに直結する人事評価システムのUI・UXとは
人事評価システムの使いやすさを左右するUI・UXとは、それぞれ以下を意味します。
UI(ユーザーインターフェース):画面のデザイン、ボタン、文字のフォント、レイアウトなど、ユーザーが目にするもの、操作するもの
UX(ユーザーエクスペリエンス):システムを通じてユーザーが「使いやすい」「わかりやすい」「楽しい」と感じる体験や感情
どれほど高機能な人事評価システムでも、操作のしやすさや画面の見やすさが不十分だと現場に定着せず、使いやすさにもつながりません。
ここでは、具体的なチェックポイントをご紹介します。
- 直感的な操作が可能な画面設計
- スマホ・タブレット対応でいつでもアクセス可能
- 入力や確認に手間がかからない評価フロー
それぞれ見ていきましょう。
直感的な操作が可能な画面設計
人事評価システムを現場に定着させるには、誰でも迷わず操作できる直感的な画面設計が欠かせません。
たとえば、必要な情報にワンクリックでアクセスできる構成であれば、操作ミスや確認漏れも起こりにくくなります。
また、色分けやアイコンによって現在のステップが視覚的に把握できると、初めて使う人でも戸惑わずに評価を進められます。
シンプルで分かりやすいUIは、運用のしやすさに大きく影響する要素です。
スマホ・タブレット対応でいつでもアクセス可能
テレワークや外出の多い働き方が増える中で、PCに限定された人事評価システムは使い勝手が悪いと感じやすいです。
スマホやタブレットに対応していれば、移動中や隙間時間でも評価の入力・確認ができ、進捗の遅れを防げます。
モバイル端末でも見やすく操作しやすい画面設計になっているかどうかは、システム選定時に見落とせないポイントです。
場所や時間に縛られない運用が、現場の負担軽減とスムーズな定着につながります。
入力や確認に手間がかからない評価フロー
人事評価が定着しない原因の1つが、「入力や確認に手間がかかること」です。
画面を何度も切り替えたり、必要な情報が分かりにくい設計では、現場の負担が増えてしまいます。
その点、評価シートの記入から承認、フィードバックまでがワンフローで完結する設計であれば、作業効率は格段にアップします。
進捗が可視化されるダッシュボードや自動リマインド機能なども、スムーズな運用に欠かせない要素です。
クラウド型人事評価システムのメリット

ここでは、人事評価システムの中でも、クラウド型ならではのメリットを3つ解説します。
- 社内外どこでも使える柔軟な運用性
- サーバー管理不要でIT部門の負担が軽い
- 常に最新バージョンが使える安心感
それぞれ確認してみましょう。
関連記事:クラウド型(SaaS)人事評価システムの選び方とおすすめのサービス5選
社内外どこでも使える柔軟な運用性
クラウド型の人事評価システムは、インターネット環境さえあれば社内外を問わずアクセスできるのが大きなメリットです。
オフィス勤務に限らず、リモートワークや出張先でも評価の入力・確認・承認が行えます。
評価進捗の把握やフィードバックのやりとりもリアルタイムで行えるため、場所にとらわれずスムーズな運用が実現します。
サーバー管理不要でIT部門の負担が軽い
クラウド型の人事評価システムなら、自社でサーバーを構築・運用する必要がありません。
バックアップやセキュリティ更新、障害対応といった煩雑な作業はすべてベンダー側が担うため、IT部門の負担を大幅に軽減できます。
IT担当者が限られる中小企業では、こうした保守作業の省力化が大きなメリットとなります。
導入後の管理工数を最小限に抑えながら、安心して運用できるのがクラウド型の強みです。
常に最新バージョンが使える安心感
クラウド型の人事評価システムは、自動的に最新バージョンへアップデートされるため、常に最適な状態で利用できるのが特徴です。
法改正やセキュリティ要件への対応もタイムリーに行われ、ユーザー側の手間もかかりません。
新機能の追加や操作性の改善も随時反映されるため、使い勝手が進化し続ける点も大きな魅力です。
人事業務全体を支える!他システムとの連携・拡張性
ここでは、人事業務全体の効率化に不可欠な「システム連携」と「将来的な拡張性」のポイントを解説します。
- 人事・労務・勤怠など周辺業務とのシームレスな連携
- 将来的な拡張・制度変更に柔軟に対応できるか
それぞれ詳しく見ていきましょう。
人事・労務・勤怠など周辺業務とのシームレスな連携
人事評価システムは、評価業務だけでなく、勤怠・労務・給与といった周辺業務と連携してこそ、真の効果を発揮します。
たとえば、勤怠データと連動すれば、勤務状況を反映した、より現実的で納得感のある評価が可能です。
評価結果を昇給や賞与へ自動反映できれば、処理スピードが上がり、人的ミスの防止にもつながります。
手入力や転記作業が不要になるため、現場の負担も大きく軽減されるでしょう。
このように、ほかのシステムとシームレスに連携できる評価システムを選ぶことで、人事部門全体の業務効率が向上し、戦略的な人材マネジメントも実現しやすくなります。
将来的な拡張・制度変更に柔軟に対応できるか
人事評価制度は、企業の成長や組織の変化に応じてアップデートが求められます。
だからこそ、評価システムには「今の制度に合うこと」だけでなく、「将来の変更にも柔軟に対応できること」が欠かせません。
評価項目の追加やフローの見直し、階層構造の変更などにスムーズに対応できる設計であれば、制度変更時の負担を最小限に抑えられます。
ベンダー側のサポート体制も、選定時に確認しておきたいポイントです。
実際の導入企業の声から見る、使いやすいシステムの特徴
ここでは、実際の導入企業の声をもとに、「使いやすい」人事評価システムの特徴を紹介します。
- 誰でも迷わず使えるシンプルで直感的な操作性
- 評価進捗がリアルタイムで見える化できる
- 操作ステップが少なく、入力・承認がスムーズ
以下で詳しく説明します。
誰でも迷わず使えるシンプルで直感的な操作性
人事評価システムを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。
導入企業の多くが重視しているのは、シンプルな画面設計や直感的な操作性です。
評価の入力や確認がスムーズになれば、業務への心理的ハードルが下がり、制度の定着にもつながります。
こうした「迷いのない操作感」は、使いやすさを語るうえで欠かせない要素の1つです。
評価進捗がリアルタイムで見える化できる
人事評価において、評価の進捗状況を正確に把握することは、運用の効率化とトラブル防止に直結します。
誰がどこまで入力を完了しているのか、未提出者は誰なのかなどが一目で分かる「見える化」は、評価業務をスムーズに進めるうえで欠かせません。
使いやすい人事評価システムには、進捗をリアルタイムで確認できるダッシュボード機能が備わっているケースも多々あります。
これにより「提出漏れ」や「確認ミス」を防げます。
操作ステップが少なく、入力・承認がスムーズ
システムへの入力や承認の手間が多いと、現場の負担が大きくなります。
操作ステップが複雑であるほど、入力ミスや対応の遅れが発生しやすく、評価の質にも影響を及ぼすかもしれません。
操作手順がシンプルで、入力から承認までをスムーズに進められるシステムであれば、業務効率は大幅に向上します。
評価担当者はもちろん、管理職にとってもストレスが少なく、作業の抜け漏れを防げる点も大きなメリットです。
使いやすい人事評価システム3つ
ここでは、操作性・機能性・サポート体制のバランスに優れた使いやすい人事評価システムを3つご紹介します。
- ヒョーカクラウド
- 人事評価ナビゲーター
- カオナビ
それぞれ見ていきましょう。
ヒョーカクラウド

「ヒョーカクラウド」は、業界最安値級の月額1人100円から利用できる低コストのクラウド評価システムです。
MBOやコンピテンシー評価、360度評価、1on1管理、スキルマップ、レポート分析など、人事評価の中核となる機能を備えています。
さらに、職能を可視化するスキルマップ機能や、評価時の行動ログ、ポイント付与などを通じたモチベーション向上施策も備えており、現場の組織活性化にも役立ちます。
人事評価ナビゲーター

「人事評価ナビゲーター」は、月額5,500円から利用できる業界トップクラスの低価格評価システムです。
コンサルティング会社のノウハウを反映した設計が特徴です。
一次評価の一括コピー機能やフィードバック・行動観察のメモ保存、評価データの可視化と活用など、現場の求める機能が充実しています。
さらに、無料デモやナレッジサイト、充実した導入支援体制も整っており、制度構築や導入支援に不安のある組織でも安心してスタートできます。
カオナビ

「カオナビ」は、顔写真と人材データを1つに集約し、従業員のスキルや経歴、評価情報などを一元管理できるタレントマネジメント型の人事評価システムです。
MBOやOKR、360度評価といったテンプレートをドラッグ&ドロップで簡単に作成でき、柔軟なワークフロー設計によって自社独自の評価制度にもスムーズに対応できます。
評価業務の工数が従来の1/10以下に削減された事例もあり、高い効率性が魅力です。
ユーザー同士が情報を共有できるコミュニティも整備されており、運用の定着や制度改善を継続的に支援します。
自社に合った「使いやすい」人事評価システムを導入しよう
人事評価制度がどれほど優れていても、現場で使いにくいと感じるのであれば、運用は長続きしません。
スムーズに人事評価業務を進めるためには、現場の負担を減らし、誰でも直感的に操作できる使いやすさに優れたシステムを選ぶことが重要です。
「ヒョーカクラウド」は、シンプルな操作設計と豊富な機能、充実したサポートで、多くの企業から高い評価を得ています。
人事評価システム選びでお悩みの方は、ぜひご検討ください。
ヒョーカクラウドの成功事例について
評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?
ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。
Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。
評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。
-

- 建築・建設業
評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。
会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...
-

- 医療・福祉業
- 100〜299名
従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に
導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
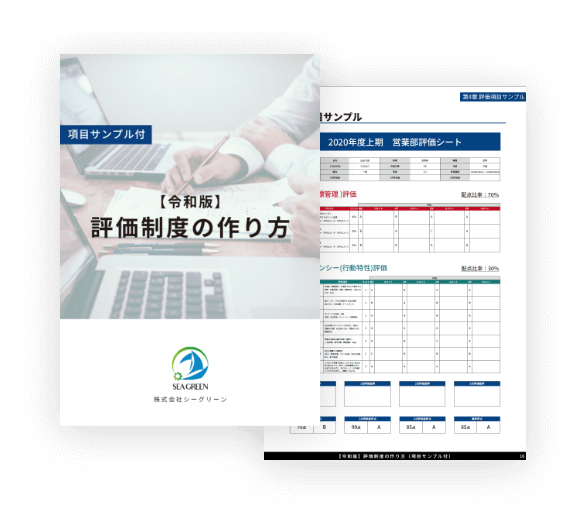
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル