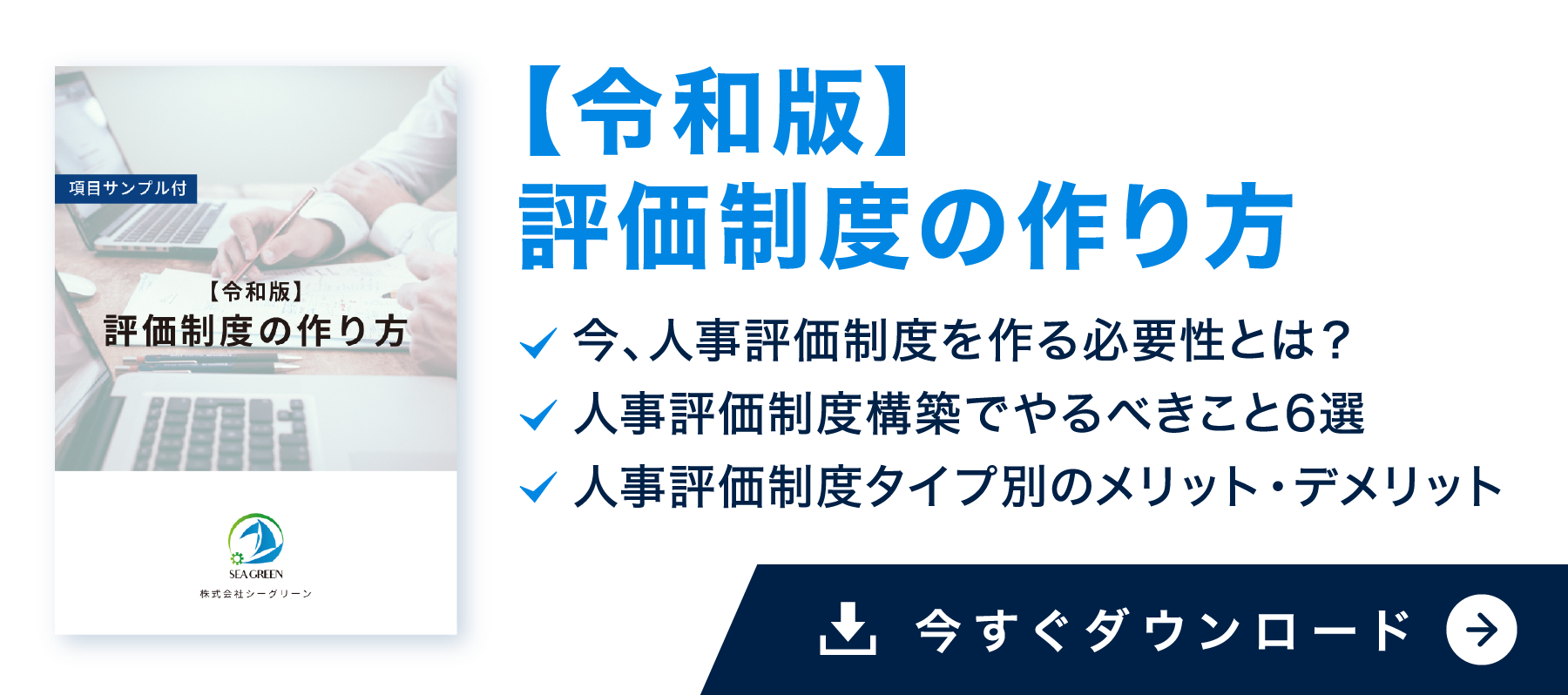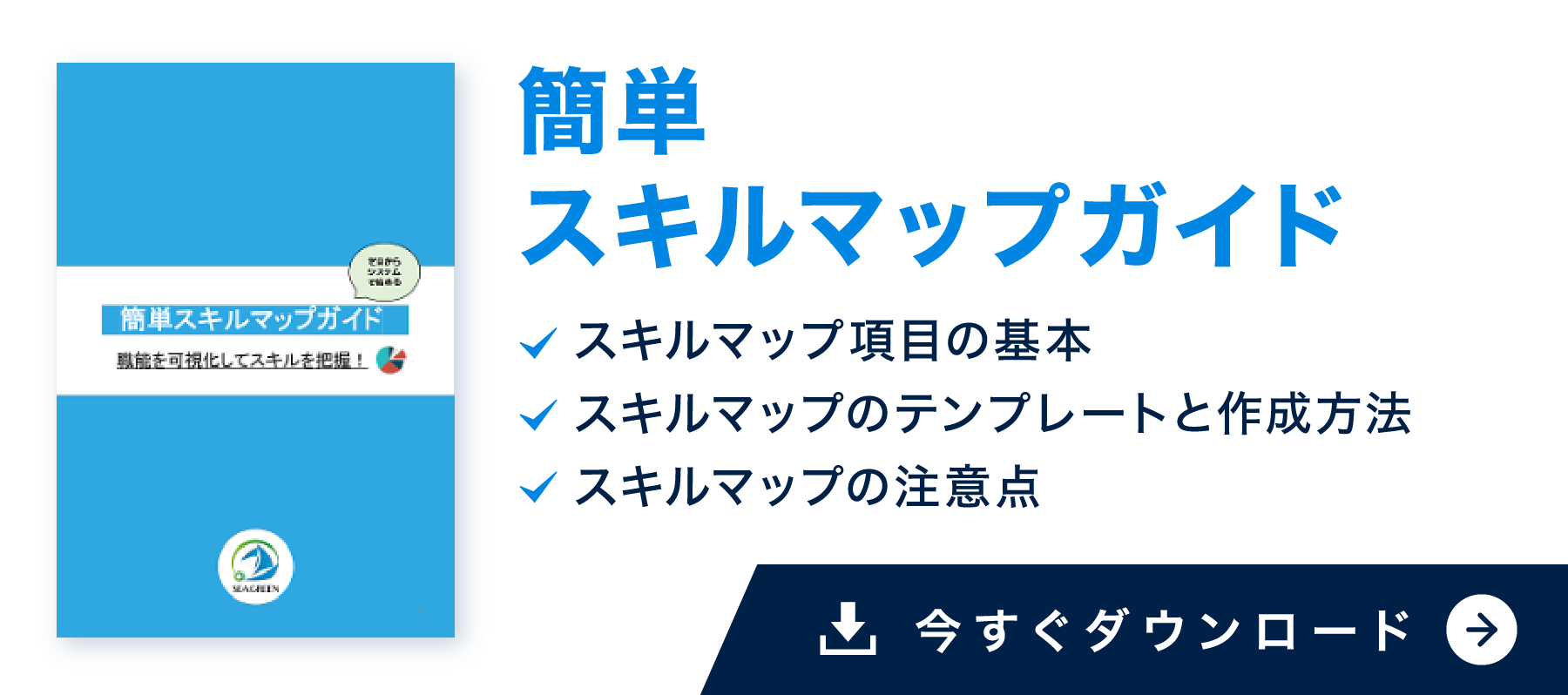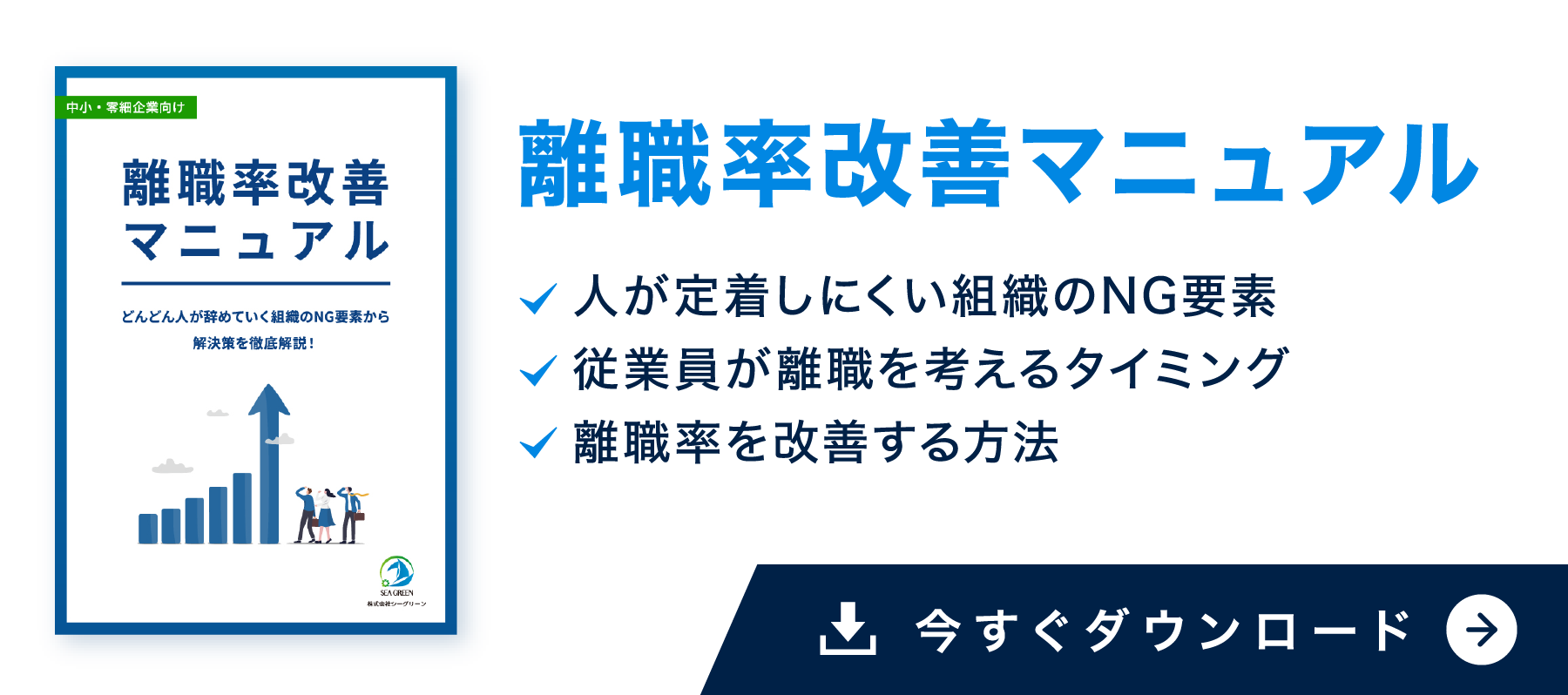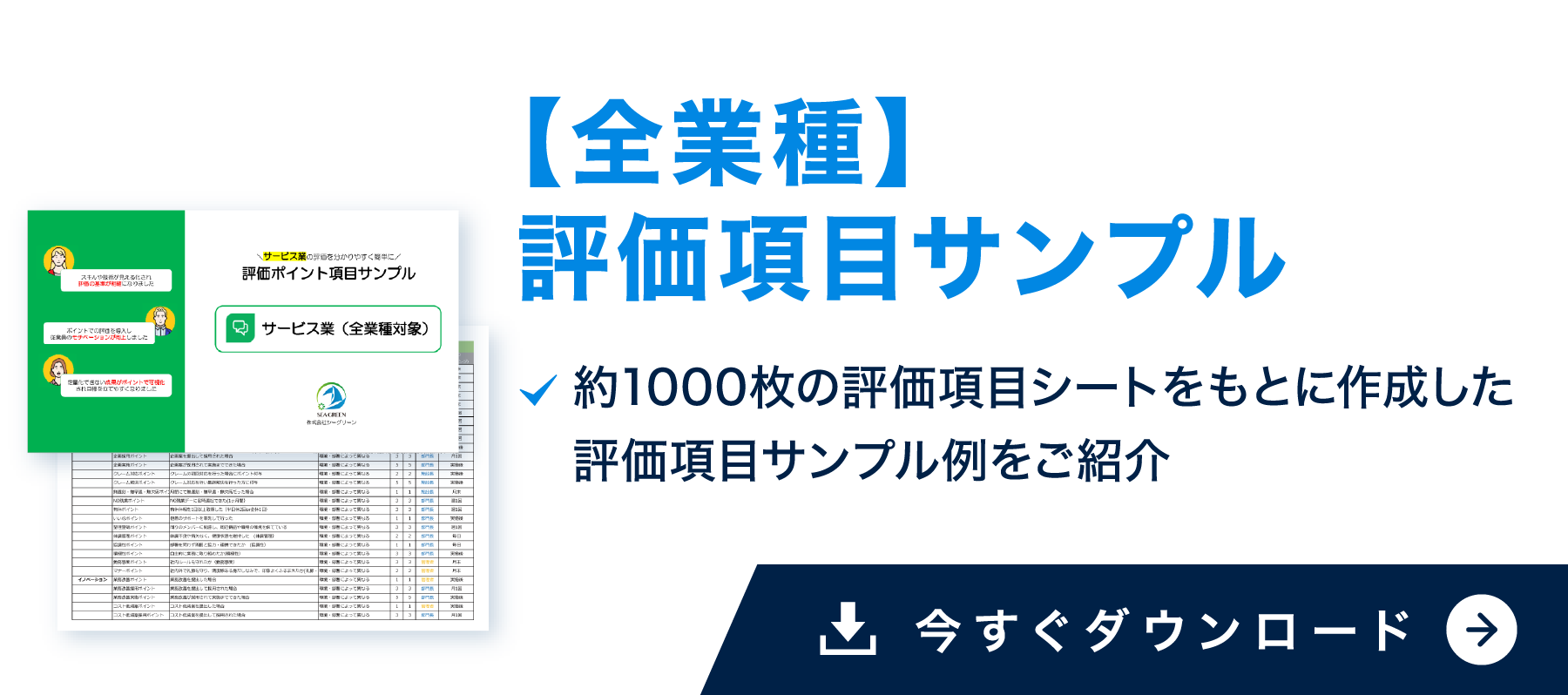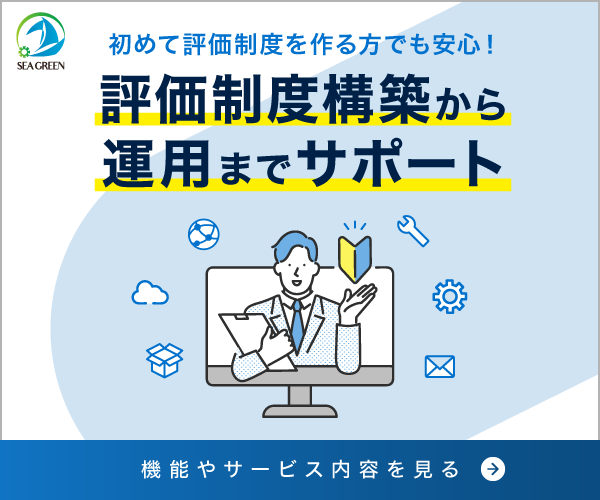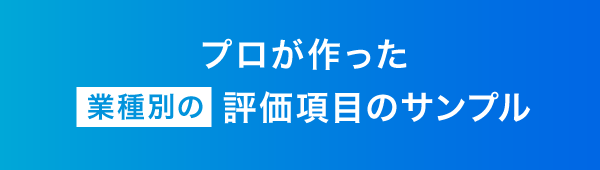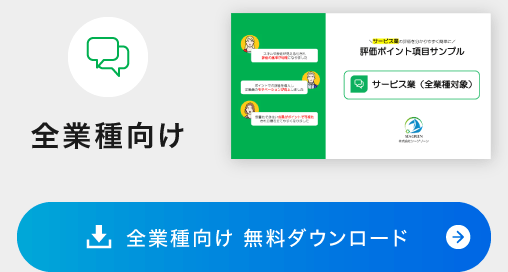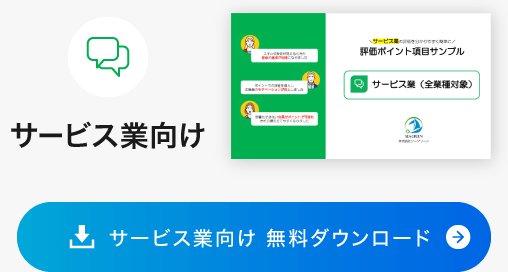人事評価制度に課題を抱える企業は少なくありません。
あいまいな基準や成果偏重の評価、トップダウンの運用は、社員のモチベーションや信頼感を損なう原因になります。
本記事では、具体的な人事評価システムの導入事例をもとに、納得感のある評価制度へと改善した企業の取り組みを紹介します。
さらに、2025年の最新トレンドも踏まえ、自社に合った制度改革のヒントをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 1 人事評価システムとは?導入の目的や企業のメリットを解説
- 2 【成功事例15選】人事評価システム導入で変革を遂げた企業の事例
- 2.1 事例1 イルニード歯科医院/ヒョーカクラウド・評価ポイント
- 2.2 事例2 コンビニエンスストア/評価ポイント
- 2.3 事例3 清水建設株式会社/カオナビ
- 2.4 事例4 ビックカメラ/カオナビ
- 2.5 事例5 東レ株式会社/HRBrain
- 2.6 事例6 はるやま商事株式会社/HRBrain
- 2.7 事例7 株式会社ライフアドバンス(恵比寿不動産)/あしたのクラウドHR
- 2.8 事例8 GMB株式会社/あしたのクラウドHR
- 2.9 事例9 株式会社もりもと塗装/人事評価ナビゲーター
- 2.10 事例10 アイアンドエス税理士法人/人事評価ナビゲーター
- 2.11 事例11 大光電機株式会社/One人事
- 2.12 事例12 株式会社中西製作所/One人事
- 2.13 事例13 福岡県直方市/ADWORLD 人事評価システム
- 2.14 事例14 ぼてぢゅうグループ/評価ポイント
- 2.15 事例15 株式会社ディライト/ヒョーカクラウド
- 3 事例から探る!「やる気をなくす」人事評価制度を脱却する方法とは
- 4 【2025年版】人事評価システム導入の最新トレンドとは
- 5 導入事例から学び、自社に最適な人事評価システムを活用しよう
人事評価システムとは?導入の目的や企業のメリットを解説

人事評価システムとは、従業員の目標設定や進捗管理、評価、フィードバックなどのプロセスをデジタルで一元管理できるツールです。
評価制度を正確かつ効率的に運用するために特化した仕組みといえます。
従来は、人事評価業務をExcelや紙で管理していたため、担当者の負担が大きく、評価のばらつきやフィードバックが個人に依存しやすいという課題がありました。
人事評価システムの導入によって、こうした非効率を解消できます。
人事評価システムの導入によって得られるおもなメリットは、以下のとおりです。
- 工数削減と業務効率化
- 評価に対する納得感の向上
- 人材データの一元管理
- リモートワークや多拠点でも一貫した運用体制の構築
業種や企業規模を問わず、現在はさまざまな現場で導入が進んでいます。
関連記事:人事評価システムとは?失敗しない導入のポイントを分かりやすく解説
【成功事例15選】人事評価システム導入で変革を遂げた企業の事例
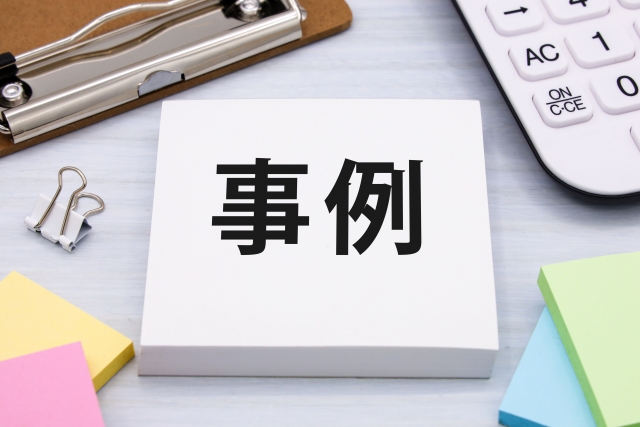
ここでは、人事評価システムを実際に導入した企業の事例を15件ピックアップして紹介します。
従業員数50名以下の中小企業から、1万人を超える大企業まで、さまざまな規模の事例をご紹介しています。自社の規模と比較しながらご覧ください。
- 事例1 イルニード歯科医院/ヒョーカクラウド・評価ポイント
- 事例2 コンビニエンスストア/評価ポイント
- 事例3 清水建設株式会社/カオナビ
- 事例4 ビックカメラ/カオナビ
- 事例5 東レ株式会社/HRBrain
- 事例6 はるやま商事株式会社/HRBrain
- 事例7 株式会社ライフアドバンス(恵比寿不動産)/あしたのクラウドHR
- 事例8 GMB株式会社/あしたのクラウドHR
- 事例9 株式会社もりもと塗装/人事評価ナビゲーター
- 事例10 アイアンドエス税理士法人/人事評価ナビゲーター
- 事例11 大光電機株式会社/One人事
- 事例12 株式会社中西製作所/One人事
- 事例13 福岡県直方市/ADWORLD 人事評価システム
- 事例14 ぼてぢゅうグループ/評価ポイント
- 事例15 株式会社ディライト/ヒョーカクラウド
それぞれ見ていきましょう。
事例1 イルニード歯科医院/ヒョーカクラウド・評価ポイント
イルニード歯科医院では、従業員約60名の評価業務をExcelで手作業で管理しており、進捗確認や集計作業に時間がかかるという課題がありました。
そこで、シンプルで直感的な操作性が特徴の「ヒョーカクラウド」と「評価ポイント」を導入。
「ありがとうポイント」の仕組みも活用し、従業員同士の貢献がリアルタイムで「見える化」されました。
評価作業の工数は大幅に軽減され、職場内のコミュニケーションも活性化しました。
現場での行動変容や、モチベーションの向上につながる好循環が生まれています。
事例2 コンビニエンスストア/評価ポイント
あるコンビニエンスストアでは、アルバイトのシフトどおりの出勤が守られず、離職も月に1〜2名発生していました。
接客は受け身で、業務連携も滞るなど、店長は教育負担や人手不足に頭を悩ませていました。
そこで導入されたのが、シーグリーンのクラウド型リアルタイム評価システム「評価ポイント」。
リアルタイムの「いいね」評価により、得意な業務への貢献が可視化されました。
導入後は離職者がゼロとなり、新たに3名の採用にも成功しました。
評価をもとに適材適所のシフト編成を行った結果、1日あたりの売上が平均で10万円増加。
従業員は「何をすれば評価されるか」が明確になり、やりがいや連帯感も高まっています。
事例3 清水建設株式会社/カオナビ
建設業大手の清水建設では、約1万人の従業員が在籍し、人事情報の統一的な把握が困難でした。
評価の偏りや情報のばらつきが多く、評価業務に膨大な時間と手間がかかっていたとのことです。
こうした課題を解決するため、同社はクラウド型の人材情報プラットフォーム「カオナビ」を選びました。
従業員のスキルや評価履歴を統合し、組織図や評価分布をひと目で把握できるように設計されています。
また、現場の操作性にも配慮し、ITリテラシーの差を考慮した導入が進められました。
運用を開始して以降、面談や人材配置の場面で必要な情報に即アクセスできるようになり、制度運用の精度とスピードが大きく向上。
人事評価が「ただの作業」から「育成の起点」へと変わりました。
事例4 ビックカメラ/カオナビ
ビックカメラは、全国規模の複数店舗を抱える大手家電量販チェーンとして、膨大な人材情報が各拠点に散在しており、統合管理が困難でした。
このため、人材検索や配置、人事異動などに時間がかかり、現場での意思決定が滞る点が課題でした。
同社は複数のツールを比較し、使いやすさや現場での評価の納得感を重視して「カオナビ」を導入。
実際に現場で試したところ、直感的なUIとアクセスの速さが好評で、導入の決め手となりました。
正式導入後、人材情報へのアクセス性が飛躍的に改善。
現場の判断スピードが大幅に向上し、評価面談や異動の決定にも迅速に対応できるようになりました。
事例5 東レ株式会社/HRBrain
東レにおける従来の従業員サーベイは、結果の分析が複雑で、現場に落とし込みにくく活用が進みませんでした。
さらに、サーベイの実施は2年に1回で、結果のフィードバックも半年後でした。
従業員の状況変化に即座に対応できず、エンゲージメントや定着率の改善につながっていませんでした。
課題解決に向けて同社が導入を決めたのが、「HRBrain」でした。
2年に1回だったサーベイの頻度を年1回に増やし、直感的なUIにより即時のフィードバックが可能になったとのことです。
導入後は組織改善のスピードが向上し、従業員の「いきいき度」が高まったと現場リーダーから評価されています。
事例6 はるやま商事株式会社/HRBrain
はるやま商事株式会社では、離職率の上昇が人事課題として顕れていました。
既存のエンゲージメントサーベイは、カスタマイズ不可で結果も見づらく、改善へつながりにくいものでした。
そこで採用されたのが、HRBrainが提供する組織診断サーベイ「EX Intelligence」です。
導入により、従来は難しかった設問のカスタマイズが可能になりました。
利用開始直後から、現場ライン長がサーベイ結果を即時に閲覧し、ギャップ分析に基づくアクションを主体的に立案・実行。
経営層のサーベイに対する関心も高まり、「会社が従業員を大切にしている」という前向きな声が社内に広がっています。
事例7 株式会社ライフアドバンス(恵比寿不動産)/あしたのクラウドHR
従業員数が40名を超えたタイミングで、個々の成果主義的な評価では組織としてのまとまりが失われつつあった株式会社ライフアドバンス。
実際、昇給・昇進の基準は売上のみに偏り、評価軸があいまいになっていました。
人事評価制度を再構築する際に導入したのが「あしたのクラウドHR」です。
導入時には、無記名アンケートで従業員の価値観を収集し、経営層も巻き込んで評価制度を共に設計しました。
運用開始後は、理念を確認する全社集会が企画されるなど、制度が「管理の手段」から「文化の核」へと変わりました。
従業員の帰属意識や参画意識が高まり、職場の風通しも改善されたとのことです。
事例8 GMB株式会社/あしたのクラウドHR
GMB株式会社では、従業員の挑戦意欲を引き出す評価視点が不足しており、組織全体のエンゲージメント低下が懸念されていました。
そこで導入されたのが「あしたのクラウドHR」です。
このシステムは、単なる評価システムではなく、「挑戦」を評価軸として明確に設定できる機能が搭載されています。
また、理念・ビジョンを浸透させる制度設計をワンパッケージで支援できる点が、導入の決め手となりました。
導入後は、「ただ守るだけ」だった評価から、「挑戦した人に光が当たる」文化に変化し、全社のエンゲージメントが徐々に向上。
従業員の言動から理念への共感や目標への情熱が感じられるようになったと、満足の声があがっています。
事例9 株式会社もりもと塗装/人事評価ナビゲーター
従業員約50名の建設系企業であるもりもと塗装では、評価基準や給与基準が明示されておらず、若手従業員の不安や迷いが業務の妨げとなっていました。
そこで、中小規模の企業に合ったシンプルなUIと手頃な価格が魅力な「人事評価ナビゲーター」を導入することに。
事前に用意された建設業向けの評価パッケージから選択・調整できたため、わずか1週間ほどで評価項目を決定することができました。
さらに導入後は、日常行動にもポジティブな変化が見られています。
整理整頓担当従業員が「気にかけていた場所」に先回りして動き、ほかのメンバーにもよい影響が広がるようになりました。
事例10 アイアンドエス税理士法人/人事評価ナビゲーター
アイアンドエス税理士法人は、評価運用をすべてExcelで管理していました。
しかし、準備・転記・集計には約5時間かかり、評価の一貫性が保てないという課題が。
そこで同法人が採用したのが「人事評価ナビゲーター」でした。
小規模組織に最適な「ちょうどよいスペック」で、Excelの延長上で使える親和性と、「メモ機能」「過去データ蓄積」による評価の一貫性向上が決め手となりました。
導入後は、評価準備から転記・集計までの業務がスムーズに進み、業務時間も短縮。
さらに、メモ機能により「評価期間全体を踏まえた判断」ができるようになり、誰もが納得できる評価が定着し始めています。
関連記事:小規模企業向け人事評価システム10選|導入のメリットと製品の選び方
事例11 大光電機株式会社/One人事
全国に拠点を持つ大光電機株式会社では、従来の評価システムの動作に時間がかかり、過去の評価や研修履歴(人材情報)が散在していました。
そこで同社が導入したのは、高速レスポンスと人材情報の統合が特長の「One人事」です。
過去の評価データや研修履歴まで1つの画面から参照可能で、操作の快適さを追究した設計が選定の理由となりました。
導入後は、情報の読み込みや画面遷移にかかる待ち時間が解消され、評価プロセスが格段にスムーズになったとのことです。
処理速度の高さは担当者のストレスを軽減し、評価や育成設計に取り組む時間が大幅に増えました。
事例12 株式会社中西製作所/One人事
創業80年を迎える中西製作所(従業員約680名)は、全国の事業所から評価シートを収集し、紙・Excel管理をしていました。
結果がそろうまでに最長5ヶ月かかったこともあり、賃金や配置人事の適時判断が困難な状態に陥っていました。
そこで、業務効率化と継続的な利用が期待できる「One人事(タレントマネジメント)」を採用。
「画面がシンプルで直感的」「人事評価機能だけを切り出して導入可能」「専任サポート体制が充実」といった特徴があります。
導入後は、導入費用が約40%削減され、評価入力にかかる工数も半減する見込みです。
従業員一人ひとりの評価プロセスが効率化され、制度の改善や人事DXに取り組む時間も確保できるようになりました。
事例13 福岡県直方市/ADWORLD 人事評価システム
福岡県直方市では、約600名の職員をわずか7人の人事担当で評価していました。
パスワード付きファイルの管理や紙とExcelによる運用では、分析はもちろん、進捗確認すら難しい状況でした。
この課題に対して直方市が講じた対策が、自治体運用に精通した「ADWORLD 人事評価システム」の導入です。
自治体にありがちな仕様に対応し、信頼性と安定性も担保されていた点が評価されています。
運用開始後は、人事担当者の事務作業が大幅に削減されました。
評価データのデジタル化によって、分析や人材アセスメントに充てる時間が確保でき、「トータル人事制度」の中核としての運用が加速しています。
事例14 ぼてぢゅうグループ/評価ポイント
ぼてぢゅうグループは、「業績」だけで評価してしまうと接客や調理の貢献を正しく評価できず、不公平感が生まれていました。
半期ごとの数値評価では、スタッフそれぞれの努力や個性が埋もれてしまっていたのです。
この状況を打開するため、「評価ポイント」の仕組みを導入しました。
評価の視点を「業績」「能力」「行動」の三つに再定義し、従業員同士がスマホからリアルタイムで評価し合える仕組みを取り入れています。
評価は365日積み上げ式へと変化し、MVP従業員は半年間で60万ポイント以上を獲得するほど活発に活用。
個々の強みが「見える化」され、日々の行動が正当に評価される環境へと進化しました。
事例15 株式会社ディライト/ヒョーカクラウド
株式会社ディライトでは、人事評価を紙やExcelで管理しており、査定業務に最大で1~2週間もかかっていました。
そこで導入されたのが、人事評価のクラウド化を支援する「ヒョーカクラウド」です。
同社ではシステム選定時に、360度評価の実装・結果を1on1面談で活用する設計・レーダーチャートによる評価推移の「見える化」機能が決め手となりました。
導入後は、最大で1〜2週間かかっていた査定業務が大幅に短縮されました。
評価の推移を確認することで、自分自身の成長や課題をすぐに把握できるようになったのが大きなポイントです。
評価プロセスが、単なる業務ではなく「育成の起点」として機能し始めています。
事例から探る!「やる気をなくす」人事評価制度を脱却する方法とは

ここでは、実際に評価制度の課題を乗り越えた企業の事例から、「やる気をなくす」人事評価制度を脱却した方法をまとめています。
- 「あいまいな評価」から「明確かつ可視化された納得感のある評価」へ
- 「完全な成果主義」から「プロセスを評価する仕組み」へ
- 「トップダウンの運用」から「従業員参加型の運用」へ
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
「あいまいな評価」から「明確かつ可視化された納得感のある評価」へ
「評価の基準が分からない」「なぜこの評価なのか納得できない」などの不満は、評価制度があいまいでブラックボックス化していることに起因します。
とくに紙やExcelによる属人的な運用では、評価プロセスが見えづらく、上司の主観に依存しやすくなります。
こうした課題に対しては、評価の基準・進捗・結果を「見える化」する仕組みが不可欠です。
事例で紹介した清水建設、もりもと塗装、中西製作所の3社では、人事評価システムを活用して評価内容の「見える化」を図りました。
これにより、従業員の納得度を高める運用へとシフトしています。
「完全な成果主義」から「プロセスを評価する仕組み」へ
売上や目標達成率といった「成果」のみを評価対象とする運用は、短期的な数字を追うプレッシャーを生み、従業員の疲弊や不公平感を招くおそれがあります。
成果主義の社内では、チームでの協働や地道な努力、成長過程などが見過ごされやすく、組織の本質的な力を引き出せない要因にもつながりかねません。
こうした課題に向き合い、評価に「プロセス」の視点を加える企業が増えています。
GMB、ライフアドバンス、ビックカメラの3社では、日々の行動や努力の積み重ねを可視化・定量化し、成長に目を向ける制度設計に転換しました。
数字だけでは見えなかった価値を評価に取り入れることで、個々の努力が正当に認められる組織文化が生まれています。
「トップダウンの運用」から「従業員参加型の運用」へ
人事評価を人事部や経営層だけで設計・運用するトップダウン型の体制では、「評価される側」の納得感が得られにくくなります。
制度が形骸化したり、従業員の意欲を下げる原因になることもあるでしょう。
このような状況を脱却するためには、従業員が主体的に評価に関わる「参加型」の仕組みが重要です。
イルニード歯科医院、ぼてぢゅうグループ、ディライトの3社は、制度設計や運用プロセスに現場が関わる仕組みを整えたことで、評価の透明性や納得感、そしてモチベーションの向上につなげています。
従業員を巻き込むことで、制度は「やらされるもの」から「自分ごと」へと変わります。
【2025年版】人事評価システム導入の最新トレンドとは

ここでは、人事評価システムの最新トレンドについて、2025年版の最新情報をお届けします。
- トレンド1 MBO・OKR・360度評価など、評価手法の選択肢が拡大
- トレンド2 リアルタイムフィードバックとピアボーナスで即時評価
- トレンド3 ノーレイティング評価が大手企業で浸透
- トレンド4 クラウド型SaaSで中小企業の導入も急増
- トレンド5 評価とタレントマネジメントの統合
- トレンド6 AI・データ活用による評価の自動化・精度向上
- トレンド7 人的資本経営の文脈で「見える化」「説明責任」を重視
- トレンド8 多拠点・リモート環境でも運用しやすい設計
- トレンド9 従業員満足度を高める「納得できる評価制度」が主流に
1つずつ、詳しく確認してみましょう。
トレンド1 MBO・OKR・360度評価など、評価手法の選択肢が拡大
人事評価の手法は、MBOやOKR、360度評価、バリュー評価など、多様化が進んでいます。これらの手法を職種や等級に応じて使い分ける「複線型」の運用が広がっているのです。
目標とプロセス、行動や価値観の評価を組み合わせることで、より個々の特性に合った納得度の高い制度設計が実現できます。
トレンド2 リアルタイムフィードバックとピアボーナスで即時評価
年に一度の評価だけでは、日々の努力や成果を正確に把握するのが難しいという声が増えています。
そこで注目されているのが、上司からのリアルタイムフィードバックや、同僚同士が感謝や評価を送り合うピアボーナスの仕組みです。
日常の行動をすぐに評価できることで、モチベーションやチームの一体感を高める効果が期待されています。
トレンド3 ノーレイティング評価が大手企業で浸透
従来のように数値でランク付けする評価手法では、納得感のあるフィードバックが得られず、従業員のモチベーション低下を招くケースも見られました。
こうした背景から注目されているのが、あえてスコアをつけない「ノーレイティング評価」です。
対話を重視した運用で、従業員一人ひとりの成長支援や関係性の強化につながる新しい評価文化として、大手企業を中心に浸透が進んでいます。
トレンド4 クラウド型SaaSで中小企業の導入も急増
かつて人事評価システムは、「大企業向けの高価で複雑なもの」というイメージがありました。しかし近年は、クラウド型SaaSの登場により、初期費用を抑えつつ、使いやすく柔軟なシステムが中小企業にも広がっています。
人事に専門部門を持たない企業でも、直感的なUIやサポート体制により、スムーズな導入と運用が実現できます。
関連記事:クラウド型(SaaS)人事評価システムの選び方とおすすめのサービス5選
トレンド5 評価とタレントマネジメントの統合
近年では、人事評価の結果を単なる査定で終わらせず、人材育成や配置戦略に活用する「タレントマネジメント」との統合が進んでいます。
スキルや適性、キャリア志向などの情報を人事評価と連動させることで、個々の従業員に合わせた成長支援が可能に。
また、それらの情報をもとに最適な人員配置を行うことで、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。
トレンド6 AI・データ活用による評価の自動化・精度向上
AIやデータ解析の活用によって、人事評価の効率化や高度化が進んでいます。
過去の評価履歴や日々の業務データを活用することで、評価のばらつきを抑え、より公平で客観的な人事評価を目指します。
属人化のリスクを減らし、従業員が納得できる評価を支える仕組みとして、今後さらに注目される分野です。
関連記事:【AI活用の新時代】1on1が使える評価システムの完全版とは?
トレンド7 人的資本経営の文脈で「見える化」「説明責任」を重視
人的資本の情報開示が求められる中で、人事評価にも「見える化」と「説明責任」が強く意識されるようになってきました。
どのような基準で評価し、どう人材育成につなげているのかを社内外に説明できる仕組みが重視されています。
評価プロセスを可視化し、客観的に説明できる体制作りが、企業価値の向上にもつながります。
トレンド8 多拠点・リモート環境でも運用しやすい設計
テレワークやサテライトオフィスの普及により、人事評価も場所に縛られない運用が求められています。
クラウド型の評価システムなら、どこからでもアクセスできるため、拠点や勤務形態に関係なく一貫した評価が可能です。
さらに、リアルタイムでのフィードバックを取り入れることで、遠隔地のメンバーともスムーズにコミュニケーションを図れます。
こうした設計が、働き方の柔軟性と組織全体の評価品質を両立させるカギです。
トレンド9 従業員満足度を高める「納得できる評価制度」が主流に
近年では、評価の「納得感」が従業員満足度に直結する要素として重視されています。
不透明な基準や一方的な評価は、モチベーションの低下や離職リスクを招きかねません。
こうした背景から、評価基準の明確化やフィードバックの充実に取り組む企業が増加しています。
透明性と公平性のある仕組み作りが、従業員との信頼関係を築く土台となるでしょう。
導入事例から学び、自社に最適な人事評価システムを活用しよう
人事評価制度は、運用の仕方ひとつで組織の活力を大きく左右します。
導入事例からも分かるように、目的に合ったシステムを選ぶことが大切です。
適切に導入することで、課題の解決だけでなく、従業員の納得感やエンゲージメントの向上にもつながります。
操作性や柔軟な設計が魅力の「ヒョーカクラウド」は、初めてシステムを導入する企業にも最適です。
自社に合った運用を目指す方は、ぜひリンクから詳細をご確認ください。
ヒョーカクラウドの成功事例について
評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?
ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。
Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。
評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。
-

- 建築・建設業
評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。
会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...
-

- 医療・福祉業
- 100〜299名
従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に
導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
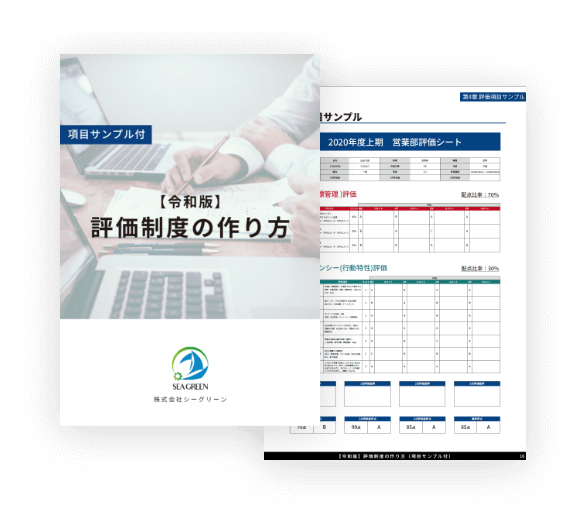
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル