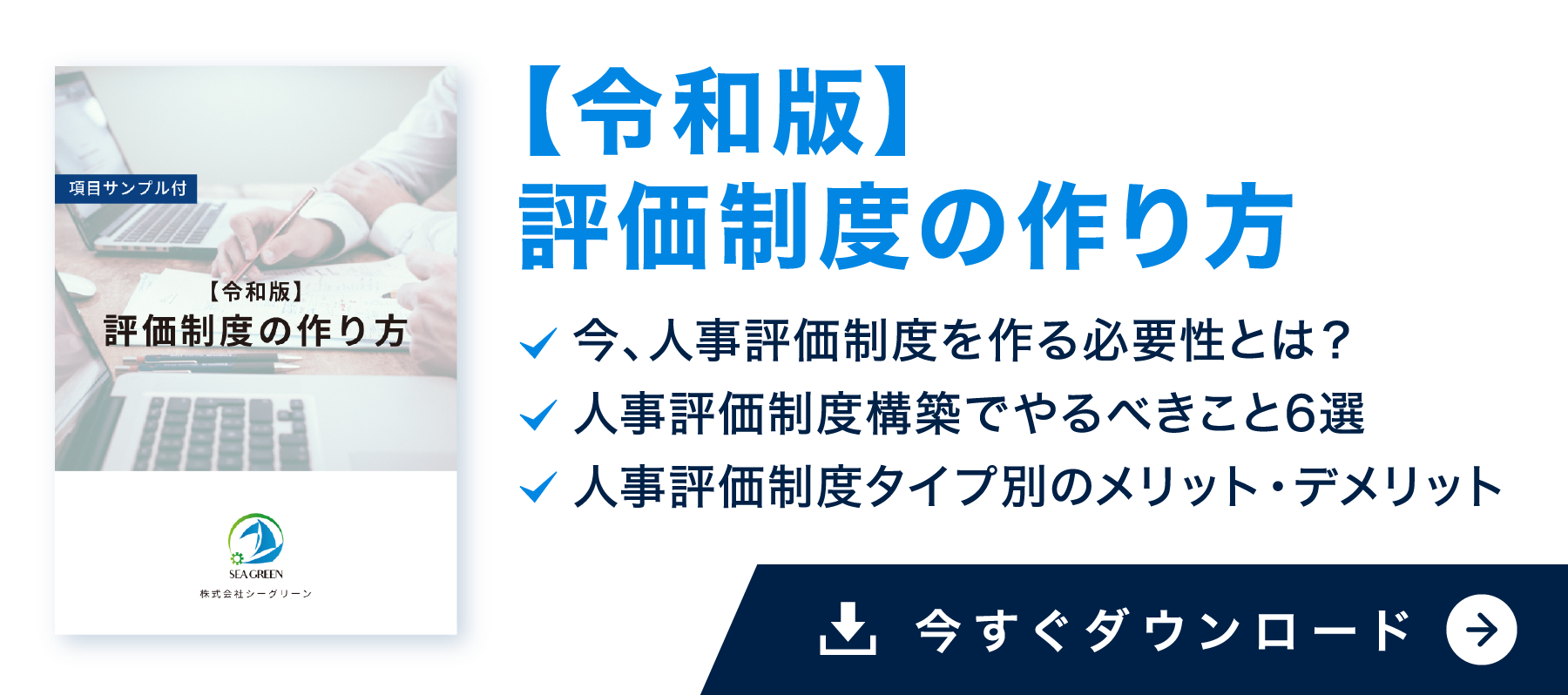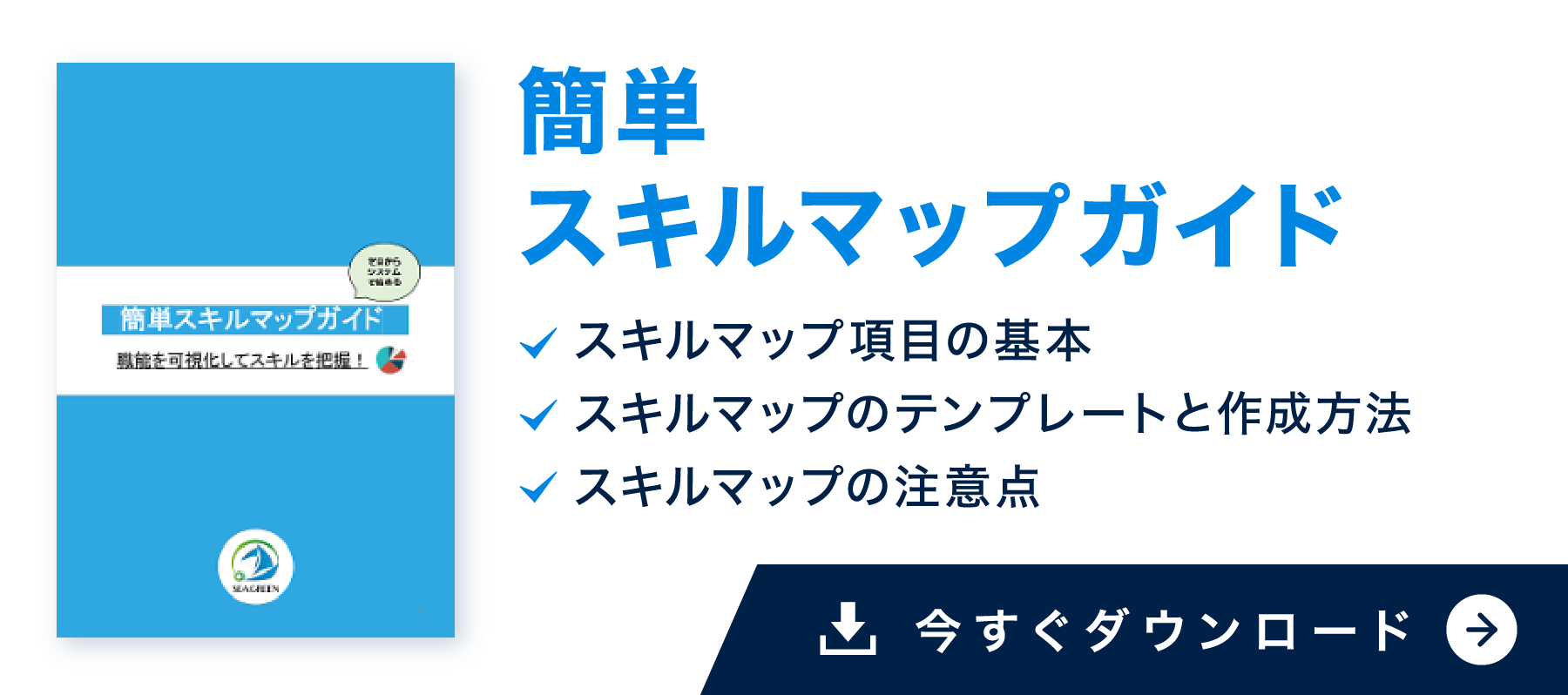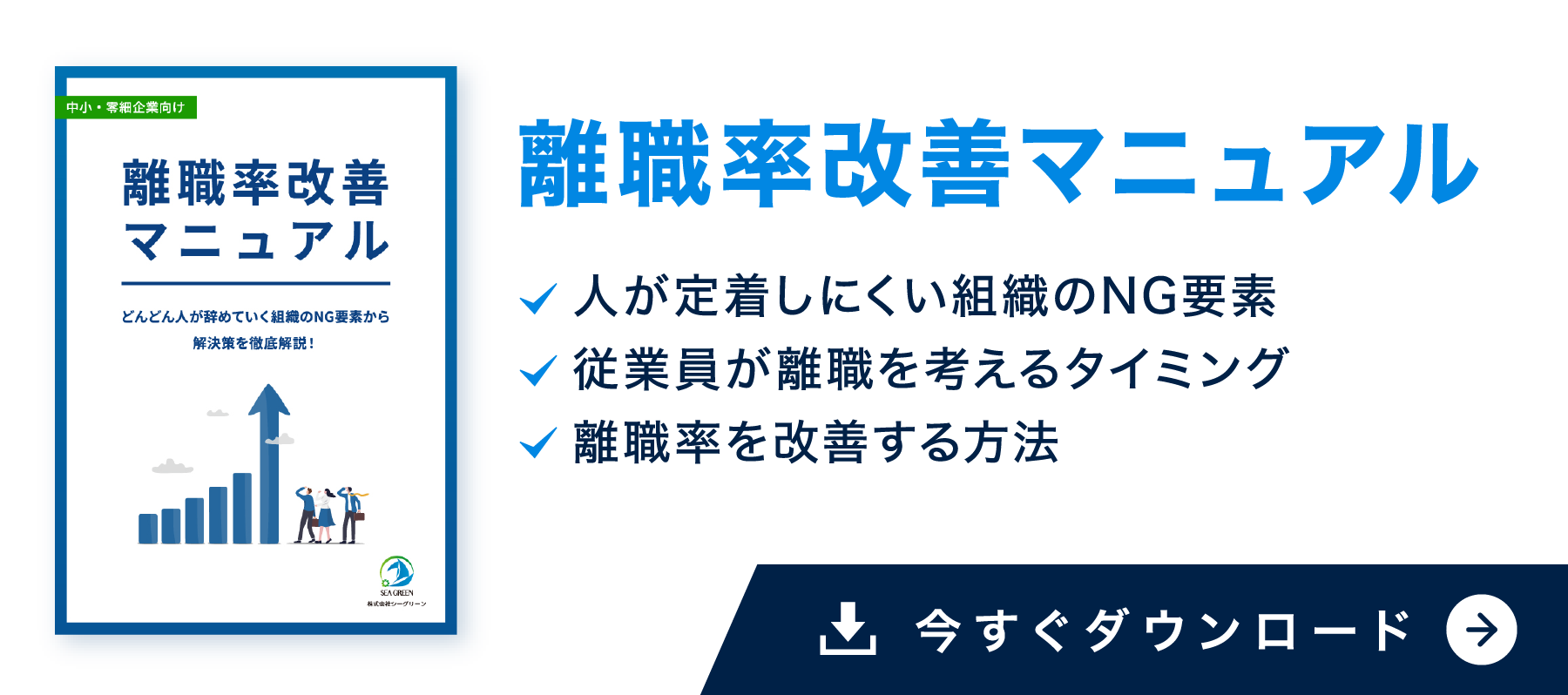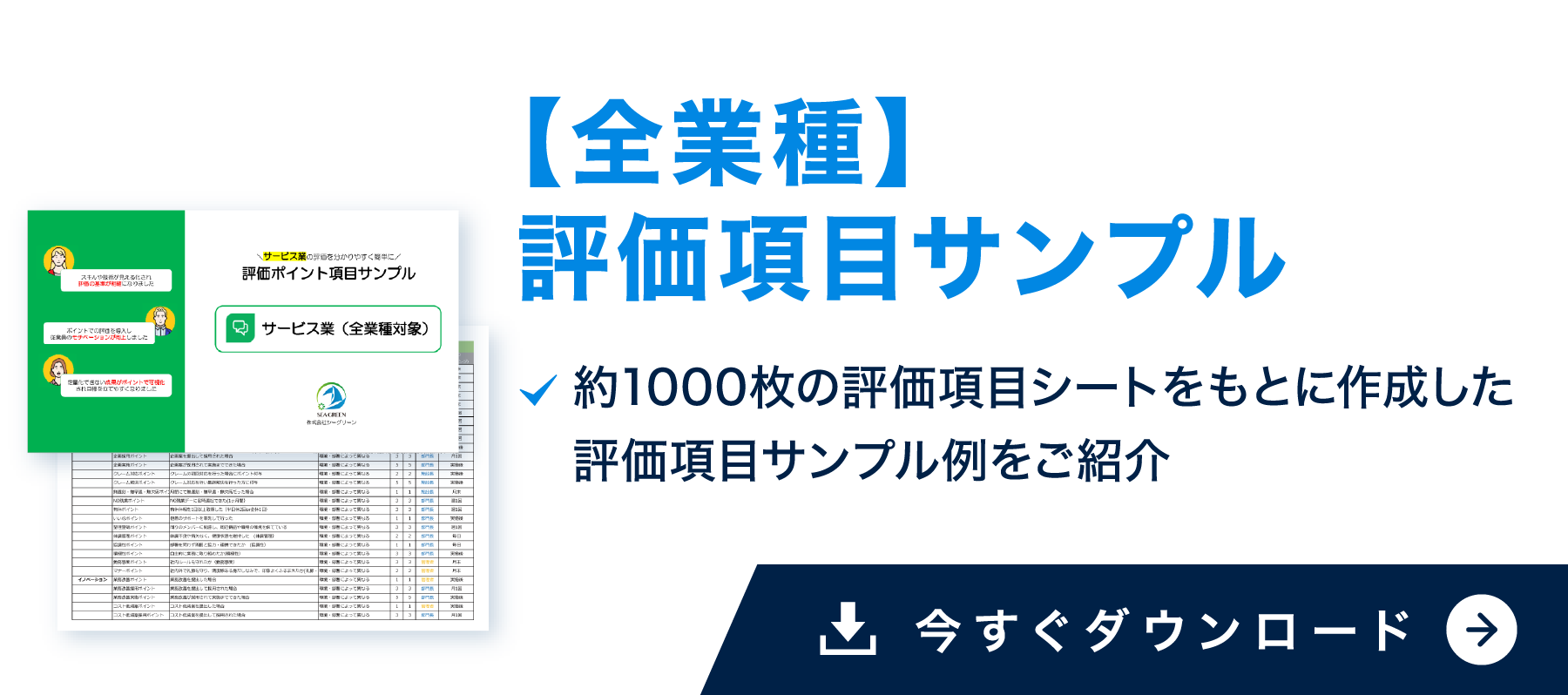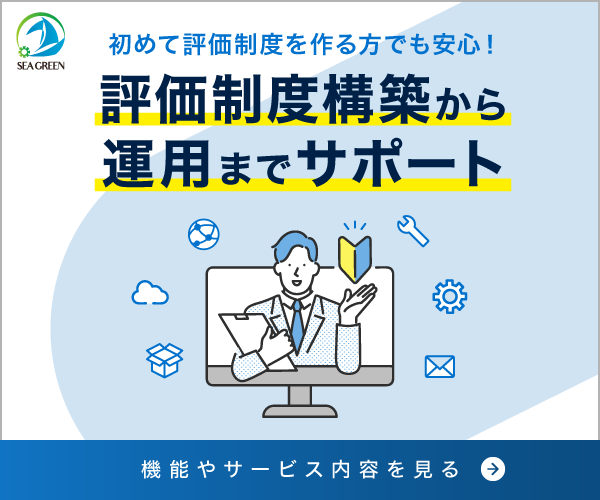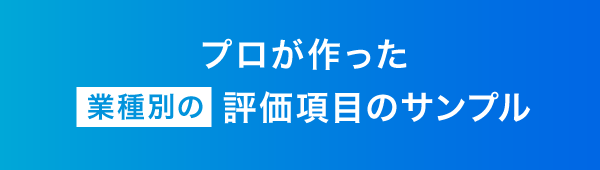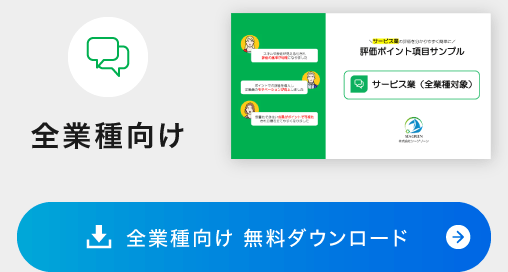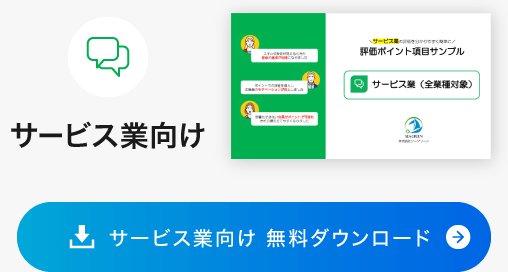人事評価は、従業員の意欲や成長スピード、組織全体の方向性にも影響を与える仕組みです。
しかし、評価の方法は多岐にわたるため、最適な制度選びに課題を感じる方もいるかもしれません。
本記事では、6つの人事評価制度をそれぞれの特徴ごとに整理し、比較しました。
制度の組み合わせ方や導入プランを考える際に役立ててください。
目次
人事評価制度の種類はどう分かれる?全体像を把握しよう

人事評価制度は、「何を評価するか」と「どのように評価するか」という2つの観点で整理できます。
おもな6つの人事評価制度を、評価する対象と評価方法の2軸で以下の表にまとめました。
| 制度 | 評価する対象 | 評価方法 |
| 能力評価 | 知識/技能/業務遂行力 | スキルマップ/等級要件/評価尺度(例:1–5)/上司評価中心 |
| 情意評価 | 姿勢/意欲/協調性/規律 | 行動観察チェックリスト/記述式コメント/複数評価者 |
| 成果評価 | 業績/KPI・KGI/目標達成度/品質 | 数値集計/OKR・MBO達成率/期初・期末面談 |
| コンピテンシー評価 | 成果につながる行動特性/行動基準 | コンピテンシーモデル/行動例(BARS)/行動評定 |
| バリュー評価 | 価値観の体現度/判断基準の一致 | バリュー項目に紐づく行動基準/事例評価/ピア評価 |
| 360度評価 | 他者から見た行動・協働・影響力 | 上司・同僚・部下・関係部門の多面アンケート/自己評価とのギャップ分析 |
このように整理することで、自社の目的に合わせて選択肢を絞り込むことが可能です。
たとえば数値を評価基準にしたい場合は成果評価、価値観や文化の浸透を重視したい場合はバリュー評価のような形で取捨選択できます。
次章からは、この6制度を1つずつ取り上げ、詳しく解説します。
能力評価:スキルや知識に焦点を当てたスタンダードな手法
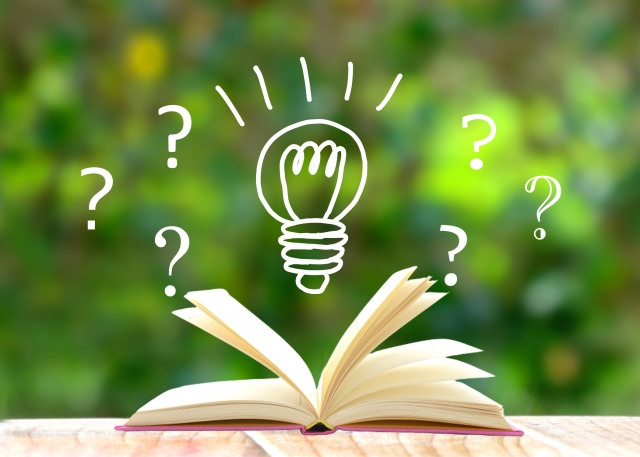
ここでは、能力評価について以下3点を解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
それぞれ見ていきましょう。
能力評価は「業務遂行力」を可視化する制度
能力評価は、従業員が仕事を遂行するうえで必要な知識や技能、そして成果を生み出すための行動を測る制度です。
たとえば営業職なら商品知識や提案スキル、顧客対応の姿勢などが必要になるでしょう。
製造職なら作業手順の習熟度、安全管理の徹底といった具合に、職種ごとに必要な能力が異なります。
基準を明確にすることで評価者間の判断が統一され、従業員も「どの能力を伸ばせば評価されるのか」が分かりやすくなります。
業績の数字だけでは把握しにくい「社員の基礎的な力」を評価できる点が、能力評価の大きな特徴です。
メリットとデメリット
能力評価のメリットは、以下のとおりです。
- 育成に直結しやすい
- 配置・等級の根拠が明確
能力評価では、従業員がどのようなスキルを持ち、何が不足しているかを把握できます。
この評価結果をもとに、研修やOJTで強化すべき点を明確にしたり、将来の役割に応じた育成計画を立てることも可能です。
また、デメリットは以下のとおりです。
- 評価者の主観が入りやすい
- 成果と評価がズレる場合がある
- 初期設計の負担が大きい
能力評価では、評価者によって解釈が異なるため、能力の高さと実際の成果が一致しない場合もあります。
また、職種ごとに評価基準や行動例を作成する必要があり、導入初期には多くの時間と労力がかかることもデメリットです。
能力評価はどのような職場にマッチする?
能力評価は、専門性や手順の遵守が成果の前提となる職場や、短期間の数値では成果を測りにくい職場に適しています。
たとえば、以下のような職場です。
- 製造
- 医療・介護
- コーポレート部門
- 研究開発
- バックオフィス業務
能力評価は、等級制度やスキルマップを活用している企業に適しています。
評価結果をもとに「誰をどこに配置するか」「誰を昇格させるか」「どの研修を受けさせるか」といった判断に直結しやすい評価制度です。
情意評価:仕事への姿勢や協調性を測る方法
ここでは、情意評価について以下3点を解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
詳しく見ていきましょう。
情意評価は「働く姿勢・意欲」を評価する制度
情意評価は、従業員の仕事への意欲や責任感、協調性といった「働く姿勢」を評価する制度です。
たとえば接客業であれば、顧客への対応、チームとの連携などが評価項目にあげられます。
こうした態度面の基準を明文化することで、成果やスキルだけでは見えにくい貢献度を可視化できます。
日常業務における小さな努力や周囲との協力関係も評価対象となるため、組織文化の醸成やエンゲージメントの向上につながる点が特徴です。
メリットとデメリット
情意評価のメリットは、以下のとおりです。
- 結果だけでは分からない、努力や協調性を評価できる
- 望ましい行動様式を組織に浸透させやすい
情意評価では、数字や成果だけでは評価しきれない日々の行動や姿勢を正当に評価できます。
そのため、チームワークや規律を重んじる文化を定着させやすく、従業員の意識や行動を組織の方向性に合わせやすいのが大きなメリットです。
また、デメリットは以下のとおりです。
- 評価者の主観が入りやすい
- 成果や能力との評価がズレる場合がある
成果や能力と評価が一致しない場合、評価対象者の不満につながることがあります。
これらの課題を解消するには、評価基準を具体的な行動例まで明確にし、ほかの評価制度と組み合わせて運用することが効果的です。
情意評価はどのような職場にマッチする?
情意評価は、協調性や姿勢が成果の前提となる職場や、顧客対応・安全管理など態度面が成果に直結する職場に適しています。
たとえば、以下のような職場です。
- サービス業・接客業
- 医療・介護
- 教育機関
- 製造・保全(安全遵守が必須)
- コーポレート部門やバックオフィス
望ましい行動を組織全体に浸透させたい職場や、文化作りを重視する企業にとくに適しているのが情意評価です。
成果評価:数値や実績を重視する目標達成型の評価
ここでは、成果評価について以下3点を解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
それぞれ見ていきましょう。
成果評価は「結果」をもとに評価する制度
成果評価は、期初に設定した目標(KPI・OKR・MBOなど)に対する達成度を評価軸とする制度です。
売上、受注件数、納期遵守率、コスト削減額、顧客満足度といった定量指標を使い、個人またはチームの成果を数値で表します。
運用では、期初の目標設定と重み付け、期中のモニタリング、期末の実績評価というサイクルを回します。
公平性や納得感を保つためには、外部要因や担当範囲の違いをどのように評価に反映させるか(帰属のルール)を事前に決めておくことが大切です。
メリットとデメリット
成果評価のメリットは、以下のとおりです。
- 説明しやすい
- 動機づけになりやすい
成果が数値で示されるため、評価の根拠を示しやすく、報酬や賞与、インセンティブと連動させやすい点が大きなメリットです。
また、成果評価のデメリットは次のとおりです。
- 短期志向に陥りやすい
- プロセスや協働が見えにくい
- 外部要因で公平性が揺らぐ
数値を重視して短期的な成果を追いすぎると、中長期の成長や品質、チーム貢献が軽視されやすくなります。
また、景気の変動や市場の競争状況といった外部環境の影響を受けると評価が変わる可能性も。
こうした偏りを防ぐためには、品質指標や行動評価も取り入れると効果的です。
成果評価はどのような職場にマッチする?
成果評価は、明確な数値目標を設定でき、個人やチームの貢献を定量化しやすい業務と相性がよい制度です。
たとえば、以下のような分野が典型例となります。
- 営業(売上額・受注額)
- カスタマーサクセス(継続率・LTV)
- オペレーション(生産量・歩留まり)
一方、数値化が難しいバックオフィス業務などでは、成果評価だけでは公平な評価や育成が難しくなります。
能力評価や情意評価と組み合わせて運用するとよいでしょう。
コンピテンシー評価:成果につながる行動特性を可視化
ここでは、コンピテンシー評価について以下3点を解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
それぞれ詳しく見ていきましょう。
コンピテンシー評価は「成果を生む行動」に注目した制度
コンピテンシー評価は、高い成果を出している人たちに共通する行動特性を基準とし、その行動がどの程度発揮されているかで評価する制度です。
成果に直結する「仕事の進め方」が評価基準となります。
たとえば営業職なら「仮説を立て素早く検証する」プロダクトや企画なら「ユーザー理解を深める」といった具合です。
スキルや成果そのものではなく、「結果を生み出すための行動やプロセス」を評価する点が、コンピテンシー評価の最大の特徴です。
メリットとデメリット
コンピテンシー評価のメリットは、以下のとおりです。
- 育成に直結しやすい
- 行動基準が具体的で納得感を得やすい
できている行動と不足している行動が明確になるため、コーチングやOJTのテーマを決めやすく、育成にも直結します。
なお、以下のデメリットも存在します。
- 設計・更新の負担が大きい
- 職種や事業が変わると横展開しにくい
- 制度が形骸化しやすい
ハイパフォーマー分析や行動例の整備、職種ごとの重み付けなど、制度の設計や見直しに手間がかかります。
また、職種が変われば「成果を生む行動」も変わるため、別の部署への横展開はしにくい傾向があります。
コンピテンシー評価はどのような職場にマッチする?
コンピテンシー評価は、成果が「仕事の進め方」に強く左右される職場と相性がよいといえます。
たとえば、以下のような職場です。
- 営業
- コンサルティング
- プロジェクトマネジメント
- 企画・マーケティング
個人のやり方に依存せず、組織として成果を生む行動様式を統一したい職場にはとくに適しています。
バリュー評価:価値観や理念への共感度を評価に組み込む
ここでは、バリュー評価について以下のポイントを解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
それぞれ見ていきましょう。
バリュー評価は「企業の価値観との一致度」を見る制度
バリュー評価は、企業が掲げる価値観や行動指針を具体的な行動に落とし込み、その実践度を評価する制度です。
たとえば「顧客中心」を掲げる企業であれば、問い合わせへの初動の速さ、課題の深掘り、約束の遵守のように、企業の価値観に沿った行動を基準とします。
期首には企業が期待する行動を従業員と共有し、期末には実際の行動をベースに評価とフィードバックを行います。
信条そのものの同一性ではなく、日々の意思決定や振る舞いが価値観に沿っているかを評価の対象にする点が特徴です。
メリットとデメリット
バリュー評価には、以下のメリットがあります。
- 企業文化の浸透が進む
- 判断や行動の基準がそろう
企業の価値観を行動で示すことで、現場の日常的な判断基準がそろい、部門が違ってもぶれにくくなります。
採用・育成・評価の軸が一貫するため、組織として「こう振る舞う」という共通言語が生まれ、望ましい文化を定着させやすくなります。
反対に、バリュー評価のデメリットは次のとおりです。
- 主観や好みが混ざりやすい
- 多様性を損ないやすい
基準があいまいなまま運用すると、評価者によって判断が異なってしまいます。
対策としては、記録や成果物、顧客の反応など、具体的な事例をもとに評価することが重要です。
バリュー評価はどのような職場にマッチする?
バリュー評価は、価値観が日々のサービス品質や安全、顧客体験に直結する職場や、組織の一体感を重視する環境と相性がよいといえます。
たとえば、以下のような職場です。
- サービス・接客
- 医療・介護
- 教育
- ミッション・バリューを採用から育成まで貫きたい組織
そのため、価値観に基づく意思決定を全社に根付かせたい企業にとくに適しています。
多拠点・リモートなど分散した環境でも、判断基準やサービス品質を統一しやすいバリュー評価が有効です。
360度評価:多方面からのフィードバックを活かす仕組み

ここでは、360度評価について以下3点を解説します。
- 特徴
- メリット・デメリット
- マッチする職場
詳しく見ていきましょう。
360度評価は「他者からの評価」を取り入れる制度
360度評価は、上司だけでなく、同僚・部下・関係部門(場合により顧客)・本人の視点を取り入れて、日頃の行動や働きぶりを評価する制度です。
評価項目は、協働・コミュニケーション・リーダーシップ・信頼性など周囲から観察できる行動があげられます。
期中で、周囲からのアンケートと自由記述により「いつ・どこで・何をしたか」の事例を集めます。
期末は、その事例をもとに被評価者と面談する時期です。
ここで「自分では指示したつもりだが、部下からはあいまいに受け取られていた」といった事実確認や認識のズレを確認します。
上司からの評価に限定せず、同僚や部下の視点も加わることで、被評価者自身が気づきにくい癖まで可視化できる点が特徴です
関連記事:1on1面談とは?個人面談との違いと効果を高めるためのポイント
メリットとデメリット
360度評価のメリットは、以下のとおりです。
- 客観性が高まりやすい
- 気づきと成長を促しやすい
- 風土の問題を早期に拾える
若手の従業員だけでなく、管理職やリーダーの行動改善も促せるのが、360度評価の特徴です。
チーム内の不協和やハラスメントの兆候など、成果指標だけでは見えない組織の歪みも早期に発見しやすくなるでしょう。
また、360度評価のデメリットは、次のとおりです。
- 運用負担が大きい
- 人間関係が影響しやすい
- 目的があいまいだと反発を招きやすい
360度評価は評価者が多いため、設計・回収・面談の手間が増えてしまいます。
また、評価者の個人的な好みや配慮が評価に影響すると、評価の信頼性が低下します。
評価の目的を明確にし、基準を具体的に定め、評価者への教育を徹底しましょう。
関連記事:AI活用で1on1が変わる!評価の新常識とその裏ワザ
360度評価はどのような職場にマッチする?
360度評価は、横断協働が多く、周囲への影響力や協働スキルが成果に直結する職場にマッチします。
たとえば、以下のような職場です。
- 部門横断プロジェクト/マトリクス型組織
- 管理職・リーダー層の育成が重要な組織
- 営業・CS・企画・開発などナレッジワーク中心の職場
個人の成果だけでなく「周囲とどのように働くか」を重視し、リーダーシップや協働の質を高めたい職場には、360度評価がとくに適しています。
2つ以上の評価制度を組み合わせての運用も有効
1つの評価手法に偏ると、評価が一面的になりやすいです。
複数の評価制度を組み合わせることで、より多面的かつ公平な評価が可能になります。
たとえば、以下のような組み合わせが効果的です。
・成果評価×能力評価:数字の裏づけと成果を支えるプロセスにより、昇給や昇格の判断ができる
・バリュー評価×360度評価:価値観の体現を周囲の目で確認し、企業文化の定着につなげられる
評価制度を組み合わせる場合は、職種や役割ごとに評価の比重を調整します。
たとえば、営業職では成果を重視し、研究やコーポレート部門では能力や行動を重視するなど、実態に即した設計が求められます。
期初に目標と期待される行動を共有し、期末に振り返ることで、結果とプロセスの両面を評価することが可能です。
評価項目は2〜3個に絞り、評価者への教育や評価基準のすり合わせ(キャリブレーション)を行うことで、評価の納得感と一貫性を高められます。
自社に合った人事評価制度をどう設計するか?
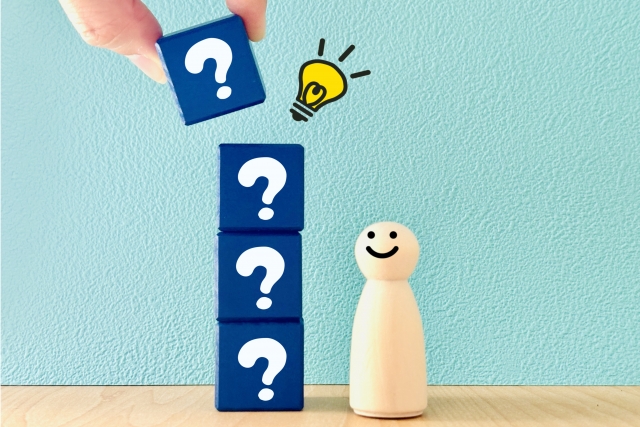
人事評価制度を設計する際は、評価の目的を明確にし、自社の事業戦略や人材の課題と整合させることが重要です。
そのうえで、職種や役割に応じた評価手法を選び、制度の運用方針を現場と共有することが成功のカギとなります。
ここでは、以下3つのポイントを解説します。
- 評価制度の目的を明確にする
- 自社の課題や人材戦略とすり合わせる
- 制度の設計・運用方針を関係者と共有する
それぞれ見ていきましょう。
関連記事:人事評価システムの導入成功事例15選!「やる気をなくす」人事評価制度を脱却する方法とは?
評価制度の目的を明確にする
評価制度を設計する際は、まず「何のために評価をするのか」を明確にします。
たとえば、処遇の公平性を高めたいのか、育成や配置の判断材料にしたいのかで、制度設計は大きく変わります。
また、KPIの策定も重要です。
評価結果を昇給・昇格に反映させるのか、育成目的にとどめるのかといった運用方針も、事前に関係者間で合意しておくとよいでしょう。
自社の課題や人材戦略とすり合わせる
人事評価制度は、企業が抱える課題や目指す組織像と連動している必要があります。
たとえば「若手の育成が進まない」「事業ごとに価値観がばらついている」といった現状をふまえ、成果や能力、価値観といった評価軸を設定します。
また、営業は成果を重視、研究職は能力と行動を重視するなど、職種によって重みづけを変える設計が有効です。
OKRやMBOと連動させる運用も検討できます。
制度の設計・運用方針を関係者と共有する
どれほど優れた人事評価制度でも、現場と認識がそろっていなければ機能しません。
制度の目的や評価の進め方を関係者に丁寧に共有することが大切です。
たとえば、評価シートの書き方や、どのような行動が高評価につながるのかといった基準の読み取り方など、具体的な運用方法を評価者に教育しておく必要があります。
基準があいまいなままだと、評価のばらつきや不満につながりやすいため、全員が共通の理解を持てるよう準備しましょう。
まずは小規模に試行し、課題を見つけてから全社展開するのも1つの方法です。
評価制度の特徴をつかみ、組織に最適な方法を導入しよう
人事評価制度にはさまざまな種類があり、組織の目的や業種によって適した手法は異なります。
たとえば、成果が数値で表れやすい営業部門には成果評価が、行動や姿勢が重視される職場には能力評価や情意評価が向いています。
複数の制度を組み合わせることで、結果・行動・価値観といった多面的な視点で従業員を評価でき、納得感も高まるでしょう。
評価制度の設計や運用を効率的に進めたい方には、クラウド型人事評価システム「ヒョーカクラウド」がおすすめです。
このシステムは、評価制度の構築から運用、フィードバックまでを一括で管理でき、自社に合った仕組み作りをサポートします。
自社に最適な評価手法を導入し、組織の成長につなげましょう。
ヒョーカクラウドの成功事例について
評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?
ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。
Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。
評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。
-

- 建築・建設業
評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。
会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...
-

- 医療・福祉業
- 100〜299名
従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に
導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
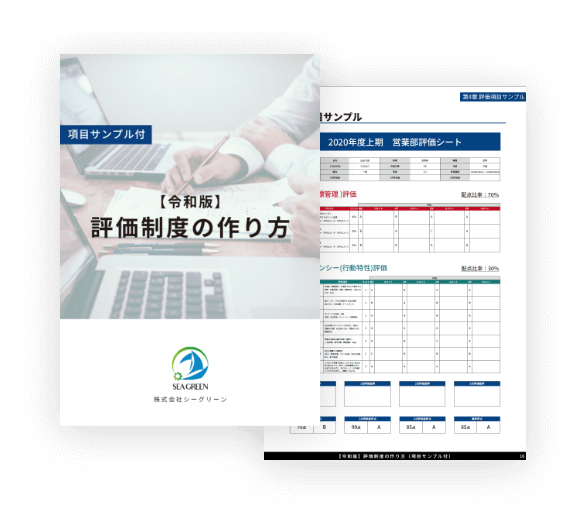
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル