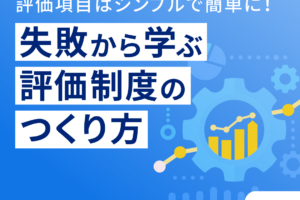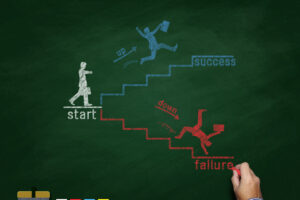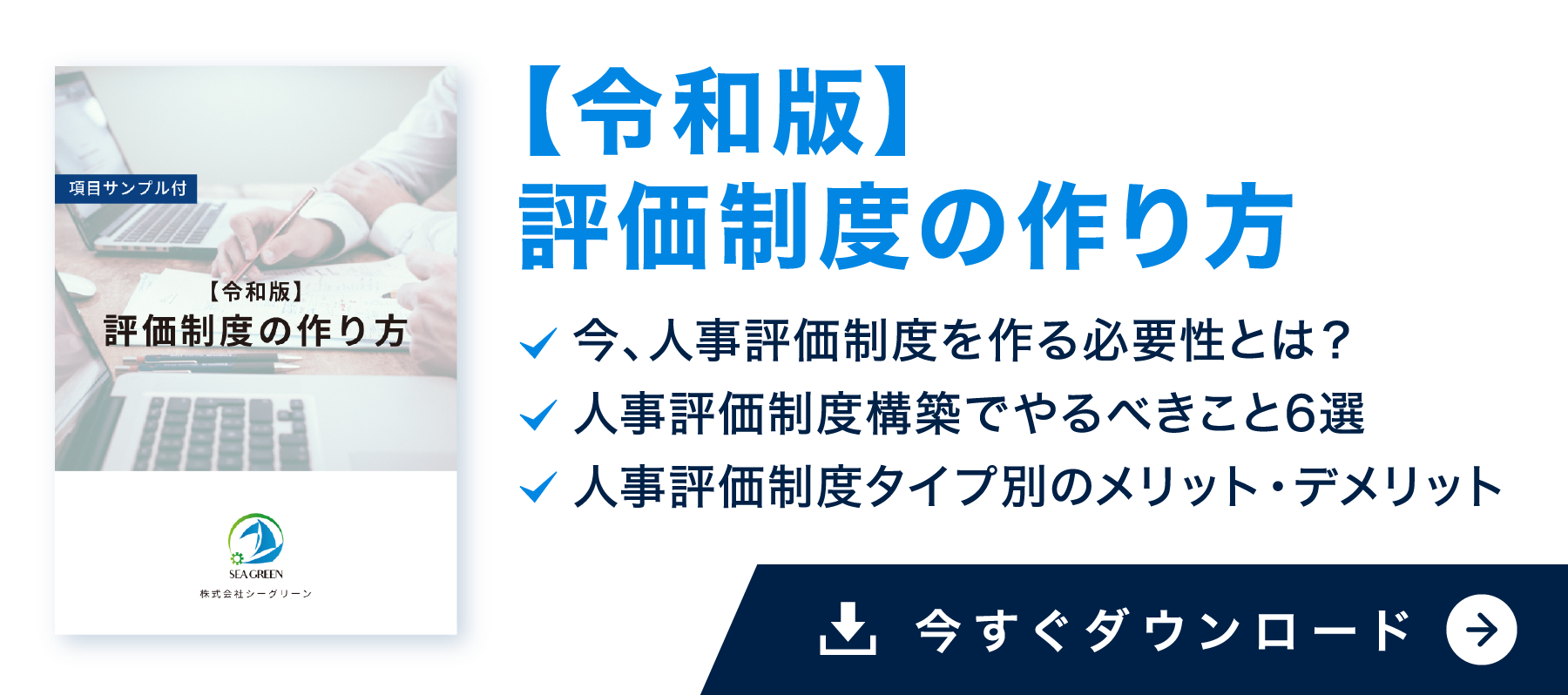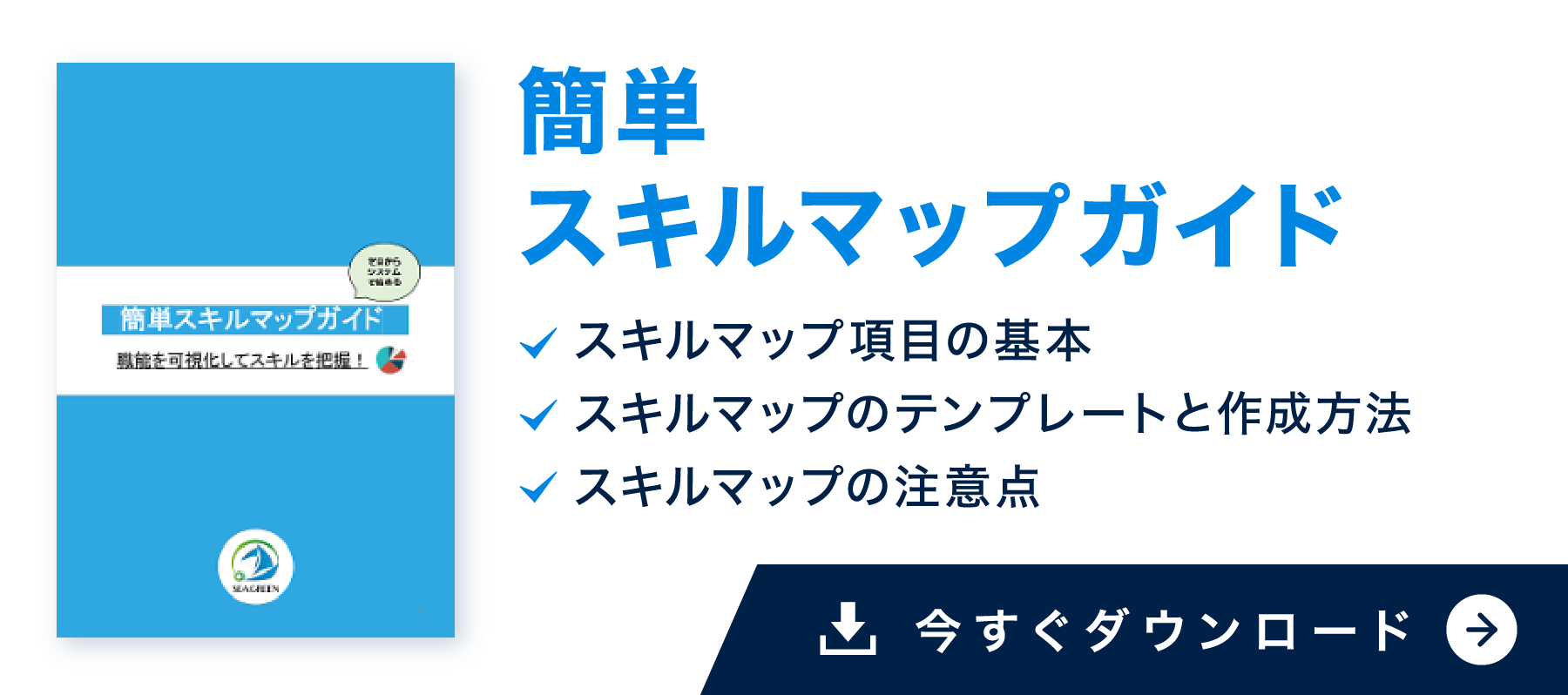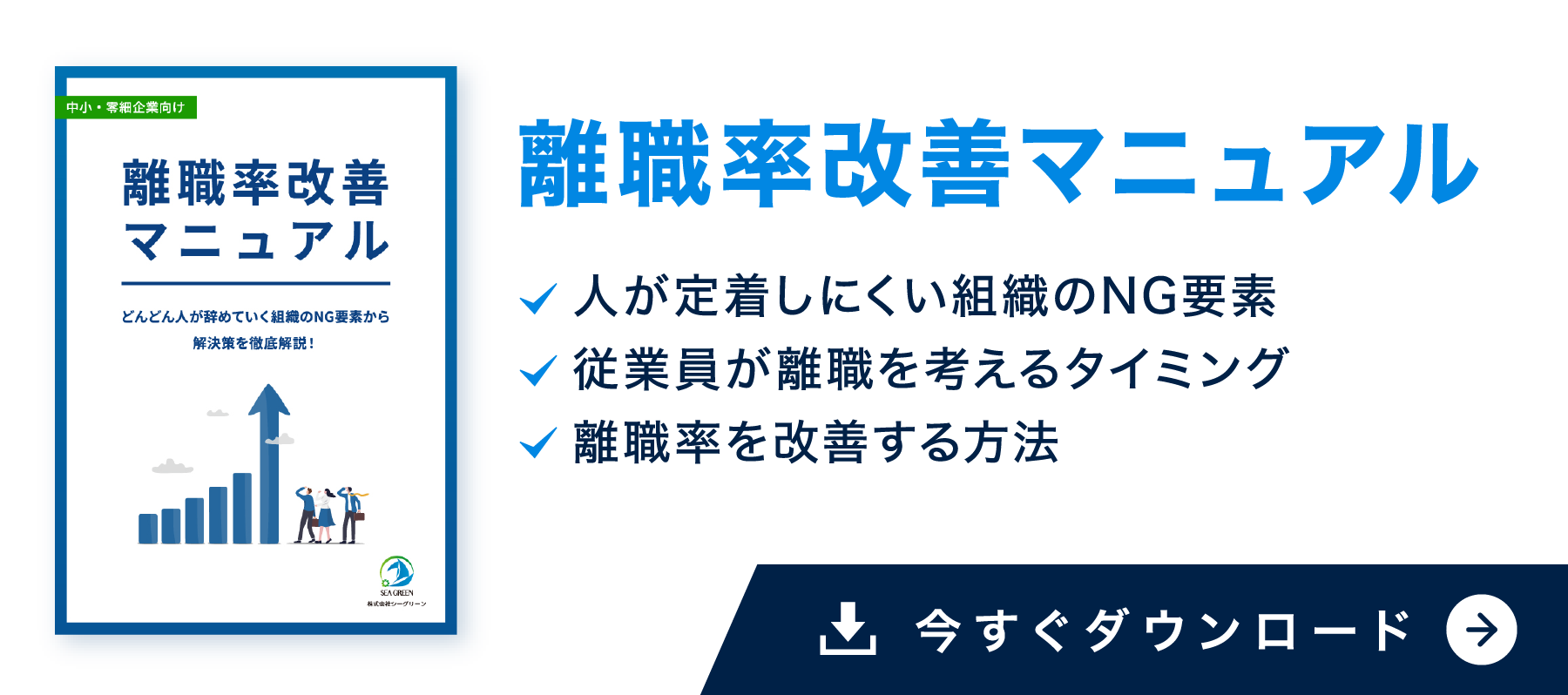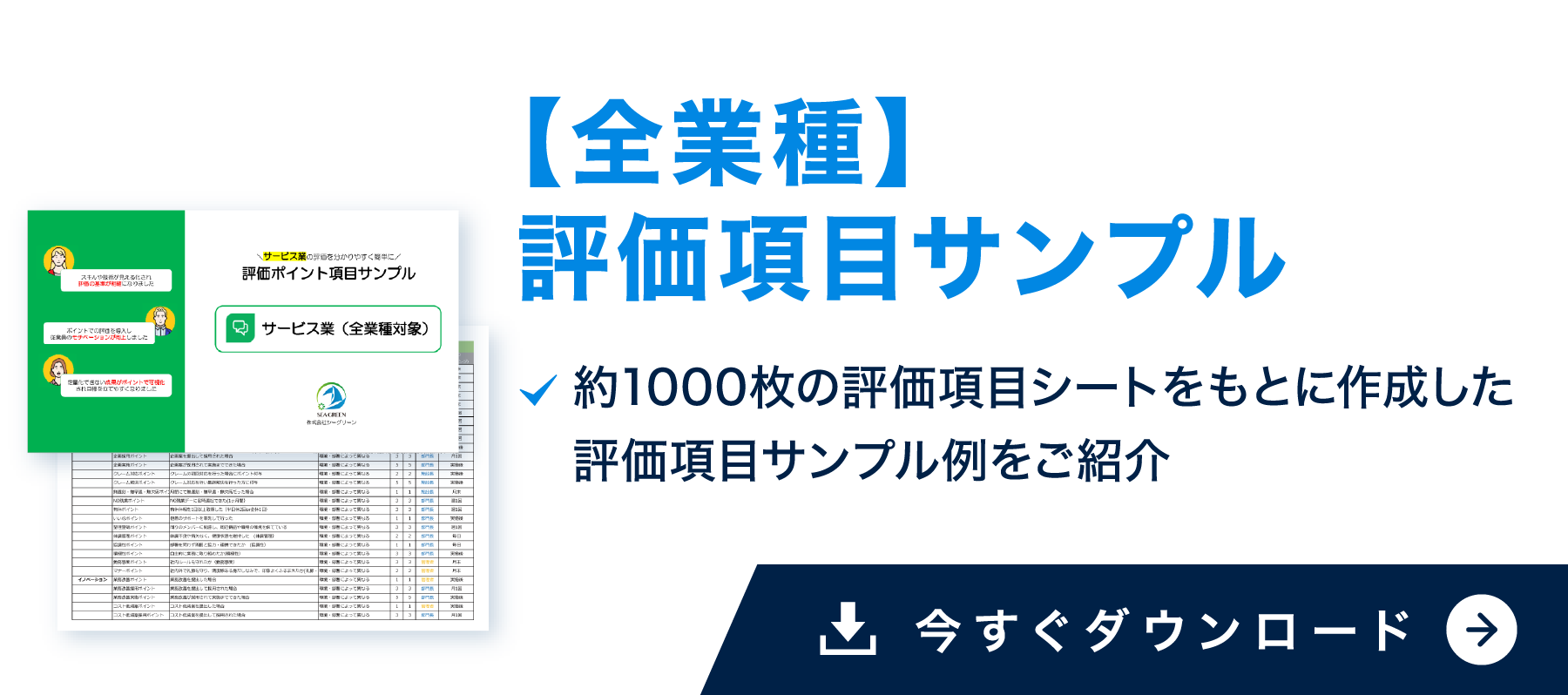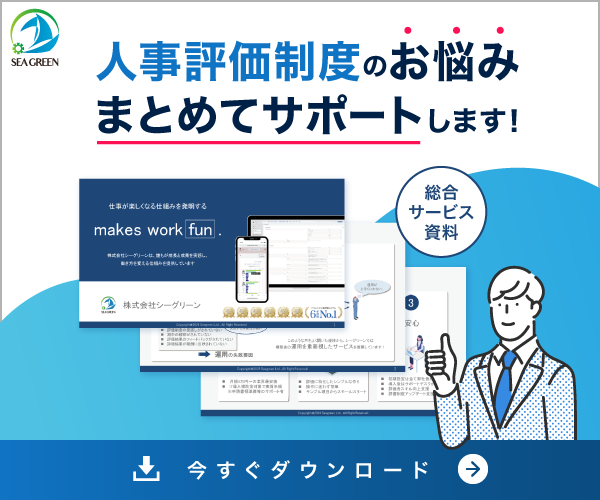「従業員のエンゲージメントが低い」「人事評価に対する不満が多い」など、人事評価に対する課題を抱えていませんか?
このような課題を感じている場合、人事評価制度が十分に機能していない可能性があります。 そこで注目したいのが、人事評価における1on1ミーティングの活用です。 本記事では、1on1が人事評価にもたらすメリット・実施手順、具体的な質問例などを解説します。
1on1とは?

1on1(1on1ミーティング)とは、上司と部下が定期的に行う、1対1の対話です。部下の成長支援をはじめ、「キャリア開発」「抱えている課題の解決」「エンゲージメント向上」などに焦点を当てて実施されます。率直な意見を話してもらえるよう、フランクな雰囲気で行われるケースが多いでしょう。
また1on1では、部下の自発的な思考を促しつつ、潜在能力の引き出しも意識する必要があります。そのため、上司には傾聴力・問題解決力・コーチング能力など、さまざまな能力が求められます。
1on1と面談の違い
1on1と面談は、しばしば混同されがちですが、実際には違うものです。ここでは、1on1と面談の違いについて解説します。
実施する目的

一般的な面談は、目標達成度のチェックといった「確認」や、業務の進捗を伝えるなどの「報告」に重きを置くケースが多いでしょう。基本的に、上司からの指示やすり合わせが中心となります。
一方で1on1を行う目的は、部下の成長や課題解決です。部下が何に悩み・何を目指すかを理解したうえで、適切なアドバイスやフィードバックを行います。そのため、一方通行ではなく、双方向から対話をすることが特徴です。
開催される頻度
1on1は、週1回から月1回など、高頻度かつ定期的に開催されます。1on1は、部下の成長促進や課題解決を目的とするからです。成長促進や課題解決は、一朝一夕で実現されるものではありません。状態を継続的に把握しつつ、変化に応じてサポート内容を変える必要があります。
一方で面談は、半期や四半期に一度といった不定期な開催が主流です。面談は、「確認」や「報告」に重きを置く傾向にあり、評価期間やプロジェクトの区切りといったタイミングに合わせて開催されることが多いからです。
1on1が人事評価で必要とされる理由
近年、1on1は人事評価においても重視される傾向にあります。ここでは、1on1が人事評価で必要とされる理由について、詳しく見ていきましょう。
評価の透明性を高める
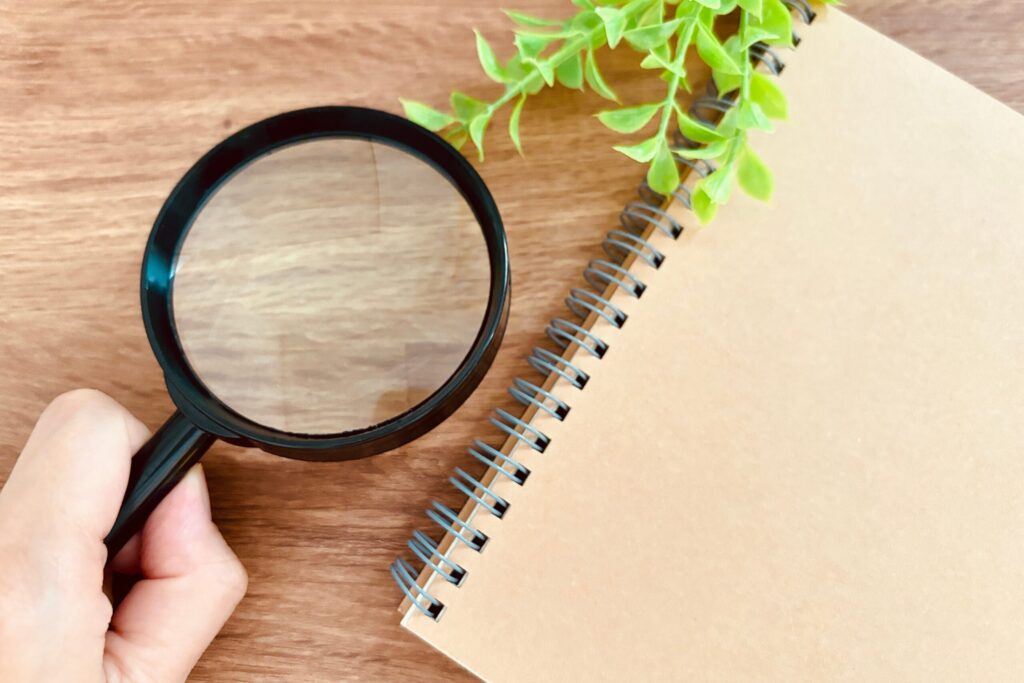
人事評価を実施するうえで、透明性の確保は欠かせません。透明性のある評価を実現することで、従業員の納得感を高めやすくなります。納得度の高い評価は、従業員のモチベーションやエンゲージメントアップも期待できるでしょう。また1on1を行うことで、上司から部下に対し、評価基準や期待される役割を伝える機会ができます。部下にとっても、「自身の課題」や「人事評価に関する疑問」などを質問する機会ができるでしょう。
また1on1は双方向の対話がベースにあるため、上司からのフィードバックだけでなく、部下からの率直な意見も吸い上げる必要があります。一方通行ではなく相互通行が実現するため、公平で建設的な評価が実現しやすくなります。
評価不満を防げる
評価不満が発生する原因の1つとして、「評価の不明確さ」が挙げられます。評価理由が曖昧な場合、従業員は自身の努力が正当に評価されていないと感じがちです。正当に評価されていないと思うと、不公平感を抱きやすくなります。
1on1を導入すれば、上司は部下に対して、「評価のプロセス」や「評価基準」を伝える機会が設けられます。適切に評価プロセスや評価基準を伝えることで、評価に対する透明さが生まれ、従業員は「自身の努力と評価との関連」を理解しやすくなるでしょう。その結果、不当な評価を受けている感覚が軽減され、不公平感の抑制に寄与します。
信頼関係の構築に役立つ
1on1は、上司が部下とじっくり向き合い、部下の話に耳を傾ける貴重な機会になり得ます。実際に、上司が部下の成長やキャリアに対し「真剣に向き合う姿勢」を示すだけでも、信頼関係の構築に役立つでしょう。
信頼関係の構築は、日々の業務をスムーズにするだけでなく、人事評価の場面でもよい影響を与えられます。たとえば、「建設的なフィードバックを受け入れやすくなる」「困難な目標にも意欲的に挑戦できるようになる」などが挙げられます。1on1を通じて信頼関係が築かれると、心理的安全性の向上や活発な意見交換の促進なども期待できます。率直な意見交換ができる環境は、組織の生産性向上にも寄与するでしょう。
評価制度の質向上や改善につながる
評価制度は、社員の成長を促すツールですが、実態と乖離していると逆効果になりかねません。そのため、制度が意図通りに機能しているかや、改善点を確認する必要があります。1on1は、評価制度の実態や改善点を知る機会になるため、評価制度の質向上や改善にも役立ちます。
1on1を定期的に実施し、その内容を振り返ることで、人事評価制度に対する具体的な改善点も見えやすくなるでしょう。たとえば、「特定の評価項目に関する対話が不足している」「特定の層に共通の課題が見られる」といった改善点を発見できます。
1on1でよくある失敗パターン
1on1は人事評価の効果を高められる反面、適切に活用できないと、思うような効果が得られないこともあるでしょう。ここでは、1on1でよくある失敗パターンについて解説します。
単なる報告・確認になっている

1on1が「今月の重要タスクは?」「進捗は?」といった、進捗確認や業務報告の場だけに終始してしまうケースは少なくありません。 形式的なやり取りを行う場合、上司は部下の状況を把握できるかもしれませんが、1on1本来の目的は達成できないでしょう。1on1の本来の目的は、従業員の成長や課題解決につなげることです。
単なる報告・確認の場になっていると、部下の本音や隠れた悩み、長期的なキャリアに関する展望などが引き出せません。結果として、部下の成長支援や適正な人事評価につながらないという事態も危惧されます。また、上司も部下も1on1を「作業」のように感じてしまい、形骸化にもつながってしまいます。
上司が一方的にフィードバックしている
上司が「持論の押しつけ」や「指示命令」をするなど、自分の意見や要求だけを一方的に伝えるケースも、よくある失敗パターンの1つです。上司が一方的にフィードバックしている状態になると、部下は「自分の話を聞いてもらえない」「意見を言っても無駄だ」と思うようになります。自分の気持ちをないがしろにされていると感じれば、モチベーションの低下やエンゲージメントの低下といった事態になることも、時間の問題です。
その結果、部下は発言をためらうようになり、双方向の対話という1on1の最も重要な要素も失われてしまいます。部下の主体性も阻害されやすく、人事評価の質向上につながらないでしょう。
不定期に行っている
1on1は、定期的に開催することで、その効果を最大限に発揮できます。問題発生時や人事評価の直前のみといった単発的な1on1では、上司と部下の間に十分な信頼関係を築けないでしょう。不定期開催の1on1は、表面的な会話に終始しがちであり、従業員の本音や潜在的な課題を引き出すことがむずかしくなります。
また、継続的な成長支援や、評価の根拠となる具体的な行動事実の蓄積は難しく、一時的な対策に留まる傾向にあります。結果として、部下の変化や成長を見逃し、適切な評価につながらない可能性があるでしょう。定期的かつ継続的に対話することで、1on1の真価を発揮しやすくなり、組織全体の成長促進につながります。
1on1を成功させるポイント
人事評価で「1on1」を活用し、効果的に実施できている企業には、共通のポイントが見受けられます。1on1を成功させる主なポイントは、以下の通りです。
部下の主体的な発見を促す

効果的な1on1では、上司はティーチングではなく「コーチング」を意識しつつ、部下自身が課題に気づけるようなプロセスを重視します。 上司は質問を重ねることで、部下が自身の状況を客観的に振り返り、「何が問題なのか」「どうすれば改善できるのか」を内省することについて支援できます。内省による気づきを通じて、部下は課題に対する当事者意識を持ち、自発的な姿勢で取り組みやすくなるでしょう。
また自発的な姿勢で取り組めば、部下の問題解決能力や自己成長力の向上も期待できます。
双方向での対話をしている
1on1は、相互理解を深めるための「対話の場」です。一方的なコミュニケーションに終始してしまうと、部下は意見を言いにくくなり、表面的な会話で終わる可能性があるでしょう。 そのため、上司は部下の意見や考えを注意深く聞き、共感的な姿勢を示すことが大切です。部下から上司へのフィードバックを促すことで、よりオープンなコミュニケーションも確立しやすくなります。
1on1を通じて得られた情報やフィードバックは、組織全体の成長を促進する原動力となるでしょう。人事評価の透明性を高め、評価に対する納得感を醸成する効果も期待できます。
PDCAサイクルを確立させる
PDCAサイクルが確立されていないと、1on1は単なる雑談で終わりやすくなります。単に話をするだけでは、「目標設定」「進捗確認」「改善策の検討」などが行われないため、単なる会話になりがちです。単なる会話では、期待する成果にはつながりにくいでしょう。PDCAサイクルを確立させると、目標への達成度合いや、課題に対する改善アクションが記録されるため、評価者は何を根拠に評価すればよいかがわかります。結果として、人事評価の場面でも、客観的な根拠を示しやすくなります。
たとえば、「来週までにExcelのマクロスキルを習得する」「新規顧客開拓のプロジェクトで〇〇件のリードを獲得する」などの目標を設定し、進捗と成果を次回の1on1で確認します。PDCAを回しつづけることで、人事評価の客観的な根拠を積み上げられるでしょう。
1on1を人事評価で活用できる場面
1on1は、人事評価に関して、さまざまな場面で活用できます。活用できる主な場面は、以下の通りです。
目標を設定する際

目標設定をする際には、上司が一方的に決めた内容を押しつけるのではなく、部下が納得できる内容にすることが重要です。そのためには、双方向で対話する「1on1」を活用すると効果的です。
部下のキャリア志向やスキル、意欲を踏まえ、対話を通じて適切な目標を作り上げましょう。1on1を活用すれば、意見を反映しながら目標設定をできるため、納得度の高い目標を設定しやすくなります。納得できる目標であれば、モチベーションを維持しながら、目標達成に向けて意欲的に取り組めるでしょう。また1on1で、個人目標と組織目標との整合性も説明すれば、目標の意義をより理解してもらいやすくなります。
期中のレビュー
評価期間の途中で1on1を行うことで、目標達成に向けた進捗を確認できます。また状況によっては、軌道修正も迅速に行えます。
期中に行う1on1レビューでは、まず目標に対する進捗状況を確認します。「目標Aはどのような状況か」「具体的な成果は」「目標Bで困難に直面していないか」といった点を確認することで、遅れや問題点を早期に発見できるでしょう。
また、個人のスキルアップやキャリアに関する考え方の変化によって、置かれた状況は変化することがあります。期中に1on1を実施することで、変化に応じた軌道修正を行えるため、常に最適な方向にすすみやすくなります。
成果・行動の振り返り
評価期間終了時に1on1を実施すると、評価結果の精度を高めやすくなります。上司と部下で、成果と要因を話し合うことで、評価のずれを最小限に抑えられるからです。主観的な印象も排除しやすく、客観的な評価にも寄与します。期間中の出来事を掘り起こし、記憶を補完することで、評価の根拠となる情報も増やせるでしょう。
成功要因や改善点を明確にすることで、今後の成長戦略にもつなげられます。
たとえば、目標達成できた要因が「顧客ニーズを的確に把握していた」だと判明すれば、その能力を他のプロジェクトにも応用できます。逆に、目標未達の要因が「情報収集不足」であれば、「情報収集スキル向上のための研修受講」や「目標の再検討」といった具体的な改善策を講じられるでしょう。
評価フィードバック
人事評価のフィードバックを1on1で実施することで、部下の成長を促進しやすくなります。評価の根拠を具体的に説明し、強み・改善点を伝えましょう。
たとえば、「〇〇のプレゼン資料の構成は素晴らしいが、データ分析に基づいた裏付けがあるとさらに説得力が増す」のように、具体的な事例を挙げながらフィードバックします。具体的な内容でフィードバックすることで、部下は自身の強みや改善点をイメージしやすくなります。
また評価フィードバックでは、部下からの質問や意見に耳を傾けることも重要です。部下の不安解消に役立ち、モチベーションやエンゲージメント向上にもつながるでしょう。
1on1×人事評価の実施手順
つづいて、納得できる人事評価につながる1on1について、具体的な実施手順を紹介します。実施手順は、以下の通りです。
実施目的を明確にする

1on1を人事評価に活用する際は、1on1導入の意図と、それぞれの期待値を明確にすることが大切です。意図と期待値が不明確なままでは、1on1が雑談で終わってしまう傾向にあります。すると、1on1の人事評価に対する貢献度も薄れてしまいがちです。まずは「なぜ1on1を導入するのか」「人事評価に1on1を活用して何を実現したいのか」といった組織全体の意図を、上司と部下で共有しましょう。
たとえば、上司は1on1を通じて「部下の成長を促進し、組織の目標達成に貢献すること」を目的とします。対する部下は「自身の強み・弱みを理解し、キャリアプランを明確にすること」を期待するなど、 それぞれの立場における期待値を設定します。組織全体の意図と個別の期待値を共有することで、1on1の方向性が定まり、双方にとって有益な時間となるでしょう。
実施頻度を設計する
1on1の実施頻度は、評価の精度や部下の成長速度を左右します。高頻度であれば、細かな進捗確認や問題発生時に迅速なフィードバックができます。ただし、頻度が高すぎると、上司・部下ともに負担が増えるため、業務との兼ね合いを考慮する必要があるでしょう。
とはいえ、頻度が低すぎると、日々の状況把握がむずかしくなり、タイムリーなサポートが遅れる可能性もあります。部下の経験やスキル、業務内容などを考慮し、最適な頻度を設計しましょう。たとえば、経験の浅い部下には月1回、自律性の高い部下は四半期に1回など、柔軟に対応することが大切です。
評価と1on1記録の連携方法を決定する
1on1の内容について、評価への連携方法を決めておくと、納得感を高めやすくなります。もし部下が課題・努力・成功体験を語っても、評価への反映度が不明確であれば、不審に思う可能性があるでしょう。そのため、1on1で得られた情報について、人事評価シートや評価面談でどのように活用するかを明確に示すことが大切です。
具体的には、「活用範囲」「評価に反映させる情報の種類」などを決め、従業員に合意を得る必要があります。たとえば、目標達成に関する進捗や課題は評価に反映するが、「個人的な悩みや相談は評価対象外とする」といった線引きが考えられます。
評価基準を踏まえた質問リストを作成する
1on1を効果的に活用するために、評価基準を踏まえた質問リストを作成するとよいでしょう。質問リストを作成する際には、「目標達成度」「行動特性」「スキル向上」など、評価項目に関連する内容で構成します。たとえば、以下のような質問内容が挙げられます。
~質問の例~
| 目標達成度 | 目標達成のために注力した点は何ですか? |
| 行動特性 | 目標達成で困難に感じた部分はありますか?その際に、どのように対処しましたか? |
| スキル向上 | 現在の業務において、自身の活かせるスキルは何ですか?今後、さらに強化したいスキルはありますか? |
上記のような質問を用意することで、定量的な成果だけでなく、プロセスや行動特性、成長意欲などを把握しやすくなります。
また質問リストは、1on1のテーマや部下の状況に合わせて柔軟に調整することも重要です。たとえば、プロジェクトの進捗に合わせた質問や、部下のキャリアに関する質問を追加することで、よりパーソナライズされた1on1になるでしょう。
1on1の内容を記録する
1on1の内容を記録することで、過去の会話内容を振り返ることが可能です。また記録内容は、評価結果の根拠としても活用できます。次回の1on1や評価面談の際に、過去の記録を参照することで、具体的な事例に基づいた建設的なフィードバックも可能になります。
記録をする際には、「目標達成の進捗」「課題」「改善策」「上司からのフィードバック」「部下の自己評価」などを明記するとよいでしょう。記録方法としては、専用ツール・共有ドキュメント・議事録などが挙げられます。上司と部下の双方が記録を共有し、認識のずれがないかを確認することもおすすめです。
効果測定を行い次回に活かす
効果測定をすることで、「1on1が成長を促進しているか」「目標達成に貢献しているか」などを客観的に評価できます。たとえば目標達成率が低い場合、1on1の内容が適切でないケースもあれば、目標設定自体に問題があるケースもあるでしょう。
効果測定の結果、1on1が期待される成果を上げていないと判明した場合、原因を分析する必要があります。1on1の実施頻度・時間・アジェンダの内容・上司の傾聴スキルなど、多角的な視点から改善点を探ります。目標設定が高すぎたり曖昧な場合には、目標を見直し、部下と合意形成を図ることが大切です。
効果的な1on1を実施するための質問例
効果的な1on1を実施するためには、適切な質問をすることが重要です。ここでは、5つの場面を挙げて、それぞれに適した質問例を紹介します。実際の1on1でも、ぜひお役立てください。
目標と進捗の確認に関する質問
- 現在の目標に対して、進捗はどうですか? どのような成果が出ていますか?
- 目標達成に向けて、何か困っていることはありますか? もしあれば、どのようなサポートが必要ですか?
- 目標設定時に想定していた状況と比べて、何か変化はありましたか? 目標の見直しは必要ですか?
- 今週(または今月)、最も注力したことは何ですか?
- 目標達成のために、今後どのようなアクションを取りたいですか?
成長と学習に関する質問
- 最近、何か新しいスキルや知識を習得しましたか?(習得した場合)どのような学習を実践しましたか?
- 仕事を通じて、成長を実感することはありますか? 具体的な事例があれば教えてください。
- 今後のキャリアに向けて、どのようなスキルや知識を身につけたいですか?
- 会社やチームで提供されている研修や学習機会で、興味がある内容はありますか?
- 今の仕事で、さらに挑戦したい内容はありますか? または、ほかに挑戦したい分野はありますか?
フィードバックと内省を促す質問
- 自分自身の強みと弱みについて、どのように認識していますか? 具体的な事例を交えながら教えてください。
- 過去の経験から学び、改善できた点はありますか?
- 今回のプロジェクト(タスク)で、うまくいった点と改善すべき点について教えてください。
- 周囲からの期待に応えられていると思いますか? もしそうでない場合、どのようなギャップを感じていますか?
関係構築とエンゲージメントに関する質問
- チームメンバーと、円滑にコミュニケーションを取れていますか?
- 職場の人間関係で、何か困っていることはありますか?
- 仕事に対するモチベーションは、高いですか? 低い場合、モチベーションを阻害する要因は何でしょうか?
- 会社やチームに対し、貢献できていると思いますか?
- 仕事以外で取り組んでいる活動や趣味はありますか?
- ワークライフバランスは取れていますか?
キャリアと長期的な視点に関する質問
- 3年後・5年後にどのようなキャリアを築きたいですか? 具体的な目標はありますか?
- 目標達成に向けて、今どのような準備が必要だと思いますか?
- 会社の中で、ロールモデルとなる人物はいますか? その理由は?
- キャリアプランについて、会社からのサポートで期待することはありますか?
- 今の仕事は、長期的なキャリア目標につながっていますか?
人事評価×1on1でよくある質問・FAQ
人事評価で1on1を導入する際、効果を最大化するには、適切な運用が欠かせません。ここでは、人事担当者や評価者が直面する可能性のある疑問点について、まとめました。
1on1の内容は、人事評価にどう活用するのが効果的ですか?
1on1の内容は、人事評価の補完情報として活用するとよいでしょう。表面的な業績だけでは見えにくい、「部下の成長過程」「課題への取り組み方」「目標達成への意識」などを把握する際に役立ちます。また1on1は、評価全体の10〜20%程度として考慮するとよいでしょう。
1on1で話さない方がよい内容はありますか?
1on1は成長をサポートする場なので、人事評価そのものの議論や、プライベートを詮索する質問は避けるべきです。また、うわさ話や説教、会社の機密情報といった話題も避けましょう。このような話をすると、信頼関係を損ねたり、部下の本音を引き出しにくくなります。建設的な議論を心がけ、成長を促す対話について意識することが大切です。
どれくらいのスパンで実施すればよいですか?
1on1の適切な実施頻度は、部下の経験やスキル・業務内容・チームの状況などによって異なります。一般的には、月に1回程度を目安としますが、「新入社員」「異動直後の社員」「むずかしいプロジェクトに取り組んでいる社員」に対しては、週に1回など、短いスパンで実施することも有効です。重要なのは、定期的に実施することと、部下の状況に合わせて対応することです。
1on1の成果は、どのように測定すればよいのでしょうか?
1on1の成果を測定する際には、定量的な指標と定性的な指標を組み合わせましょう。
定量的な指標としては、「目標達成率」「KPIの達成度」「離職率の低下」などが挙げられます。定量的な指標は、1on1が直接的に貢献した結果を測定できます。
定性的な指標の例は、「部下のモチベーション」「自己成長の実感」「上司との信頼関係」などです。定性的な指標は、アンケートやインタビューを通じて把握できます。
評価者と部下の相性が悪い場合、1on1をどのようにすすめるべきですか?
まずは1on1の目的について、「部下の成長をサポートすること」だと、上司が認識する必要があります。また、部下の話を先入観なく最後まで聞く姿勢も求められます。フィードバックをする際には、個人的な感情は避け、具体的な事実に基づいて話しましょう。
それでも、相互理解がむずかしい場合には、人事担当者などに同席してもらうこともおすすめです。状況が改善しない場合は、上司の変更も視野に入れる必要があります。
1on1×人事評価で納得度向上に専門ツールがおすすめな理由
人事評価で1on1を活用する際には、専門ツールの活用がおすすめです。主な理由は、以下の通りです。
1on1と評価の一貫性を確保できる

1on1の内容は、評価の全てではありません。しかし、人事評価との連携は、従業員の納得度を高めるうえで重要です。評価結果と日頃のコミュニケーション内容が乖離している場合、従業員は評価に対する不信感を抱きやすくなります。
また会社の規模が大きくなればなるほど、全ての従業員の1on1情報を評価者が把握し、偏りなく評価に反映させるのは困難です。 専門ツールを導入すれば、1on1での目標設定・進捗状況・課題・フィードバックなどを一元的に管理できます。
さらに記録された情報は、従業員自身もチェックできるため、自己評価の精度向上にもつながります。評価の透明性も高まり、評価に対する納得度とモチベーション向上にも貢献するでしょう。
部下の納得感を高めやすい
人事評価に対し部下が納得感を持てると、モチベーションアップや離職率低下が期待できます。また専門ツールを活用すれば、1on1ミーティングでの対話内容を可視化できます。ツールに記録された客観的なデータが評価の根拠として残るため、評価の公平性も増すでしょう。
さらに、ツールに蓄積された「過去の1on1」の記録は、日々において自身の成長を振り返る材料となります。また専門ツールを活用すれば、社内サーバーやクラウド上で情報が一元管理されることから、容易にアクセスできるでしょう。
担当者の管理負担を軽減できる
1on1ミーティングを実施する場合、事前準備や評価データの収集・集計などを行うため、担当者に負担がかかる傾向にあります。専門ツールを導入すれば、1on1に関する業務を効率化でき、担当者の負担を軽減できます。たとえば、「1on1のスケジュール管理」「実施状況の追跡」「評価データの集計」などを自動化できるでしょう。またツールによっては、評価結果の分析機能や、レポート作成機能も搭載されているため、人事戦略の立案にも役立ちます。従業員情報の管理を一元化できることから、人事関連業務全体の効率化にも寄与します。
人事評価システム『ヒョーカクラウド』は1on1機能も搭載
『ヒョーカクラウド』は、日常的な1on1と人事評価を効果的に実現できる、クラウド型の人事評価システムです。ヒョーカクラウドの1on1には、以下のような機能が搭載されています。
面談のログ機能
『ヒョーカクラウド』の面談ログ機能を活用すれば、1on1での対話内容をデータとして記録できます。評価者は過去の会話内容をいつでも振り返ることが可能で、主観に偏らない客観的な評価が実現します。さらに記録されたデータは、評価面談時だけでなく、日々の業務におけるアドバイスや指導にも活用できます。
アジェンダ共有機能
『ヒョーカクラウド』のアジェンダ共有機能を活用すると、1on1ミーティング前に、面談内容を共有できます。双方が事前に議題を把握できるため、効率的な対話が期待できるでしょう。また、アジェンダの内容は記録として残ることから、過去の振り返りや、今後の目標設定の参考資料としても活用できます。
MBOやコンピテンシー評価とのデータ連携
『ヒョーカクラウド』は、MBO(目標管理制度)やコンピテンシー評価とのデータ連携機能を備えています。1on1ミーティングにおいても、目標達成度や行動特性に関する具体的な議論が可能となり、効果的な育成や評価につなげることが可能です。たとえば、目標の進捗状況や達成度を確認しながら、課題の特定や改善策の検討を行えます。コンピテンシー評価の結果を基に、能力開発計画の策定に役立てることも可能です。
1on1で「納得できる人事評価」を実現させよう!
人事評価に対する不満は、従業員の納得度を低下させ、モチベーション低下や組織の停滞を招きます。人事評価に1on1を活用すると、評価への納得度を高めやすく、効果的な人事評価を実現しやすくなります。
また人事評価に1on1を活用する場合には、専用ツールの利用がおすすめです。人事評価システム「ヒョーカクラウド」なら、効果的な人事評価と1on1が実現します。資料は、以下から無料でダウンロードできます。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
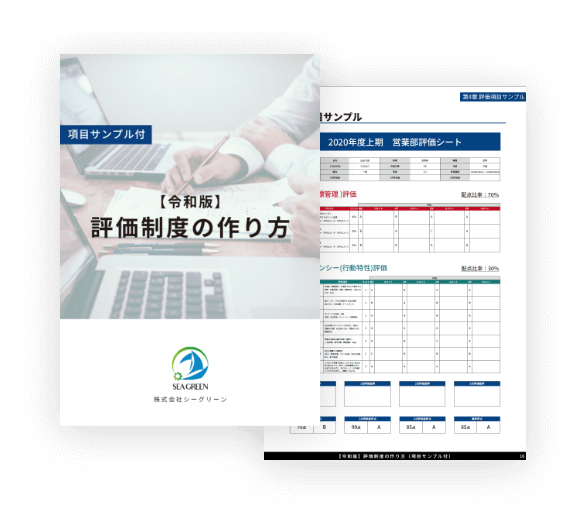
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル