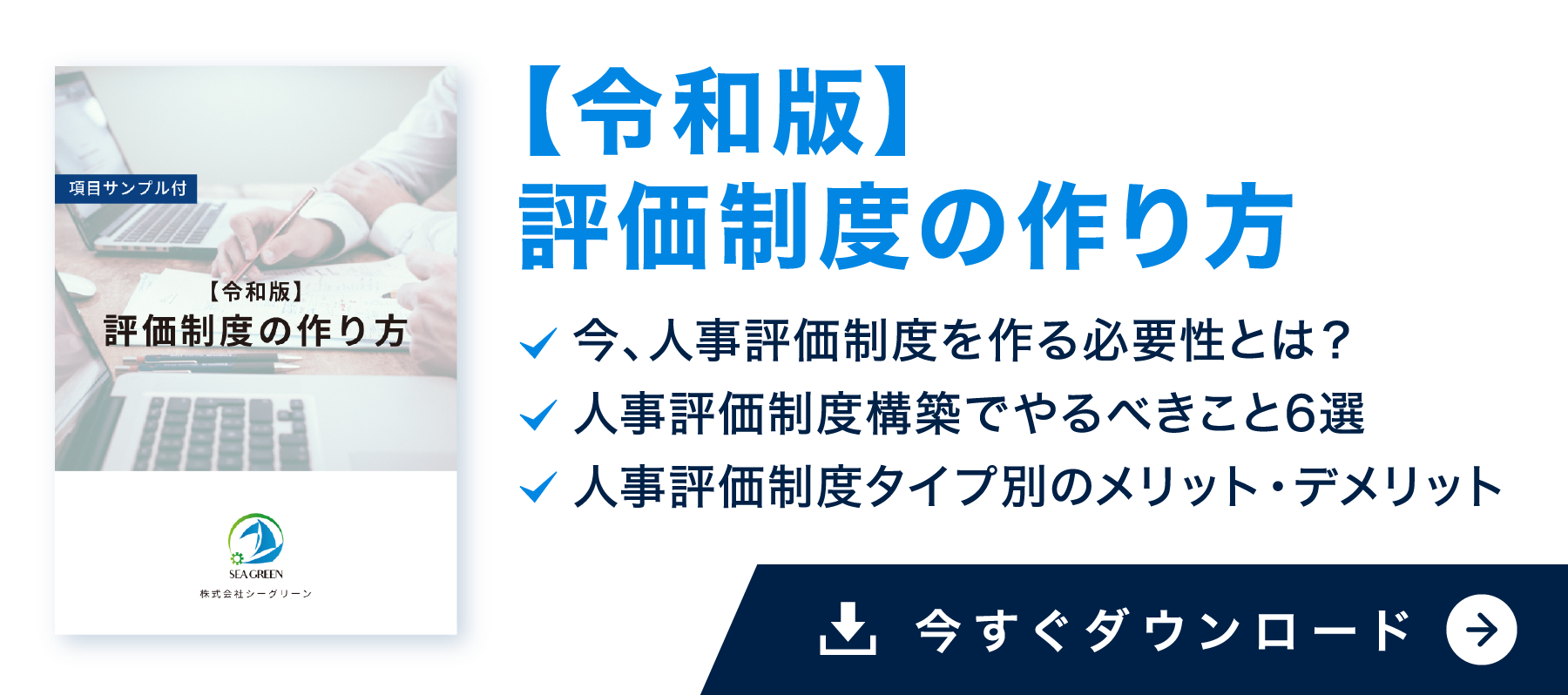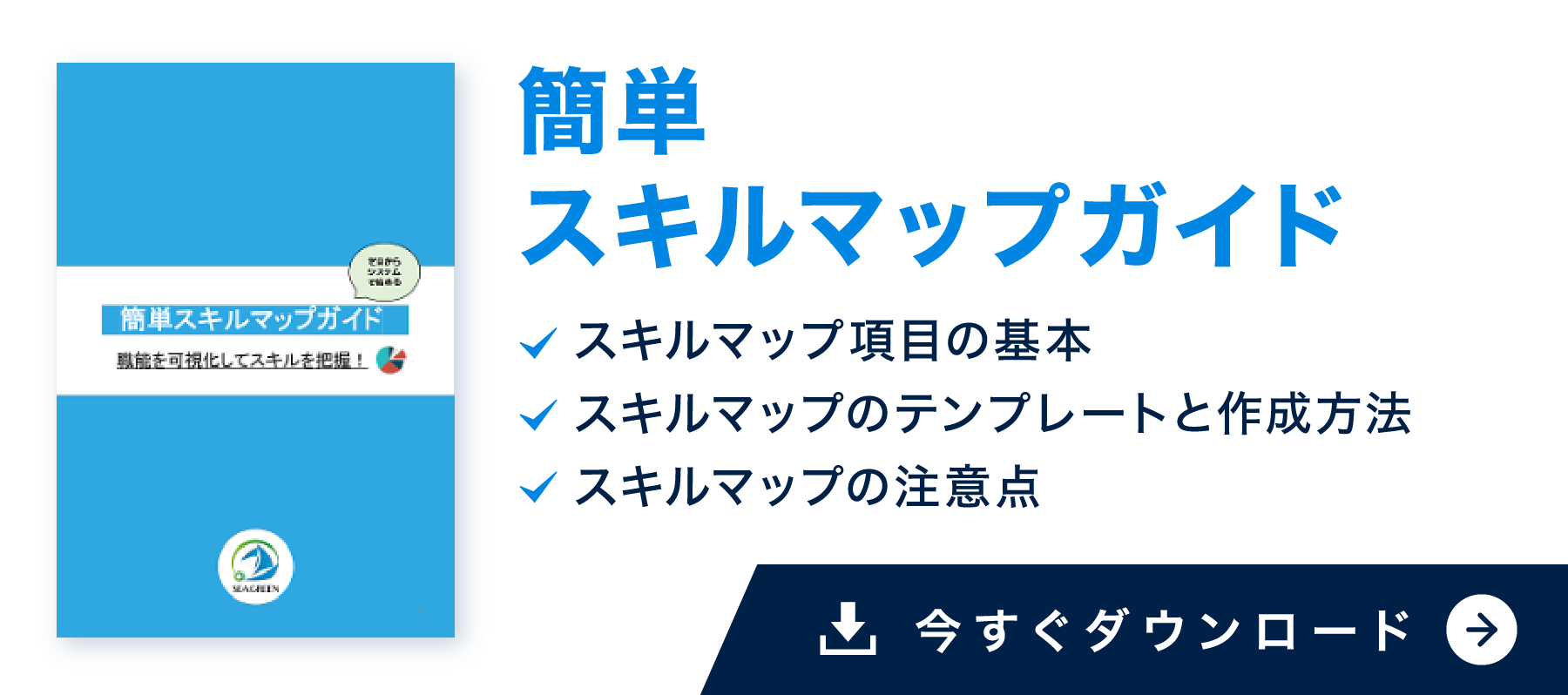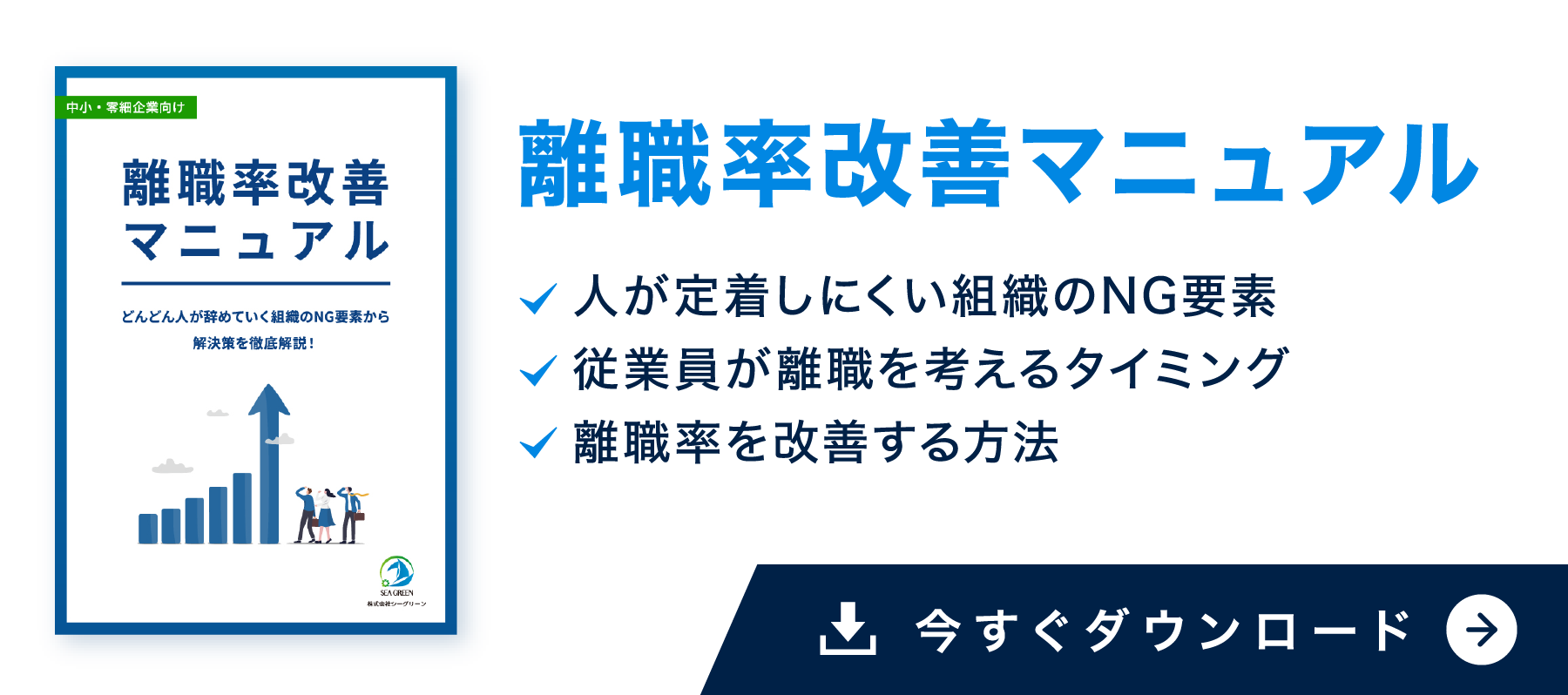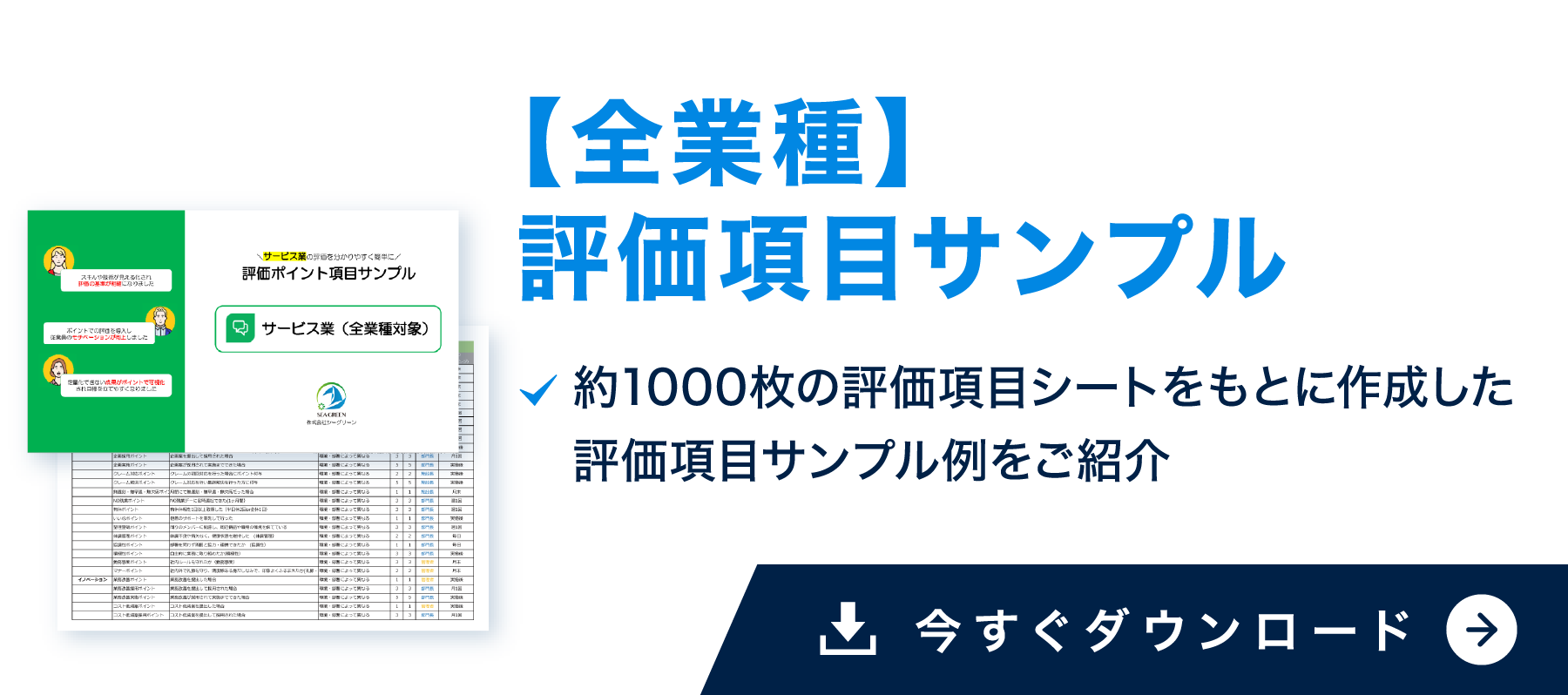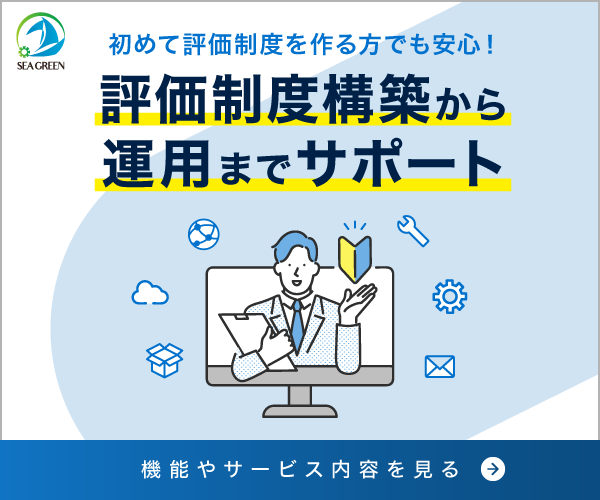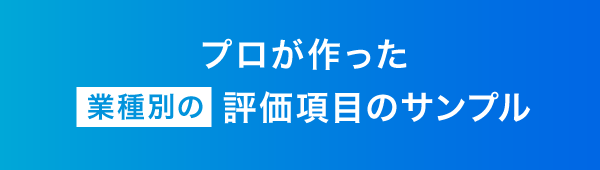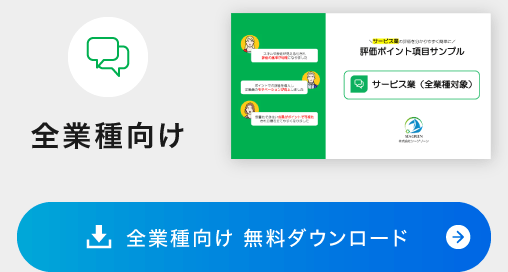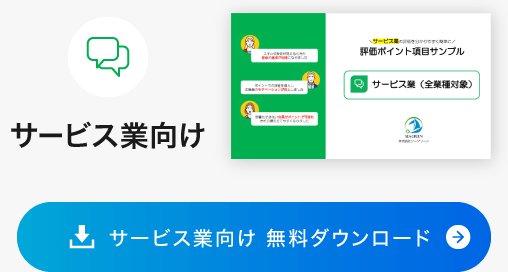「現状の評価制度がうまく機能しないので、内容を見直したい」
「評価制度の導入にあたり、適切な内容を用意したい」
このような考えをお持ちではありませんか?
人事評価制度とは、従業員の働きぶりを評価し「企業全体の生産性向上」に役立てる制度です。そのため正しい制度が必要があるものの、適切に作られていない企業も一定数存在します。
当記事では、人事評価制度の正しい作り方やポイント・よくある質問について解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
押さえておきたい!評価制度の代表的なフレーム
まずは、評価制度の代表的なフレームについて見ていきましょう。昨今では、評価を実施する際に、さまざまな評価手法が活用されています。また、複数の手法を組み合わせて運用する事例も見受けられます。一般的に使用されるフレームは、以下の通りです。
| 評価制度 | 特徴 |
| MBO | 個人と上司で決めた目標に対し、その達成度を評価する |
| OKR | 高い目標と成果指標を評価する |
| 360度評価 | 上司・同僚・部下など、複数の視点から評価する |
| バリュー評価 | 企業理念や価値観に基づく行動に対し評価する |
| 年功序列 | 勤続年数や年齢に応じて、給与や役職が上昇する |
| コンピテンシー評価 | 高い成果を挙げる人材の行動パターンと比較し、評価する |
多様な選択肢がある中で、制度設計では、自社のビジョンや組織風土に合う仕組みを選ぶことが大切です。各評価制度の詳細について、以下をチェックしてみましょう。
MBO/Management by Objectives(目標管理制度)
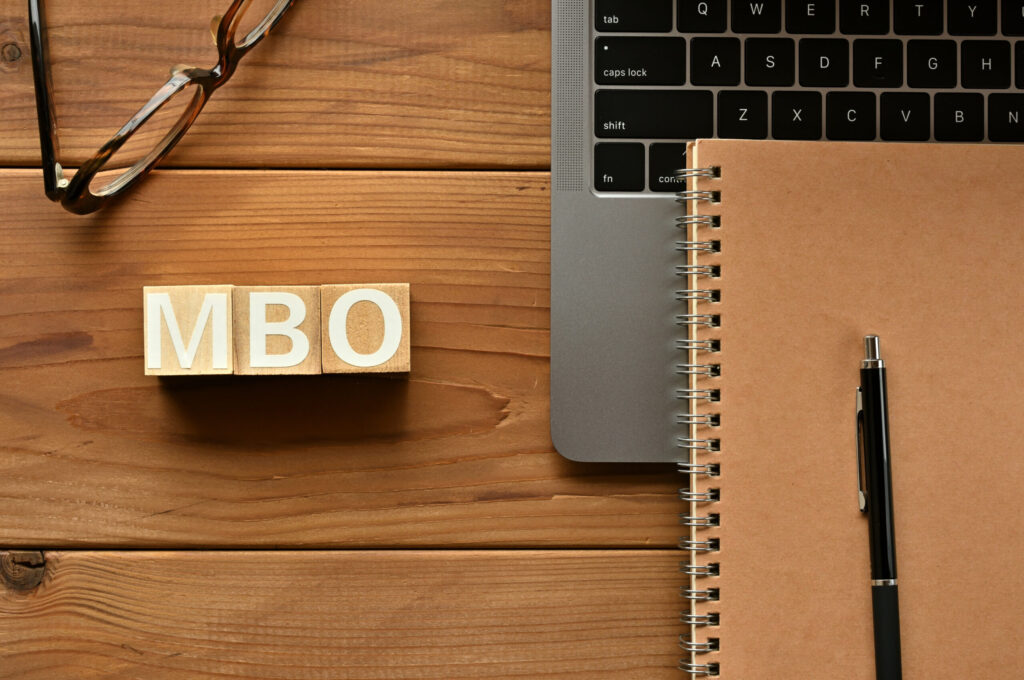
MBO(Management by Objectives)では、上司と部下とで設定した目標に対し、部下自身が期末に達成度を評価します。「何を達成すべきか」が明確になるため、従業員のモチベーションアップと主体制の促進に効果的です。具体的な目標設定により、客観的な評価が可能になります。ただし、目標設定の質や難易度の調整が難しく、短期的な成果に偏りがちな点には注意しましょう。
【適する場面】
- 営業部門や事業部など、数値目標が設定しやすい職種
- 個人の裁量が大きく、自律的な働き方が求められる環境
- 成果主義への移行期にある組織
OKR/Objectives and Key Results
OKRは、目標(Objective)と、その達成度を測る成果指標(Key Results)をセットで管理する制度です。たとえば「顧客満足度の向上」という目標に対し、「問い合わせ対応時間を24時間以内にする」といった、測定可能な指標を設定します。
MBOとの主な違いは、目標設定の考え方と評価への反映方法です。MBOは、個人の目標達成度を直接評価に結びつけます。一方でOKRは、会社と個人の目標を連携させることで、組織全体の方向性を統一することが特徴です。
近年では、OKRの「透明性の高い目標管理」を活用する企業が増えており、評価制度を補完するフレームワークとして注目されています。
【適する場面】
- 変化が激しく革新性が求められる業界(例:IT企業、スタートアップ企業)
- プロジェクトベースで働くチーム
- 組織全体の連携を強化したい企業
360度評価
360度評価は、上司・同僚・部下など、複数の関係者から多面的に評価する制度です。多くの意見を集められるため、従業員の行動特性や能力を正確に把握しやすくなります。自己認識と他者認識のギャップを明確にしやすく、成長につなげることも可能です。たとえば、自分では「チームをしっかりサポートしている」と思っていても、部下からは「指示が曖昧なことがある」といった評価を受けるなど、一人では気づかない部分が明らかになります。
ただし、複数の評価者が評価シートに記入するため、負担が大きい点には注意が必要です。
【適する場面】
- 管理職やリーダー層を育成する時期
- チームワークが重視される職場環境
- 組織のコミュニケーション改善や人材開発に重点を置く
バリュー評価
バリュー評価は、企業の価値観(バリュー)を実践する姿勢や行動に着目し、評価を行う制度です。業績や成果だけでなく、「どのように仕事に取り組んだか」「企業文化に合致した行動を取れたか」を重視します。組織における価値観の浸透と統一を図り、長期的な企業文化の醸成に効果的です。ただし、価値観(バリュー)は抽象的になりがちなので、具体的な行動指標に落とし込む工夫が欠かせません。
【適する場面】
- 企業理念やミッションを重視する組織
- サービス業や接客業など、顧客との関係性が重要な業界
- 多様な人材が集まるグローバル企業
年功序列
年功序列では、勤続年数や年齢に応じて、給与や役職が段階的に上昇します。日本における、伝統的な評価制度です。従業員に長期的な安定とキャリアを提供し、企業への忠誠心を醸成する効果があります。しかし、グローバル化や成果主義の浸透により、個人の能力や貢献度を適切に反映しにくい点が課題となっています。現在は多くの企業で「ほかの評価制度」への移行が進んでおり、年功序列の導入企業は減少傾向にあります。
【適する場面】
- 長期的な人材育成が求められる業界(例:製造業、金融業)
- 技能や経験の蓄積が価値となる職種
- 伝統的な企業文化を維持したい組織
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、高い成果をあげる優秀な人材と比較し、評価する手法です。高い成果を挙げる人に共通する行動特性や能力(コンピテンシー)をモデル化し、コンピテンシーに対し、どの程度能力を発揮したかを測定します。コンピテンシーとなるモデルは、実在する社員のケースもあれば、実在しない理想像の場合もあるでしょう。職務や役職ごとに、具体的な行動基準を設定できるため、評価の客観性と公平性を高められます。
【適する場面】
- 専門職や技術職が多い組織
- 人材の能力開発に力を入れる企業
- 職種や役職が多様で、各自に求められる能力が異なる大企業
正しい人事評価制度の特徴
適切な評価制度には、以下のような特徴があります。主な内容は、以下の通りです。
公平性がある

適切な人事評価制度は、明確な評価基準と統一された評価軸で従業員を判断するため、公平性を確保できます。軸にそって判断すると評価担当者の主観が入らず、誰がおこなっても同じ結果になるため、制度に対する納得度も高まるでしょう。
納得度が高まれば、「この会社で頑張って働こう」と思えるため、生産性向上や愛社精神にもつながります。
企業・従業員双方が成長できる
評価制度を設ける目的の1つに、企業・従業員双方の成長があげられます。
効果的な人事評価制度は、企業ビジョンと連動した評価基準を設けることが多いでしょう。従業員の企業目標への貢献度に応じて、評価が決まることも特徴です。目標達成に向けて、自身に不足する能力を補ったり、得意分野の能力に磨きをかければ「従業員の成長」につながります。
成長した従業員が多くなれば、企業としてパワーアップできるため、企業の成長にも直結します。
シンプルである
さまざまな内容を盛り込んだ「ボリュームがある評価制度」は、実は評価制度としての機能は低い可能性があります。
なぜなら、内容を盛り込みすぎると複雑化し、制度の本質が見えなくなるからです。また評価担当者が、制度内容を正しく理解できない可能性もあるでしょう。複雑な評価制度は、次第に形骸化する傾向にあります。
一方でシンプルな評価制度は、評価の要点を絞り込む必要があるため、制度設計をする際に「評価の本質的な要素を見極める」必要があります。シンプルだからこそ評価担当者にとって理解しやすく、運用面での負担も軽減できるでしょう。
不適切な評価制度の弊害
不適切な人事評価制度では、従業員の成果や能力について、適正に評価することが難しくなります。ここでは、不適切な評価制度がもたらすデメリットについて見ていきましょう。
生産性低下

不適切な評価制度は、従業員の頑張りを正しく評価できないため、意欲の高かった従業員のやる気も削いでしまいがちです。
意欲が低下すると、業務に身が入らないため、最低限の仕事をやればよいと考える人も増えてしまいます。意欲が低い状態の従業員が集まれば、チームとしての生産性低下はもちろんのこと、企業全体の生産性も下げてしまうでしょう。
離職率が高まる
不適切な評価制度には、「自社に合っていない方法を導入」していたり、「評価担当者の主観が混じる仕組み」などの特徴が見受けられます。
自社に合っていない方法であれば、社員の頑張りを誤って評価してしまう可能性も否定できません。また評価担当者の主観が混じる仕組みであれば、上司の好き嫌いなどで判断したり、評価担当者が変わると異なる評価結果がつくといったリスクも考えられます。不公平な評価結果は、社員の離職も増長させてしまいます。
企業・従業員間のギャップが広がる
不適切な評価制度では、企業が求める行動や、成果の基準が従業員に正しく伝わりません。従業員は「どうすれば評価されるのか」が分からず、手探りで業務に取り組むことになります。一方の企業側は「なぜ従業員が期待通りに動かないのか」と疑問を抱きます。従業員が良かれと思って行った行動が評価されず、企業も意図した成果が得られないという悪循環が生まれます。
相互理解の欠如は、時間の経過とともに、企業と従業員の間に深い溝を作りがちです。信頼関係の破綻や、組織の結束力低下を招く要因となる可能性があるでしょう。
人事評価制度の正しい作り方
人事評価制度は、正しく作ることで適切に機能します。以下のステップに沿って、作成するとよいでしょう。
Step1:現状の把握/問題の抽出

人事評価制度は企業経営を支える重要な仕組みであり、組織が目指す「理想の姿」を実現するために役立ちます。
効果的な制度を構築するには、まず自社の現在地を把握することが不可欠です。現状を客観視し、潜在的な課題を特定することで、必要な制度設計の方向性が見えてくるでしょう。
たとえば、従業員の定着率が低く、離職者が絶えない状況だとします。現象の背景には、「慢性的な人材不足による職場環境の悪化」「従業員への過度な負担集中」などがあり、組織全体の生産性低下を招いている可能性があります。根本的な問題を見極めることで、評価制度を通じてどのような改善を図るべきかがわかるでしょう。
Step2:人事評価で「叶えたいこと」を目標として定める
Step1で現状把握と問題抽出を行った後は、これらの課題を解決するために「何が不足しているのか」を考察します。不足している要素を明確にすることで、人事評価制度を通じて実現すべき具体的な目標が浮かび上がってきます。
先ほどの「離職率の高い企業の例」で考えてみましょう。現状分析を通じて、「従業員が長期間働ける環境が整備されていない」「人手不足の状況下でも組織のモチベーションを維持できる体制が欠如している」といった不足要素が見えてきます。
不足要素を踏まえると、人事評価制度で実現したい目標は「従業員の定着率向上と、変化に対応できる組織体制の構築」となるでしょう。
Step3:評価項目・評価基準を決める
Step2で決めた目標達成を念頭に置き、従業員をどのように評価すれば「目標達成ができるか?」を考えます。
目標達成を目指すには、「従業員が目標をどの程度達成できたか?」を判断する評価項目・評価基準が不可欠です。
評価基準では、主に「能力評価・業績評価・情意評価・年功評価」が用いられ、企業の目的に準じて各割合が変化します。
ただし、昨今では「年功評価」を採択する企業は減っています。
また評価項目・基準について、明確に言語化する点も欠かせません。明確になることで、従業員への理解が深まり、目標達成の速度も加速します。
Step4:評価方法・ルール・処遇への対応を決める
Step3までで評価の骨組みを決めたら、評価方法やルール、処遇への対応を決めていきましょう。
「A、B、C、D、E」といった5段階に設定するケースや、中心化をさけるべく真ん中を設定しない「1、2、3、4」といったケースもあります。
また評価結果について、「どういった結果をどの程度処遇に反映させるか?」の規定も用意しましょう。きちんと評価を下せる「評価担当者」の選出も、重要な要素です。
Step5:制度内容を全社員に周知する
制度内容が決定した後は、全社員への周知が欠かせません。十分な説明を行わずに制度を開始すると、評価の目的や方法が不明確なまま運用されることになり、従業員に不透明さを印象付けてしまいます。また事前の説明なしに制度を導入すると、従業員は「経営陣から一方的に押し付けられた制度」という印象を持ちやすくなり、制度への協力的な姿勢を期待しにくくなります。
周知の方法としては、全社員を対象とした説明会の開催が効果的です。同時に、説明会の内容を書面にまとめて配布するのもおすすめです。
人事評価制度を有効活用するための工夫
人事評価制度は、導入するだけでは十分な効果を発揮しにくいでしょう。制度を機能させるには、ポイントを押さえる必要があります。以下のポイントを押さえ、人事評価制度を有効活用できるようにしましょう。
1on1を継続的に開催する

定期的な1on1面談は、評価制度を成功に導くことに役立ちます。
1on1で上司と部下が対話することで、目標の進捗状況を把握でき、必要に応じて軌道修正を行えるでしょう。また、悩みや課題を相談できる環境ができることで、安心して業務に取り組みやすくなります。
継続的なコミュニケーションを通じて、従業員は日頃から、自分の成長状況や課題を把握できます。評価時期に突然結果を告げられるのではなく、普段から自身のパフォーマンスを客観視できるため、最終的な評価結果への納得度も高められるでしょう。
評価結果をフィードバックする
評価結果を伝える際に、点数や等級の通知だけでは不十分です。従業員が成長するには、「具体的に何が評価されたのか」や「どういった部分に改善の余地があるか」を明確に伝える必要があります。良かった点については、具体的な行動や成果を挙げて称賛し、改善点については建設的なアドバイスとともに今後の方向性を示すとよいでしょう。
丁寧なフィードバックは、モチベーション向上につながるだけでなく、上司と部下の信頼関係の構築に役立ちます。透明性のある評価プロセスは、組織全体の健全性を高められるでしょう。
ITツールを有効活用する
ITツールを活用すると、目標設定・進捗管理・集計・フィードバックの記録まで、一元管理が可能になります。すると、手作業による煩雑な業務が削減されるという理由から、評価業務全体の効率がアップします。過去の評価データを蓄積・分析すれば、個人の成長軌跡や組織全体のパフォーマンス傾向も可視化できるでしょう。
また、評価プロセスが透明化されることで、従業員は「自分がどういった基準や指標で評価されているか」を把握できます。透明性が高まると、モチベーションアップや帰属意識向上につながり、組織全体のパフォーマンス向上も期待できます。
人事評価制度の作成で必ず押さえたいこと
適切な人事評価制度を用意するために、作成段階で押さえたい内容は以下の通りです。
評価エラーを発生させない仕組み作り

評価エラーとは、評価担当者の主観や価値観が影響し、正しい評価結果が導けない現象を指します。
評価エラーが発生すると「不公平な評価結果」になるため、従業員から不満が出やすくなります。
エラー発生を防ぐには、評価制度を作成する際に、評価基準を明確にする点が欠かせません。
評価の軸をもとに判断するので、評価担当者の主観が反映しにくくなります。
評価エラーについて詳しく知りたい場合には、以下の記事もチェックしてみてください。
目標からプロセスまで可視化させる
評価制度は「評価制度を通じて叶えたい目標」を念頭に置き、その目標達成に向かって適切なプロセスを踏むことが重要です。
目標と目標に向かうまでのプロセスが可視化できると、プロセスを踏み間違いにくく、企業と従業員双方の認識すり合わせに役立ちます。
そのため、人事評価を作成すると同時に、可視化できる仕組みも考えると良いでしょう。
可視化する際には「人事評価システム」などのツールを使うと、スムーズに実行できるのでおすすめです。
コミュニケーション方法を決める
人事評価制度をうまく機能させるには、制度設計だけでなく、運用面での取り組みを意識することも重要です。具体的には、以下の要素が必要になります。
| ・人事評価制度の概要・やり方を社内に浸透させる ・適宜「問題が発生していないか?」を確認する ・評価結果を適切にフィードバックする |
上記の実施には、コミュニケーションがかかせません。そのため、人事評価を作成すると同時に、コミュニケーション方法も決めておきましょう。
人事評価制度の概要・やり方の浸透では、全社員に対して説明会を開催すると良いでしょう。「問題が発生していないか?」の確認や、評価結果のフィードバックには、定期的な1on1が役立ちます。
1on1ミーティングのNG行動とは?意味ないを防ぐ進め方を解説
最新の法令や現代社会の動向を意識する
人事評価制度を継続して機能させるには、法令の変更や社会情勢の変化に応じて、制度を見直すことが大切です。たとえば、労働関連法令の改正により、評価項目や評価基準の調整が必要になるケースがあります。
また、現代社会の変化(例:テレワークの普及/ダイバーシティへの配慮)から、時代に応じた内容を反映することもあるでしょう。最新の法令や現代社会の動向を定期的に意識し、人事評価制度に反映させることで、時代に即した評価システムを維持できます。
制度の定着に向けたサポート体制を用意する
人事評価制度を用意しても、組織に定着しなければ、その効果が半減されてしまいます。定着させるには、評価者に対して、継続的に教育することが不可欠です。「評価スキルの向上」「評価基準の統一」「フィードバック技術の習得」など、評価者が自信を持って評価業務に取り組めるようサポートします。
同時に、全社員に対しても、人事評価制度の目的や意義を説明することが大切です。評価を受ける側の理解と協力を促進することで、人事評価制度の定着を促進できます。「定期的な研修会の実施」「相談窓口の設置」「制度運用に関するQ&Aを整備する」などもおすすめです。
人事評価制度の作り方でよくある質問(FAQ)
人事評価制度を作る際に、疑問が生じることもあるでしょう。ここでは、人事評価制度の作り方で「よくある質問」について解説します。
Q1: 人事評価制度はどのくらいの頻度で見直すべき?
A: 一般的には、年1回の見直しが推奨されます。しかし、法改正や組織体制の大きな変更があれば、年次見直しを待たずに見直すことも大切です。
また制度を導入したばかりの頃は、運用上の課題が見えやすくなります。そのため、最初の頃は四半期に一度程度で見直すのもよいでしょう。
Q2: 評価制度の導入にはどれくらいの期間が必要?
A: 人事評価制度の導入期間は、組織の規模や現状の制度整備状況によって異なります。しかし一般的には、3か月から半年程度を要するケースが多いでしょう。導入は、「現状分析→課題の抽出→評価基準と制度設計→システム構築→試行運用・本格運用」という段階を経て進められます。重要なのは、迅速な導入ではなく、組織に適した制度を丁寧に構築することです。
Q3: 小規模な会社でも評価制度は必要?
A: 小規模な会社においても、人事評価制度の導入は必要です。従業員数が少ないからこそ、一人ひとりの貢献度や成長を適切に評価し、公正な処遇を実現する必要があるからです。また小規模組織では、社長や管理者と社員との距離が近く、評価が主観的になりがちです。人間関係が密接であるため、「なんとなく」や「感覚的」な評価に陥りやすく、不公平感や不満の原因となることがあります。明確な評価軸を設定することで、主観的な判断を排除し、客観的で公正な評価を実現できます。
Q4: 評価結果が不満だった社員への対応は?
A: 評価結果に不満を持つ社員に対しては、コミュニケーションを通じた対応が不可欠です。個別面談の機会を設け、評価の根拠や理由を客観的に説明するとよいでしょう。評価項目ごとに具体的な事例を挙げながら、なぜその評価に至ったかを伝えます。同時に、今後の成長に向けた具体的なアドバイスや改善ポイントを提示し、社員の成長をサポートする姿勢を示しましょう。
評価制度構築が未経験でも大丈夫!シーグリーンなら手厚い導入支援あり
「人事評価システムを導入したいけれど、人事評価制度が存在しない」「評価制度の作り方がわからない」といったお悩みをお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
シーグリーンの人事評価システム『ヒョーカクラウド』なら、人事評価制度の構築経験がない場合にも安心して導入できます。専門コンサルタントが、企業の規模や業界特性に応じて、最適な評価制度の設計から運用開始まで手厚くサポートいたします。制度構築の知識やノウハウがなくても、段階的に進められる導入プロセスを用意しているので安心してお任せいただけます。
シーグリーンの人事評価システム『ヒョーカクラウド』について、詳細は以下をチェックしてみてください。
ポイントを押さえ、正しい人事評価制度作りを
人事評価制度は、適切な内容を設計し、継続的に運用することで効果を発揮します。当記事で解説した評価制度の作成・運用ポイントを参考にし、自社に適した制度を用意しましょう。また人事評価制度の導入後も、定期的な見直しや改善を行い、時代の変化に対応した制度運用を心がけることが大切です。
人事評価制度の導入は、一朝一夕にできるものではありません。継続的な見直しと改善を通じて、柔軟な制度運用を心がけましょう。
ヒョーカクラウドの成功事例について
評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?
ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。
Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。
評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。
-

- 建築・建設業
評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。
会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...
-

- 医療・福祉業
- 100〜299名
従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に
導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
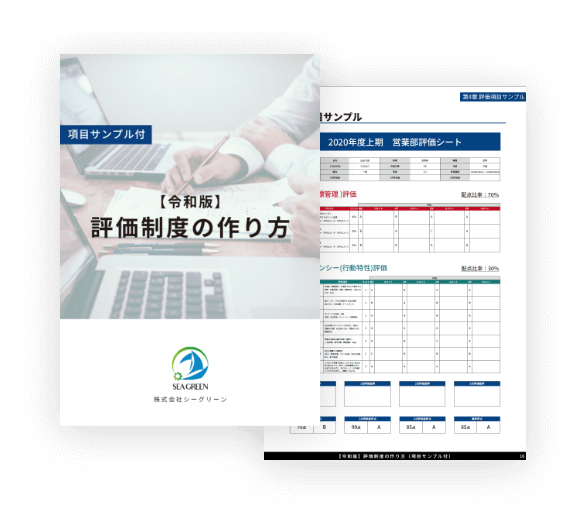
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル