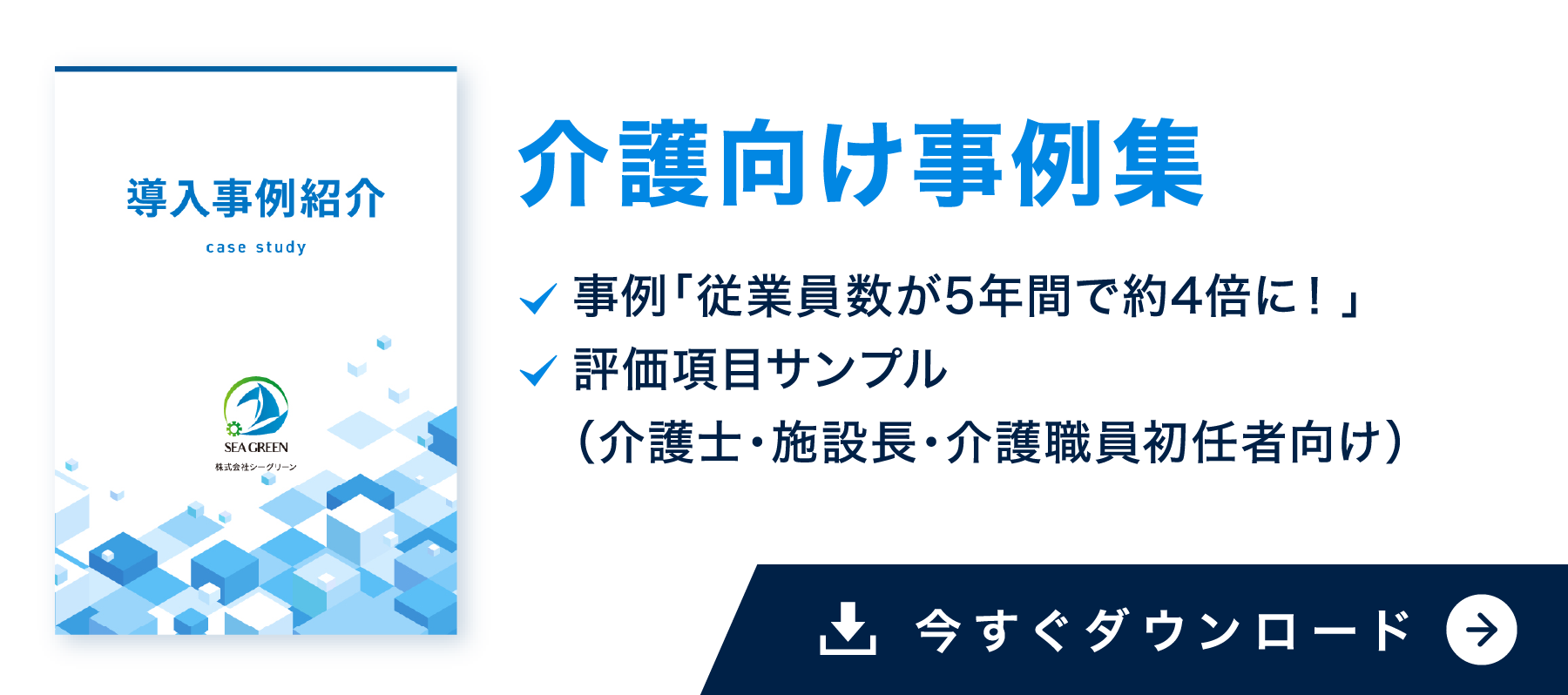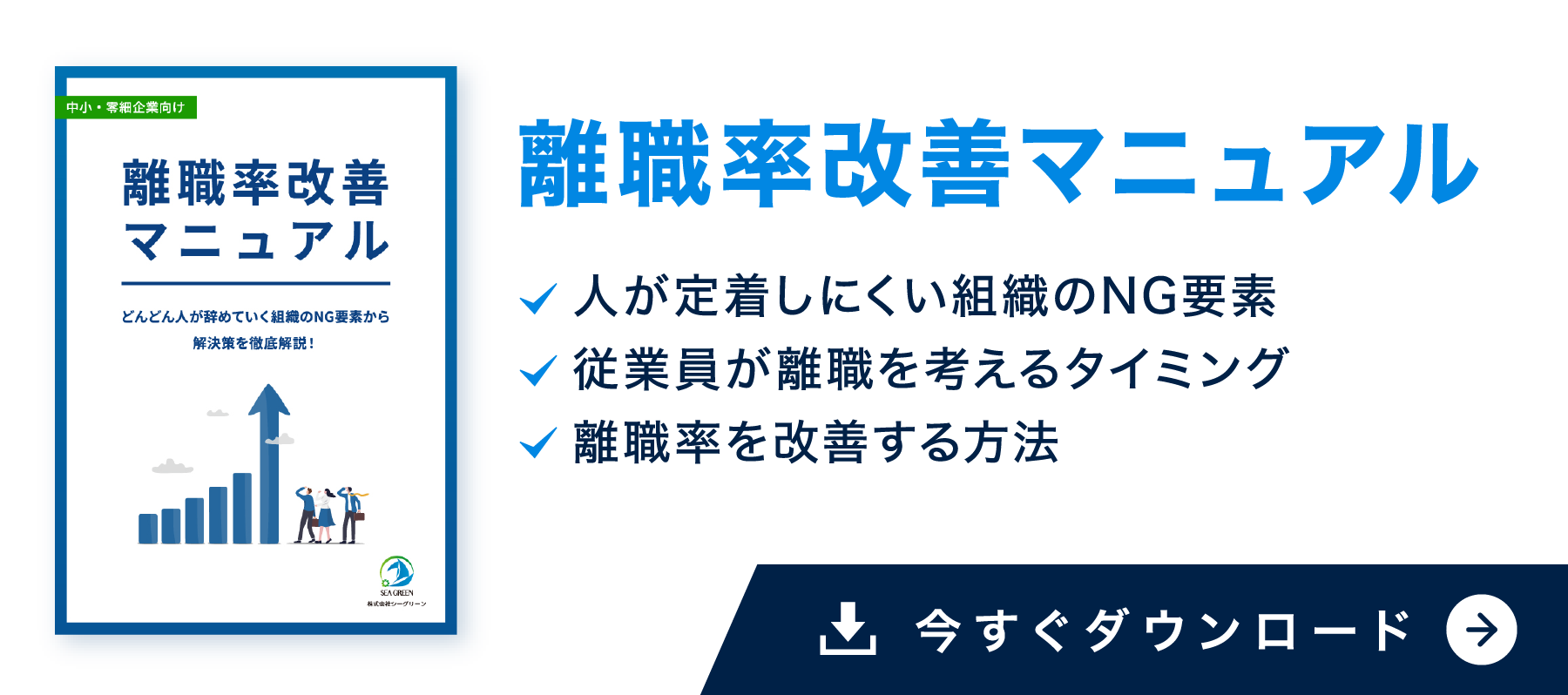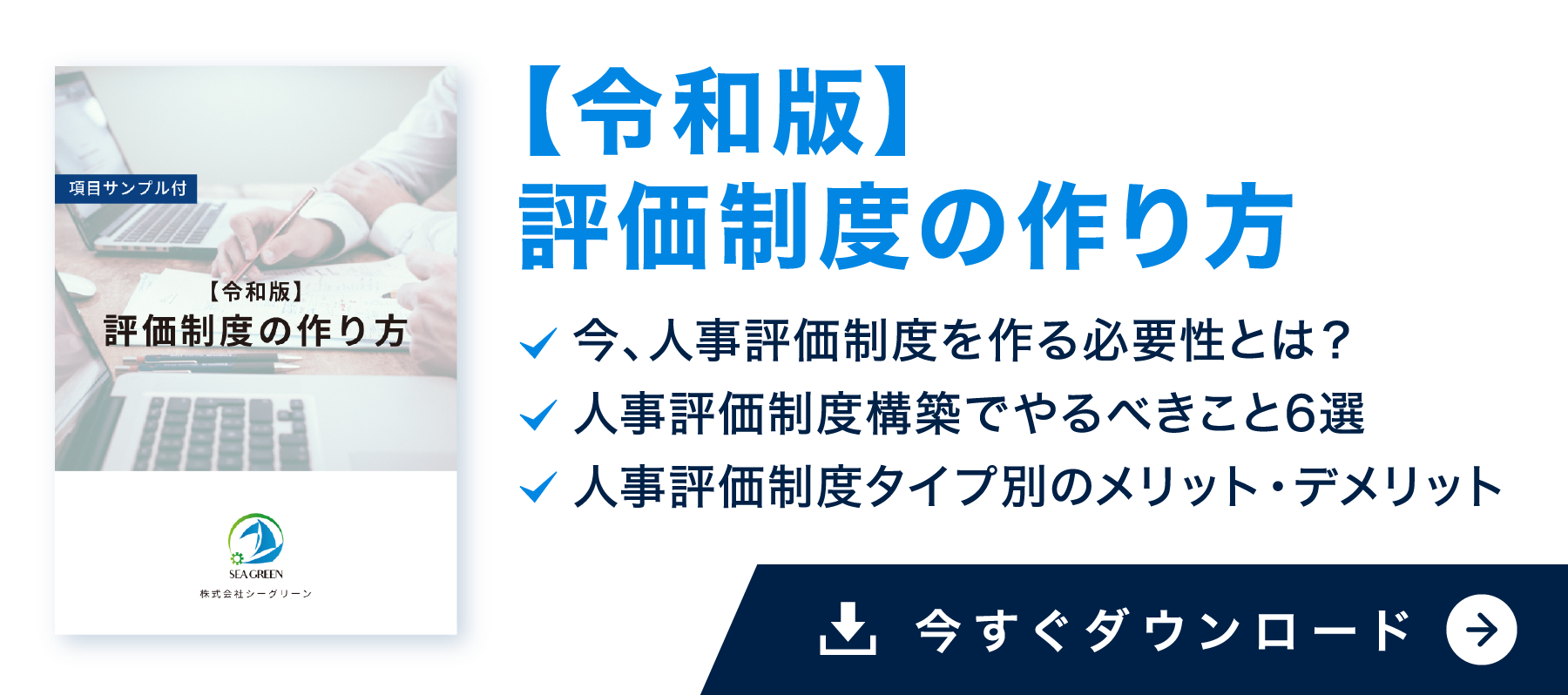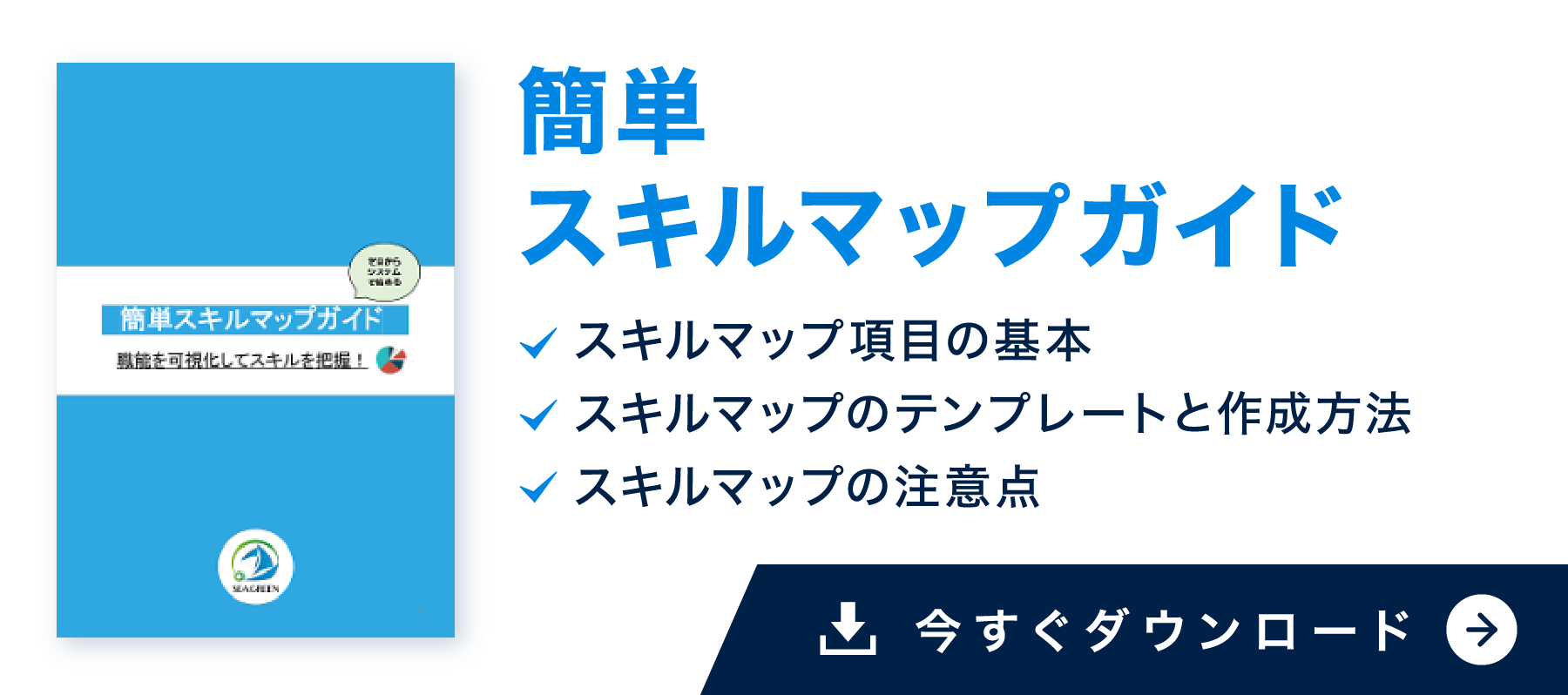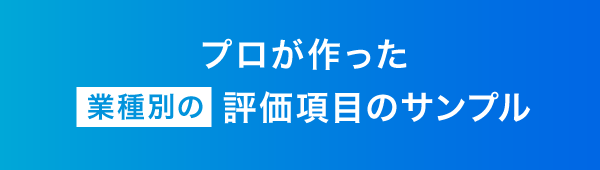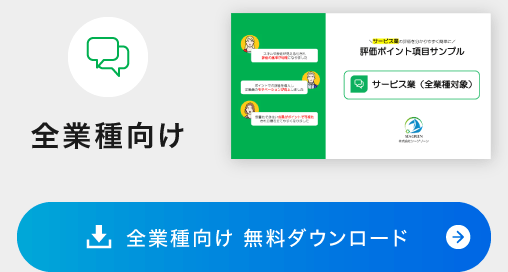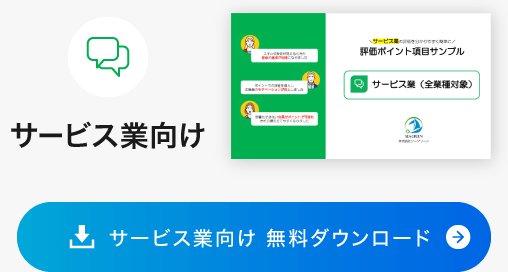急速に高齢化社会がすすむ日本において、介護業界でも大きな変革期を迎えています。昨今では、高齢者人口の増加による「2025年問題」と「2040年問題」も問題視され、現行の介護サービス体制では対応が難しくなると予想されます。
課題に立ち向かうには、業界全体の構造改革と持続可能な解決策が不可欠です。当記事では、介護業界の現状と将来の課題を分析したうえで、未来に向けた対策を探ります。
目次
介護業界の現状について

現在の介護サービスは、需要に対して供給が追いつかない状況にあり、人手不足が深刻な問題となっていることも事実です。高齢者人口の増加に伴い、介護ニーズが高まる一方で、介護職員の確保が困難な状況も続いています。
ニーズに対応できない状況を改善するには、働き方改革や処遇改善など、多角的な対策が必要でしょう。さらに、介護の質を維持・向上させる取り組みも、重要な課題だといえます。
2025年問題と2040年問題について

2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上となり引き起こされる「医療・介護需要の急増」と「介護人材不足の深刻化」という課題です。2040年問題とは、高齢者人口がピークを迎え、65歳以上が全人口の35%に達することで起こりうる課題を指します。健康状態や生活スタイルの変化による介護ニーズの複雑化と、生産年齢人口の急減による労働力不足などが該当します。
急速な高齢化に対応するには、介護体制の抜本的な見直しを含む、包括的な対策が課題です。持続可能な社会保障制度の構築に向けて、2025年問題と2040年問題の両課題に取り組む必要があるでしょう。
参考サイト:厚生労働省_我が国の人口について
介護業界の2025年・2040年問題/10年後も抱える課題
介護業界で予想される「将来の課題」は、複雑で多岐にわたります。将来的に予想される主な課題は、以下の通りです。
慢性的な介護人材の不足

介護現場における人手不足は、すでに深刻な問題として表面化しています。日本では「少子高齢化が今後も加速する」と予測されており、深刻な人手不足という状況は続く見込みです。
また介護職への就業意欲が低下している背景も、人材不足になる要因の1つでしょう。加えて、仕事の厳しさに対し「適切な評価や給与」が反映されなければ、人材不足なのに人が定着しないという、負のスパイラルを生じかねません。
高齢者ニーズの多様化
高齢者のニーズが年々多様化しているため、介護サービスは、画一的な対応では不十分になっています。「医療的なケアが必要な人」「社会的なネットワークを求める人」「趣味や活動に参加したい人」など、各自が持つ期待は異なるでしょう。
多様なニーズにこたえるには、きめ細やかなプロセスが不可欠です。一方で介護現場は、人材の確保に苦労しており、結果として高齢者が求めるサービスを十分に提供できないケースも見受けられます。
介護サービスにおける質の確保
介護サービスの質を確保することは、利用者の尊厳を守るうえで重要なものの、課題が山積みであることも事実です。介護現場では、統一された評価基準が不足しており、サービスの質にばらつきが見られることもあるでしょう。
質の高いサービスを提供するには、介護職員のスキル向上や教育の充実が求められます。しかし、サポートできるリソースが不足する傾向にあり、質の維持や向上が課題となっています。
財政的な制約と持続可能性
介護サービスは公的制度に基づいており、限られた予算で運営されることが多いです。しかし、高齢者人口の増加に伴う「サービス需要の拡大」という背景から、財政的な圧力がいっそう強まると考えられます。
「介護職への賃金引き上げ」や「質の高いサービス提供に向けた投資」が難しくなると、人材不足をさらに悪化させる可能性もあるでしょう。また、介護報酬の適正化や利用者負担の見直しなど、持続可能な制度設計が求められます。
2025年・2040年問題に向けた対策
2025年・2040年問題を乗り越えるには、さまざまな対策が必要です。ここでは、2025年問題・2040年問題に向けた「具体的な対策」について解説します。
技術革新による効率化の推進

介護現場における人手不足を解消するには、テクノロジーの活用が有効です。たとえば、センサー技術やAIを用いた見守りシステムの導入により、業務の効率化につながります。
またロボット技術の応用により、移乗や移動の支援など、身体的負担の大きい業務の軽減も期待できるでしょう。さまざまな技術革新を積極的に取り入れることで、限られた人材であっても、質の高いサービスを提供しやすくなります。
介護人材の確保と育成
介護人材の確保と育成は、緊急の課題です。まずは、介護職の魅力を高め、新たな人材を呼び込むための取り組みが必要でしょう。具体的には、処遇改善や労働環境の整備、キャリアパスの明確化などが挙げられます。
また、外国人材の受け入れや、元気な高齢者の活躍促進など、多様な人材の活用も検討に値するでしょう。さらに、介護職員のスキルアップを図るための教育・研修制度の充実も重要だといえます。
安定的な制度の土台づくり
持続可能な介護サービスを提供するには、安定的な制度が不可欠です。たとえば、介護保険制度の見直しや介護報酬の適正化を行うことで、サービス提供者が安定した収入を得やすくなります。安定的に収入を得られれば、従業員に適切な報酬を還元でき、サービスの質を向上させられるでしょう。
また、医療・介護との連携強化など、異なる機関が協力する体制を用意できれば、利用者のニーズに合わせた支援を行いやすくなります。
多様な人材活用による役割分担
多様な専門職が協力することで、限られたリソースを有効活用し、業務の効率化がはかれます。また介護という業務の特性を考慮すると、専門的な知識や技術を適切に配置することが重要です。
たとえば、介護職員が日常ケアを担当し、リハビリ専門職や栄養士が専門性を発揮することで、質の高いサービスを提供しやすくなります。多様な人材の協力により、より包括的な介護体制の実現が期待できます。
介護人材の評価を見直す重要性
介護人材の適切な評価は、業界全体の課題解決に影響を与えるといっても過言ではありません。ここでは、介護人材の評価を見直す重要性について解説します。
人材のモチベーション向上につながる

適切な評価は、介護職員のモチベーション向上に直結します。自身の仕事ぶりが正当に評価され、評価結果が処遇に反映されることで、仕事へのやりがいや誇りを醸成できるでしょう。
また評価結果をフィードバックすることで、自己の課題や成長の方向性がわかり、継続的な成長に役立ちます。適切な評価の実施による「ポジティブな循環」を生み出すことで、介護人材の定着率向上にも寄与するでしょう。
業務の質アップを促す
明確な評価基準を設ければ、介護職員は「自身が行っている業務の質」を客観視できます。日常的に評価項目を意識することで、日々の業務改善や、スキルアップへの動機づけにもつながるでしょう。
また評価結果を分析することで、自身の課題が明らかになり、業務の標準化や効率化にも役立ちます。評価制度は、介護人材の自己成長を促し、介護サービスの質向上に貢献する重要な仕組みだといえます。
適切な評価が離職率の低減に寄与する
介護職員の高い離職率は、業界全体における重要課題の1つです。背景には、「処遇の問題」や「やりがいを感じられない」などが挙げられます。適切な評価制度を導入し、職員の頑張りが評価される仕組みを整備すれば、働く価値を実感しやすく、離職率の低減も期待できます。
定期的な面談も実施すれば、職員の悩みを早い段階で察知しやすく、離職の意志がかたまる前に適切なフォローができるでしょう。また「スマイル評価 +クラウド」のような人事評価システムを使えば、職員のパフォーマンスデータを可視化できるため、より効果的なサポートやキャリアアップの機会を提供することが可能です。
人事評価システムを見直し、介護業界を変革しよう
介護業界が抱える課題を解決するには、人事評価システムの見直しが不可欠です。評価基準の明確化と、評価結果のフィードバックにより、介護人材の成長と業務の改善を促せます。また、処遇への反映など、評価結果の活用方法を工夫することで、モチベーションの向上や離職率の低減にもつなげられるでしょう。
人事評価システムは、介護業界の変革を推進するための重要な基盤といえます。介護業界に強い人事評価システムをお探しの場合には、「スマイル評価 +クラウド」がおすすめです。人事評価制度の構築や運用面までサポートを希望する場合には、ヒョーカクラウドがパッケージとして含まれた「スマイル評価 +制度構築 package」が適するでしょう。

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【介護福祉向け】導入事例紹介・評価項目サンプルをプレゼント!
【介護福祉向け】導入事例紹介・評価項目サンプル
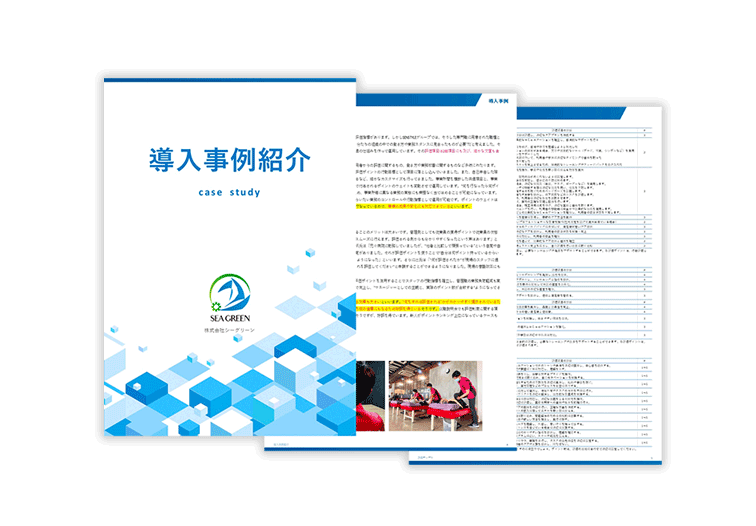
この資料で分かること
- 【成功事例】従業員数が5年間で約3倍に!
280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に - 評価項目サンプル
(ケアマネージャー、施設長、介護職員) - シーグリーンのサービス紹介