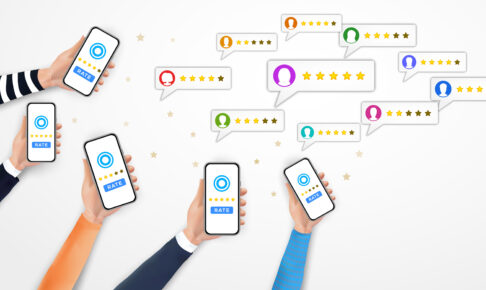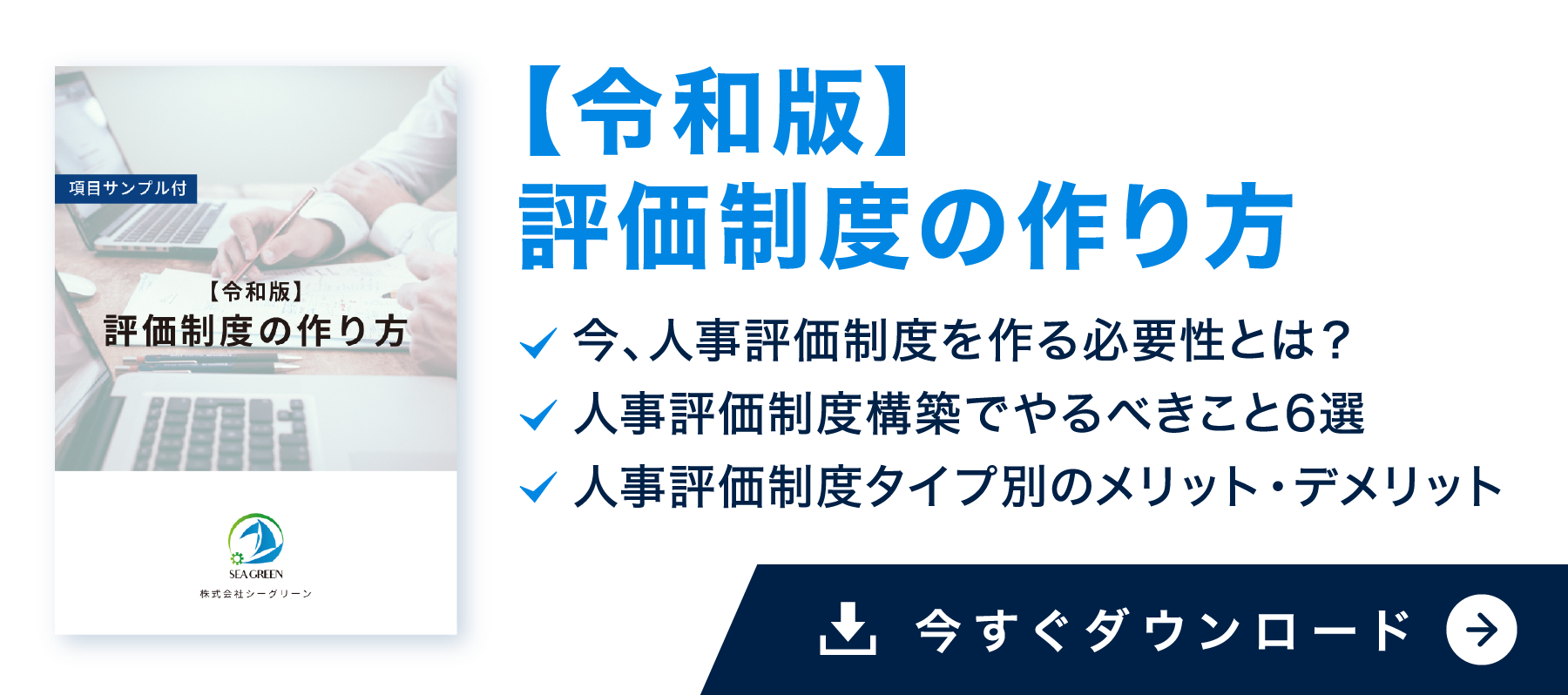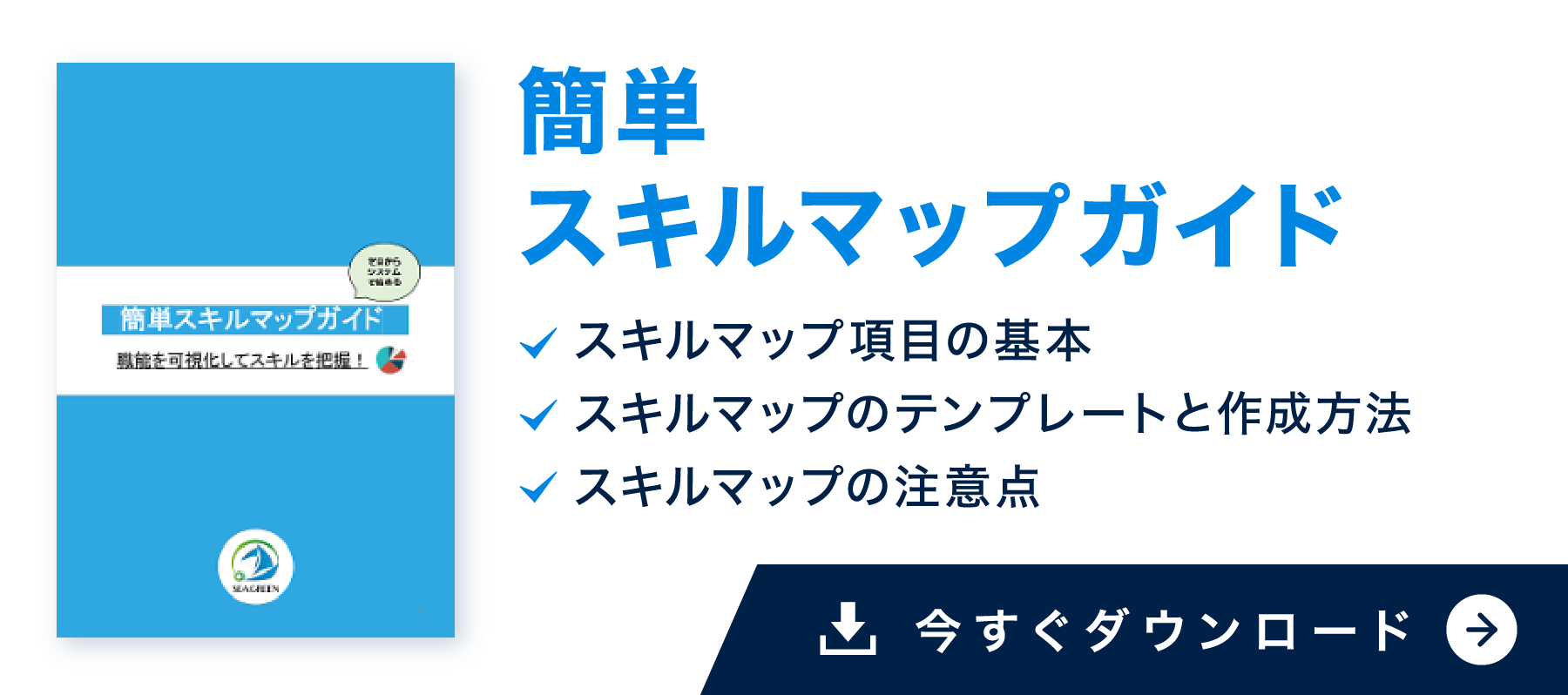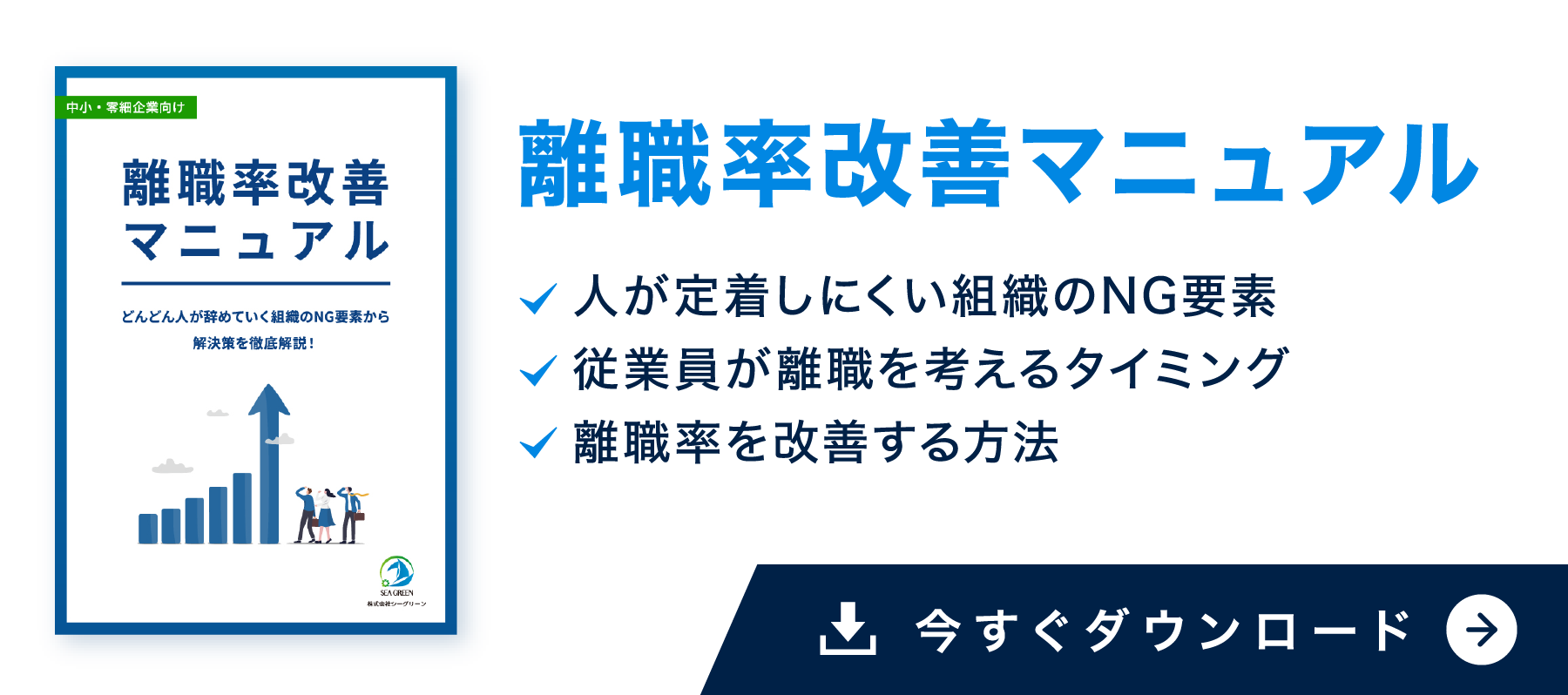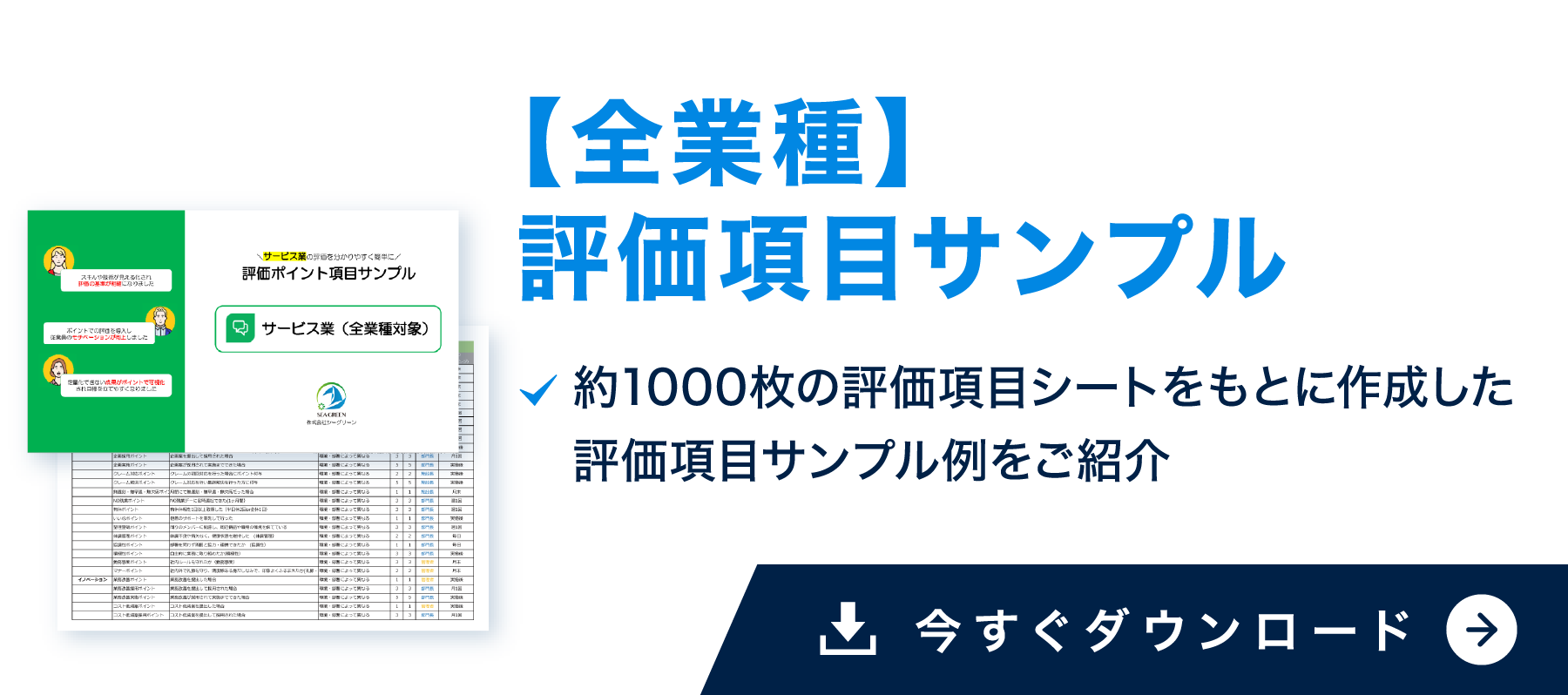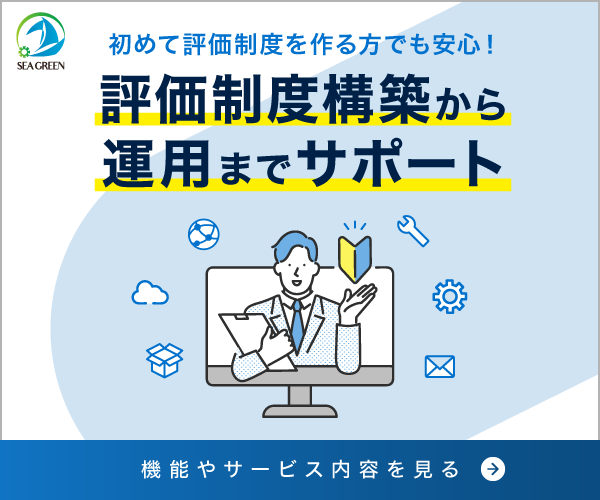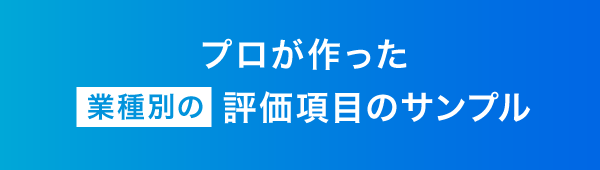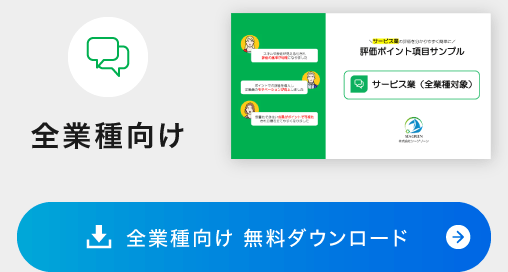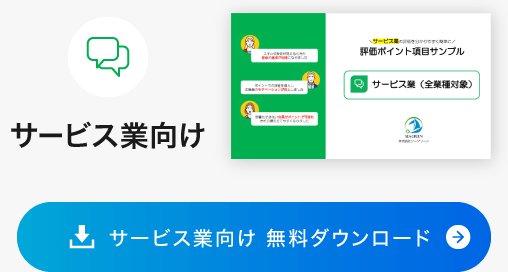人事評価制度にもトレンドがあり、時代の流れに即して内容も変化します。2024年の昨今において、人事評価制度のトレンドはどういった内容なのでしょうか?
当記事では、2024年における「人事評価制度のトレンド」を紹介するとともに、各トレンドのメリット・デメリットについても解説します。人事評価制度のトレンドを知り、適切な制度を取り入れたいと考える場合には、ぜひ当記事をお役立てください。
目次
2024年の人事評価制度_5つの特徴とは?
人事評価制度には、時代に応じた特徴が見受けられます。2024年の人事評価制度において顕著な特徴は、以下の通りです。
1、役割主義に移行している

年功序列制度が下火になり、1990年代からは成果主義にシフトする企業が増えたものの、昨今では成果主義から「役割主義」に移行する事例も増えています。
成果主義は、仕事の成果・結果に応じて、評価が決まる仕組みです。しかし、「成果だけに執着する」や「チームワークが弱くなる」といったマイナス面も目立つようになったため、職務や仕事内容に応じて報酬や等級が決まる「役割主義(ジョブ型)」に移行する企業が増えています。
2、行動が重視されている
前述の通り、昨今では担当の職務や仕事内容に応じて評価する役割主義がトレンドです。
役割主義では、与えられた役目を果たす度合いによって報酬や待遇が決まるため、従業員の行動が重視されます。成果主義がトレンドの時代は、「結果を出したか?」という点が重視されていたものの、昨今では「きちんと役目を遂行したか?」という、行動そのものが大切だからです。
3、評価サイクルが短期化し、リアルタイム化も
成果主義が主流な時代では、成果の計測期間を設けるべく、1年や半年ごとに評価を実施する傾向にありました。昨今のように役割重視の時代下では、行動を重視することから、評価に対して長い期間を設ける必要がありません。
むしろ行動を評価するには、評価サイクルを短期化する方が好都合なため、評価サイクルを短期化する傾向にあり、リアルタイム化する事例も見受けられます。
4、ランクづけが廃止される
IT技術の急速な進歩や国際化によって、環境の移り変わりが激しい時代になりました。そのため、以前のように従業員を「A・B・C」などとランクで管理しても、決定したランクが意味をなさなくなるケースも多く、ランクづけが廃止される傾向にあります。
少子高齢化により「労働者の獲得に苦戦する企業」も見受けられ、一人ひとりを丁寧に育てる動きが活性化したことも、ランクの廃止につながっています。
5、評価結果や評価基準がオープンに
今までは、評価結果や評価基準について、従業員に公開しない流れが主流でした。一方昨今では、評価結果や評価基準も開示した方が良いと考える企業が増えており、オープンにする事例も増えています。
評価結果を示せば、透明性が出て従業員の納得感が増し、評価基準を開示すれば、どのように行動すれば良いかがわかるためモチベーションアップにつながります。
人事評価制度のトレンドを導入するメリット・デメリット
人事評価制度のトレンドを、自社の制度に取り入れたいと考える人もいるでしょう。ここでは、人事評価制度のトレンドを採択する場合について、メリットとデメリットを解説します。
トレンドを導入するメリット

人事評価制度は、従業員の頑張りを評価するだけにとどまらず、中長期的な経営計画にもとづき、会社の目的を実現することが目的だと言えます。また目的は、時間の経過とともに、変化するものです。
トレンドの人事評価制度を採択すると、時代に即した判断につながり、ライバルに負けない組織づくりにつながる可能性があるでしょう。
トレンドを導入するデメリット
「流行しているから」といった安易な理由でトレンドを導入すると、自社に合わず思うような結果が出ないこともあります。自社の現状や方針を見極めたうえで、相性の良い内容を選ぶことが重要です。
また自社に合った内容を採択しても、担当者の評価スキルが不足していると、適切な結果を導けない可能性があるため、評価担当者に向けた適切な教育も必要です。
2024年の人事評価制度_8つの具体的な種類を紹介
つづいて、2024年における人事評価制度について「8つの具体的な内容」を紹介します。自社の目的に応じて、適切な内容を選ぶことが大切です。
1、リアルタイムフィードバック

リアルタイムフィードバックとは、読んで字のごとく、リアルタイム(=即時)にフィードバックを行なう手法です。上司が、部下の成果や働きぶりをこまめにフィードバックできるため、軌道修正の容易さが特徴です。頻繁にコミュニケーションを取れるため、組織の活性化にも寄与します。
ただしフィードバックの頻度が多すぎると、上司・部下の双方に負担がかかるため、適切な頻度の見極めが必要です。
2、バリュー評価
バリュー評価とは、企業が設定したバリュー(=自社の社員としての行動基準)を実践・達成できているかを評価する手法です。
バリュー評価を実施すると、企業の方針や価値観にそって、従業員がどれだけ忠実に行動できたかがわかります。またバリュー評価を通じ、企業方針を浸透させることも可能です。ただし数値で評価しにくいため、主観の入らない仕組みが必要になります。
3、OKR
OKRとは、「会社(またはチーム)の目標」と「個人の目標」をリンクさせ、達成度を評価する手法です。OKRでは双方の目標をリンクさせるため、会社と従業員の認識がズレにくいといったメリットがあります。
ただし、複数の部署を兼任する従業員は、目指す目標が多くなり「従業員の負担が増える」可能性があるため、バランスを考えることが大切です。
4、360度評価
360度評価とは、1人の被評価者に対し、複数の関係者が多面的に評価を行なう手法です。自身や取引先の評価が加味されるケースも見受けられます。多くの人が評価するため、客観的な評価が実現し、上司が見えていない部分を評価できます。
しかし、チームメンバーと口裏を合わせ、お互いに甘い評価をつける事例も存在することから、被評価者と密接に仕事をする人には「評価項目を限定させる」などの対策が必要です。
5、ノーレイティング
ノーレイティングとは、従業員にABCなどのランクをつけないかわりに、リアルタイムで目標設定を実施し、都度評価を実践する手法です。
即時に評価するため、急な環境の変化にも柔軟に対応できます。また、リアルタイムでの評価という特徴から、評価を行なう頻度が多くなり、コミュニケーションの活性化にもつながります。ただし、評価する頻度が多すぎると評価者の負担が増えるため、実施するスパンに配慮が必要です。
6、コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、企業が理想とする優秀な社員像にもとづき、その人物の行動特性と比較して評価する手法です。評価基準が明確で評価しやすく、人材の育成にも役立ちます。理想とする社員像は、実在の社員を参考にするケースもあります。
ただし、社員像の抽出に時間を要するため、開始までに時間がかかる傾向にあります。また「取り巻く環境」や「会社の立ち位置」の変化に応じて、理想の社員像も変える必要があるでしょう。
7、ピアボーナス
ピアボーナスとは、ピア(=仲間)同士で評価しあい、ボーナス(=報酬)を贈りあう制度です。一般的にボーナスはポイントでカウントし、たまったポイントを商品、サービス、お金などに変えます。積極的に社員同士で褒めあうため、コミュニケーションの活性化や良好な人間関係の構築につながります。ただし、「同じ相手には連続して評価できない」など、細かいルールが必要です。
8、パルスサーベイ
パルスサーベイとは、従業員の満足度を、パルス(pulse/脈)をはかるように短いサイクルで実施する調査手法です。調査スパンが短いため、従業員の心の動きを迅速に把握できます。以前の結果と比較すれば、問題点も見つけやすいでしょう。
ただし設問数が多すぎると、回答する従業員はもちろんのこと、集計や分析を実施する企業サイドにも負担がかかります。パルスサーベイの実施では、適切な質問を厳選することが大切です。
自社に合った人事評価制度を選ぶことが大切
人事評価制度には、時代に即したトレンドが存在するものの、流行しているから採択するのではなく「自社に合った内容を選ぶ」姿勢が必要です。
自社に合った人事評価制度を選ぶには、自社の状況を踏まえたうえで、達成したい目標を精査する必要があります。目標を決定したら、実現に向けてふさわしい人事評価制度を選びます。とはいえ、適切な人事評価制度選びには、一定の知識が必要です。
自社に合った人事評価制度選びで迷う場合には、株式会社シーグリーンの「人事評価構築パッケージ」がオススメです。人事評価システムの構築・設計からサポートし、貴社にベストな内容をご提案します。
ヒョーカクラウドの成功事例について
評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?
ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。
Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。
評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。
-

- 建築・建設業
評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。
会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...
-

- 医療・福祉業
- 100〜299名
従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に
導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報
山本 直司(やまもと ただし)
株式会社シーグリーンHR事業部
評価制度構築チームマネジャー
これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。
構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。
【令和版】評価制度の作り方をプレゼント!
【令和版】評価制度の作り方
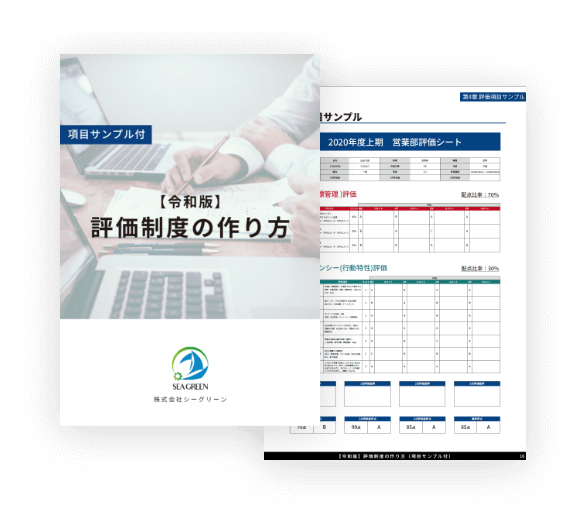
この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル